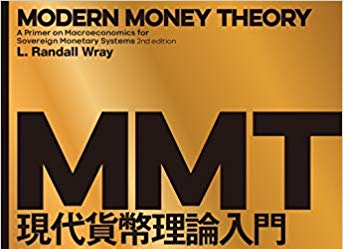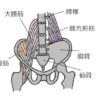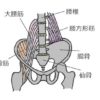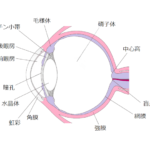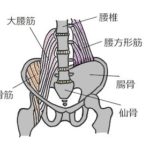目次
●速読は光の読書
栗田先生によれば、読書には音の回路を使う「音の読書」と、光の回路を使う「光の読書」があり、「従来の読書は音の読書、SRSで学ぶのは光の読書」とのことだ。
見ること(情報入力)と読むこと(情報処理)は違う。目で文字を見てその映像を脳に入力するのは一瞬でできるが、その文字から構成される文章の意味を考えるには時間がかかる。普通は脳がその解析を終えて「意味がわかった」となるまで、目は文章の上で動きを止め、新たな入力をせずに待っている。
速読の訓練ではいったんそのリミッターを外してしまう。脳による文章の意味の解析が終わらないうちに目を次の文字、次の行、次のページに動かして、どんどん新しい情報を入力していくのだ。
意味の解析が終わらないうちに次々と処理すべき新しい映像情報が流れ込んでくることで、脳はパニックになる。
そこで脳に十分な適応力があれば、「このままではだめだ」となって、新しい状況に対応して処理の方法を抜本的に変え、ドラスティックな革命を起こす。
文字は本来、視覚的な情報なのだが、脳では聴覚情報である言葉と紐付けられており、普通は脳内の音声用回路で処理されている。
だがもともと人間の場合、外部から届く情報の8割が視覚情報とされ、脳内でもそれを処理する領域のほうが音声情報を処理する領域よりはるかに大きく、処理スピードも比較にならないほど速い。
このため脳は音声回路では処理しきれないほど大量の情報が文字の形で入ってくると、これまで文章の意味を解析するのに使っていた脳の音声領域での処理をあきらめ、視覚領域で文字情報の処理を始める。
これが「光の読書」である。
速読の訓練は、脳内にこの情報処理革命を引き起こすためのカリキュラムなのだ。
一般的な読書で使われる「音の回路」は、表層意識の中にあるという。
音の回路は本来、出力用の回路であって、情報処理には向いていない。
表層意識は記憶容量が小さく作業能力も低い。人間の情報処理作業の大部分は実は潜在意識で行われ、処理結果も潜在意識内の格納スペースに収納されている。
しかし表層意識は意識の中のトップであり、企業でいえば経営者にあたり、潜在意識に作業を命ずることができる。
仕事で煮詰まった場合に、睡眠を取ると解決策が思い浮かぶことがある。これは睡眠の間に潜在意識が、表層意識の与えたテーマに沿って作業を行った結果だ。
いわゆる「気が乗らない」という状態は、頭(表層意識)ではやらなければと思っているのに、潜在意識がついてこない状態である。
光の回路を使う「光の読書」を行うためには、経営者たる表層意識が「理解」という作業を自分でするのをやめさせ、従業員たる潜在意識に作業を分担して行うよう命令させなければならない。
たとえば目の焦点が合ったところからの情報は表層意識に向かいやすいので、周辺視野からの情報を利用する訓練(エッジビュー)を行う。また文字を意味あるものとして捉えると音の回路に入ってしまうので、記号、模様として認識するようにする。
光の読書で得られる本の理解とは「光の理解」であって、それは音の読書で得られる本の理解とはそもそも異質なものだという。
●業界人には高いハードル
結局、筆者は数字上の「初速の10倍」は達成したものの、「光の読書」「光の理解」の領域を知ることはできないまま、5回の講習を終えることになった。
講習中は一時的に速くなった読書スピードも、しばらくしたら元に戻ってしまった。
SRSには「水の底に足を着けて歩くのが普通の読書なら、足を着かずに泳ぐのが速読」という喩えがあるのだが、イメージとしては水泳の講習に行き、ボードをつかんでのバタ足などを教わったものの、体力も足りず息継ぎの技術もなく、「プールの反対側まで泳ぐ」という目標は達成できないままに終わってしまった――というような印象である。
栗田先生によると経験上、編集者やライターなど日頃から文章を生業にしている人間は、音の読書から脱することが難しいとのことだ。
150冊も本を出している方だから、おそらく多くの担当編集者が速読の習得に挑戦し、あらかた挫折してしまったのだろう。初日リタイア組も多かったのではないか。
筆者もご多分に漏れず言語系の人間で、映像系のイメージ力は極端に低い。
イメージ力が豊かな人は、夢もカラーで見るし、目をつぶってもそれまで見ていた光景をありありと思い浮かべることができる。
筆者の場合、夢にはほとんど色がなく、目の前で見ている光景でさえ、目を閉じると色情報のほとんどが欠落し、画素も一気に荒くなってしまう。
「それでよく小説なんか書けるね」と妻からからかわれる。妻の方は夢もカラーなら思い浮かべる光景もカラーなのである。
「光の回路」を使うSRS速読法は、視覚領域の力を利用して言語系の情報処理能力を飛躍的に向上させる能力開発法なので、言語系に偏ってイメージ力が貧困な人間には習得が難しいようだ。
筆者のイメージ力の低さは、中学と大学の二度にわたる受験の影響かもしれない。
栗田先生は過去に多くの受験生を指導しており、受験生には大きく「発展適応」と「萎縮適応」の二つのタイプがあるという。
発展適応する受験生は、試験を自らの能力開発の機会と捉え、受験勉強に努力するだけでなく、受験に直接関係ない分野にも興味を失わず能力開発を続ける。
萎縮適応する受験生は、受験に必要な科目に精力を集中し、それ以外の分野からはなるべく手を引いてしまう。
前者は問題ないが、後者は試験には受かっても、社会人になってから伸びずに苦労するという。
それは人の能力には多数の側面があるのに、萎縮適応するとそのうち複数の側面を犠牲にして萎縮させてしまうことになるからだ。その結果、後の人生でその萎縮させた能力が必要になったときに対応できなくなり、行き詰まってしまう。
その典型が、過去に言語系を操作するだけの勉強をしてきたためにイメージする力を萎縮させてしまった人であり、能力開発法を指導していて一番困るのがこのタイプだという。
筆者なども、まさにそれに該当する人間のように思われる。とすれば、わずか5回の講習で脳内に革命が起こらなかったのも無理はない。
筆者と同様、SRSの講習を受けたけれども、速読は身につかなかったという人は多いようだ。筆者を講習に誘ってくれた友人も同じだった。
自分が泳げるようにならなかったからといって「人間が泳ぐことなど不可能だ」と決めつけるのが間違っているように、自分ができるようにならなかったからといって「速読など不可能だ」ということはできない。
とはいえ、光の回路で読書する脳内革命を実現するのはそう簡単なことではないというのが、講習を受けての筆者の実感である。
●「読む」とはなんぞや
SRSの講習で印象の残ったことの一つに、
「『読む』とはなんぞや」
という先生の話があった。
ちょっと考えると「読む」とは、「本に書かれた情報を文字を通じて摂取する作業」ではないかという気がする。
だが実際、我々が一冊の本を読み終えたとき、本の内容をどれくらい正確に記憶に留めているだろうか。
筆者の父は筆者の何倍かの本を読む読書家だったが、同じ本を2冊買ってくることがよくあった。一度読んだ本をまた買ってしまうのだ。つまり読み終えた本の内容どころか本のタイトルすら、ろくに覚えていなかったのである。
そんな読み方をしていても、読書は父にとってかけがえのない楽しみだった。
筆者の本の読み方も父に近いものがある。
速読の練習をやってみて、「形だけ速く読んでみても、内容が理解できた感じがしないし、覚えてもいない」と文句を言っているわけだが、では「普段ゆっくり読んでいるときは、読み終わった後でちゃんと内容を覚えているのか」と言われれば、全く自信がない。
情報を吸収するためではないとすれば、何のために本を読むのか。
筆者は「読む」とは、文章を通じた書き手と読み手の対話(コミュニケーション)だと考えている。
文章を読むことは、一見すると書き手から読み手への一方通行のように思える。
しかし実際はそうではない。読み手は一つの文章を読むたびに何かしらの感想を心に浮かべている。筆者流に言えば、心の中で作者に対して「つっこみ」を入れている。
本好きが本を読むことは、グルメが料理を食べることに似ている。すばやく料理を食べて短時間で栄養を摂取することができたとしても、「おいしい!」という感想、感動をじっくり味わうことができなければ、グルメは満足できない。
本の読み手にとって重要なのは、文章から得られる情報より、むしろ文章によって引き起こされる自分自身の感想であり、感動なのだ。
たとえば時代を越えて読み継がれる優れた古典は、読み手の心を写す鏡として存在価値を保ち続けている。内容そのものは既知であっても問題ない。大事なのはそれが読み手の心に有用なリアクションを生み出してくれることなのだ。だから人は何度も読んだはずの座右の書を繰り返し手に取る。
世の本好きに速読に消極的な人が多いのも、読書を情報摂取の手段というより、料理のように味わう対象と捉えているためだろう。本好きにとって、本の内容を高速で記憶することができたとしても、それに対する自分の感想を確認する時間が取れないのでは、本を読む意味が半減してしまう。
では速読では、本好きが求める読書の喜びは得られないのだろうか。
「泳ぐことができなかった」筆者にその点を語る資格はないのだが、栗田先生の話を聞く限り、そうではないようだ。
SRSでは「わかる」という感覚を「外から来た情報と自分の内部にファイリングしてあった情報が共鳴すること」と捉え、「本を読むとは、活字を通じて著者と外部共鳴を起こすこと」「感動とは、深層領域を含む心の全体が揺さぶられる状態」と説明している。
これを解釈するなら、読むとは著者の思いに共感したり感動したりすること、つまり自分の心を動かすことが目的である――ということになるだろうか。
本の内容を記憶するだけではなくそれと共鳴し、そこから感動を受けることができて、初めて真の意味で「読んだ」といえるのだし、速読でもそれは十分可能なのだ、ということだろう。
●脳内メモリは拡張できるか
もう一つ印象に残ったのが、「深層意識における作業テーブルの広さ」の話だった。
作業テーブルの広さとは筆者の理解では、PCにおける作業用メモリの容量のようなものだ。
小説を書いていると、自分の脳の作業用メモリ容量の限界を明確に感じることがある。
たとえば長大なストーリーを伏線や謎解きをからめて帰納的な手法で書いていると、途中で考えきれなくなってしまい、筆が全く進まなくなるという現象が起こる。
それは小さなメモリしか積んでいないパソコンに大きすぎるプログラムを流そうとしたときによく似ていて、作業が極端にのろのろとしか進まなくなったり、思考がフリーズして全く進まなくなったりする。普段なら簡単に思いつくようなこともなかなか思い浮かばなくなり、ひどい時には何週間も机の前にぼうっとして座り、一行も書けないという状態になってしまう。
筆者は一度そういう苦しい経験をして、そのとき自分が陥った状態が自分の脳内メモリの容量限界に起因するものだと自覚するようになった。
以後は自らのメモリ容量の限界に達するのを避けるために、ストーリーの全体と細部をまとめて一気に捉えようとする努力をやめ、極力個々の問題にブレークダウンして逐次処理するよう心がけてきた。
自分の脳内の作業用メモリの容量をなんらかの方法で拡張し、物語を多くの視点からチェックし全体の整合性をとりながら一気に造形できれば、執筆の効率は飛躍的に上がり、物語のスケールも複雑かつ壮大なものにできるはずだ。
これはおそらく小説家だけの話でない。たとえばプログラマーなどにも筆者と同様の経験をし、同じ願望を抱いている人が多数いると思う。
人の脳内メモリの量はおそらく各人ごとに、生得的に決まっているものなのだろうと、筆者は考えてきた。
世間では「人の脳は全体の一割しか使われていない」などと主張する向きもあり、あたかも人の知性には無限の可能性があるかのように言われているが、それは根拠のない願望にすぎない。
生物は環境に適応するため必要に応じて脳を発達させてきたのであり、進化論的に見て人間の脳が生活上の必要をはるかに越えるほどの容量を持っているとは考えにくい。必要もないのに長くなってしまったマンモスの牙でもない限り、ハードウェア的には必要ぎりぎりプラスアルファの能力しか備えていないと考えた方が合理的だ。
先に述べたように筆者はイメージ能力が低く、夢を見るときもモノクロだし、目をつぶると目の前の光景から色が消え、画素も荒くなってしまう。
この現象についてもそれまで「作業容量や記憶容量の制限から、脳が必要に迫られて映像の情報量を落としているのだろう」と考えていた。
脳のハードウェア性能が低い場合、映像信号の情報量を落とすことは、生存に関して有利に働くのではないかと考えられる。
PCで処理する場合も画像ファイルはテキストファイル等に比べて容量が大きく、転送するのに時間がかかるし、記録できる量にも限界がある。
生物の脳神経系でも同じ問題が起きているはずだ。
だが生物において視覚情報の伝達速度が遅くなることは、外敵や獲物に対する反応の遅れに直結し、生存の可能性を著しく低めてしまう。
このため人体は、視神経から脳に送られる映像信号の転送・処理速度を実用レベルまで引き上げるために、あえて視覚情報の情報量を圧縮しているのではないか。
つまり人間の脳は生存の必要に迫られて、自らの低レベルなハードウェア的制限に合わせて適宜、情報を削りながら処理しているのだと考えられる。
脳内の作業用メモリが生活の必要に対してぎりぎりの容量しかなく、その容量は遺伝的に決定されて個人の努力では変えられないものだとすれば、人は自己の生存のために、現実の使用状況に応じて処理すべき作業ごとに脳内メモリを割り振ることになる。
結果、映像系の処理を優先させれば言語系の処理能力は犠牲になり、言語系を優先させれば映像系の処理が劣化する。
筆者の場合、成長期の受験勉強や本の多読乱読の結果、意図しないうちに脳内に言語処理優先の体系を作り上げてきたのだ、と想像できる。
要は文系人間ということだ。
以上が「目の前の光景をカラーで想起できない」ことについての筆者の仮説だった。
だが栗田先生によれば、深層意識における作業テーブルを拡大するための方法が存在し、その鍵はイメージ力の向上にあるという。
栗田先生自身は、自分の心の中を映像的に俯瞰することができ、その中を自由に降下していって、イメージが生まれる場所や望みの記憶が保管された場所に到達することができるとのことだ。「人の意識は円錐形のような形をしており、表層意識は狭いが、下に向かうほど広くなっている。底はなく、心の世界の広さは無限大である。これは私が長期間の瞑想を行って確かめたことだ」と説明されていた。
夢枕獏さんのSF小説『サイコダイバー』を地で行くような話である。そんなことができる人が現実にいるとは、まさか思わなかった。
人のイメージ力の上限が遺伝的に決定される脳のハードウェア的な制限から定められたものではなく、栗田先生の言うように本来なら大きく発達する余地があったものを萎縮適応で退化させてしまった結果だとしたら、トレーニングを通じて自分のイメージ力を向上させることは可能だし、それをしてもバーターで言語系の処理能力が低下する心配はないことになる。
栗田先生も「完全に枯れた枝は再生困難だが、萎縮した枝であれば、本人が自覚さえすれば再び伸ばすことは不可能ではない。再生のために必要な期間は一般的に2ヶ月半」と述べている。
これは筆者にとっては、大いに希望が持てる話である。
筆者がSRSを再び習うことはないかもしれないが、今後も希望は捨てずに、自分の能力を高めていくための工夫を続けていこうと思う。
≪ SRS速読法体験記 前編 トレーニングで赤ちゃんの夜泣きを防ぐ ≫