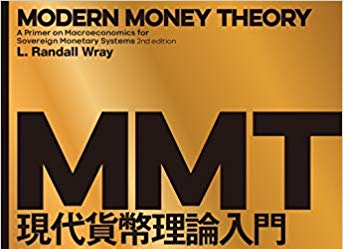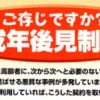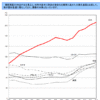目次
●人間の常識的理解に反するMMT
L・ランダル・レイ著『MMT 現代貨幣理論入門』の解釈、その2。
前回は「マクロ会計の恒等式」から導かれる、財政赤字の解消に必要な方策について述べた。
マクロ会計の恒等式自体は、
国内民間収支+国内政府収支+海外収支=0
という、数学的(数学というより算数のレベルだが)にはごく常識的な話である。
ところがそれを敷衍(ふえん)していくと前回の記事で見たように、
「好景気のときほど企業と家計の貯蓄は減る」
「不景気なときほど企業と家計の貯蓄は増える」
「不景気なとき政府は財政赤字に陥るが、それを解消しようと増税すると、財政赤字は減らずに家計はさらに貧しくなる」
という論理的結論に至る。
これは人間の直感的理解とは真逆であるために、多くの人にとって理解しにくい議論となっている。
2019年の消費税増税に見られるような日本政府の財政赤字解消政策は、MMTの理論からすると馬鹿げていて、財政赤字を減らすどころか増やすことにしかならない。
だが実際にそうした政策が実施されているわけなので、日本では政治家はもちろん、財務省の官僚も、政府系のマクロ経済学者も、MMTの基本的な考えを受け入れていないように思われる。
みなさん、天下の秀才と謳われる人たちのはずだが、それぐらいMMT理論は、人間の常識的感覚に反するものだということだろう。
●貨幣とは負債である
今回は「お金とは何か」というテーマに関して、これもまた大変ユニークな、MMT派の解釈を紹介する。
ウィキペディアで「貨幣」の項目を引くと、貨幣とは、
「商品交換の際の媒介物で、価値尺度、流通手段、価値貯蔵の3機能を持つもののこと」
と最初に定義されている。
ところがその2行下に、
「負債の一形式であり、経済において交換手段として受け入れられた特殊な負債のこと。特に現代経済においては、すべての経済主体が信頼する借用書のこと」
という別な定義が書かれている。
後者は多くの学徒にとって耳慣れない内容であり、比較的最近、MMT派の経済学者によって書き加えられたものであろう。
そう、
「貨幣とは(政府の)負債である」
というのが、MMTの解釈なのだ。
貨幣の成り立ちについて、著者のレイは1998年の著書『Understanding Modern Money』でくわしく論じているとして、本書では歴史的考察は省かれている。
あいにく筆者は前著を読んでいないのだが、序文を見る限り、著者の主張は、
「主流派経済学においては、『物々交換社会の中で、価値があると認められた商品が、交換手段として用いられるようになった。それが貨幣に発展していった』と考えている。これが商品貨幣論である。
MMTでは、商品貨幣論は誤りであり、『政府が債務の計算単位としての通貨を定め、モノとしての貨幣を発行し、それを納税に必要なものとすることでその需要を生み出して流通させている』と考える」
ということのようだ。
●貨幣は「麻雀の点棒」だった
古代において、貝殻が貨幣として用いられていたことはよく知られている。
現代人は、現代における通貨のあり方から類推して、
「貝殻1個が米1升、魚10匹というように定められて、米と魚を交換するときに、モノ同士を直接やりとりする代わりに、今のお金と同じように貝殻を受け渡ししていたのだろう」
と考えがちだ。
だが貨幣としての貝殻の使われ方は、今のお金の使われ方とは違っていた。
現代において貝殻に価値がないように、古代においても貝殻に価値を認める者などいなかった。
ではなぜ価値のない貝殻が、貨幣として用いられたのか。
貝殻は実は、モノやサービスが提供された際、それを忘れないためのメモ代わりに使われていたのではないか。
たとえば米の収穫までには、多くの人手が必要になる。収穫された米は、米の栽培を手伝った人に、手伝った労力に応じて分配される必要があるが、誰が何回手伝ったかなど、正確に覚えておくのは難しい。「おれは10回手伝った」「いいや8回しか手伝ってねえ」などと揉めるのを防ぐためにも、何かモノを使って記録しておくほうがよい。
そのための手段が貝殻だった――と考えると、納得できる。「1回手伝ったら貝殻1個」と決めておけば、収穫の後で各人の手持ちの貝殻の個数に応じて、穫れた米を分配してやればよい。
このように貨幣は当初、モノやサービスの交換を仲介していたわけではなく、モノやサービスを提供したことを証拠立てるメモ、いわば借用証書だったと考えられる。
これがMMTの考え方である。
古代の貨幣とは、現代のモノに例えるなら、麻雀の点棒のようなものだった。
点棒は印のついたプラスチックの棒にすぎず、それ自体に価値はない。だがゲームの勝ち負けはそれによって記録されている。点棒を使わずにお互いの細かな点数まで覚えておくのは面倒だし、トラブルのもとだ。点棒とはメモの代わりである。賭け麻雀においては、ゲーム終了後に手持ちの点棒に応じて精算が行われる。ここでは点棒は借用証書として機能する。
●貴金属と結びつけられた貨幣
当人同士が了解してさえいれば、メモの種類は何でもよい。メモ自体に価値は必要ない。だから古代においては、貝殻だけでなくいろいろな種類の貨幣があったはずだ。
日本で本格的に金属貨幣が使われ始めたのは平安時代末期で、使われたのは大陸から輸入された宋銭だった。
それまで日本でも朝廷が、和同開珎にはじまる皇朝十二銭を鋳造したものの定着せず、平安時代末期に租税の単位として用いられていたのは、絹だった。朝廷は宋銭の流通を嫌ったが、日宋貿易を独占する平氏が宋銭の流通を推し、均質で携帯にも便利な宋銭はやがて絹に取って代わり、鎌倉幕府や朝廷の租税の単位も宋銭となった。
つまり中世日本においては、貨幣は国が作るものではなく、輸入されたものだった。
植民地時代のアメリカでも、主に流通していた貨幣はイギリス政府発行のものではなく、スペイン政府が発行し南米で流通していたスペインドルだったとされる。
貨幣の本質は、貸し借りを記録するためのメモなのだから、政府が作ろうが外国から輸入しようが、貝殻だろうが金属だろうが、便利でありさえすれば何でもよいわけである。
その後、戦国時代に金や銀の採掘・精錬技術が大陸から日本に伝わり、戦国大名が領内の鉱山を開発し、貴金属貨幣が発行されるようになった。この場合の貴金属貨幣は、地金そのものに価値があり、貨幣としてだけでなく輸出品として用いられた。
貨幣が貴金属で作られるようになったことで、貨幣の価値は貴金属の含有量によって決まるようになった。その慣習は江戸時代になっても続いた。金銀本位制の成立である。この時代、西欧諸国でも貨幣の価値は貴金属と結びつけられて考えられており、このマインドセットが後の金本位制のベースとなった。
金本位制とは、政府が発行する紙幣を定量の金(gold)と交換する制度である。金の産出量は少ないため、これによって通貨の価値が保証される(=インフレにならない)と考えられた。
しかし貨幣の需要は経済の拡大に伴って増加していく。モノとサービスの交換が盛んになれば、それだけ借用証書の需要も増えるのが当然である。金本位制では産出量が少ない貴金属と通貨の交換を保証することで貨幣の供給量が制限されるため、経済の発達に応じた通貨の発行増加が困難になり、経済に悪影響が生じる。
金本位制は第二次大戦後まで断続的に続くが、1972年に米ドルが金との交換に応じなくなったことを最後に終焉する。
主流派経済学では、今も「通貨には価値が必要であり、貴金属との交換の保証はそのための手段である。金本位制こそ貨幣の原点であり、本来の姿である」という考え方が存在する。
一方、「通貨とは借用証書である」とするMMTは、「借用証書それ自体に価値など必要ない」と考え、貴金属との関係を断った現在の通貨のあり方を肯定する。
麻雀の点棒が金や銀でできている必要はどこにもない。そんな馬鹿なことをするために点棒が不足すれば、ゲームの進行に差し支えてしまうということだ。
●課税の目的は「財政支出を賄うこと」ではない
MMTにおいては、「貨幣の価値を保証するのは、課税である」と考えられている。
主権国家が国民と企業に納税の義務を課し、その単位を自国通貨とすることで、国民と企業には自国通貨を保持するニーズが生じる。MMTは、それが通貨の価値を保証していると説く。
さらにMMTは、「課税とはそれによって貨幣の価値を保つための制度であり、『課税は財政支出を賄うための手段である』という考えは誤りである」とする。
なぜそう言えるのか。
「なぜなら政府は財政支出のために、納税を必要としないからだ」
とMMTは説く。
一般の家計では、支出のためには収入を必要とする。これは企業も同じだ。人々は日常生活や仕事の上で「収入がなければ支出ができない」ことを骨身に滲みて思い知らされている。このため、政府についても「税収がなければ財政支出もできない」と思い込みやすい。
だがこれは根本的な誤りだと、MMTは指摘する。
政府は家庭とは違う。企業とも違う。
政府は自ら通貨を発行・創造できるのだ。
政府は支出のために収入を必要としない。支出したい金額を創造するだけでよい。
主流派経済学においては、貨幣を発行する中央銀行は「政府とは別な組織である」ということになっている。MMTはこれを「建前にすぎない」と喝破(かっぱ)し、中央銀行と政府を「一体のもの」とみなす。
通貨主権を持つ国家において、貨幣の創造は容易である。よく「輪転機を回しさえすればよい」と揶揄(やゆ)されるが、現代においては「キーボードを叩くだけ」でよい。政府が中央銀行に指示し、中央銀行のサーバー内にある政府口座にキーボードで数字を入力させれば、それで政府の新たな預金が誕生する。事情は日本でもアメリカでも、イギリスでも中国でも、通貨主権を持つ国(自国通貨を発行している国、と言い換えてもよい)ではみな同じだ。
現在、国内外の民間市場に存在する「ドル」資産はもとを正せば全てアメリカ政府が発行したものであり、「円」資産は、全て日本政府が発行したものである。
政府は通貨を発行することによって、それに相当するモノやサービスを購入している。これが財政支出である。政府にモノやサービスを提供することによって通貨を受け取った人々は、それを使って今度は自分がモノやサービスを購入し、政府に納税する。
ドルを使って納税するためには、納税より前にドルが市場になくてはならない。
円を使って納税するためには、納税より前に円が市場になくてはならない。
つまり通貨は納税より先に発行されている。通貨が発行されるということは財政支出があったということなので、納税よりも財政支出が先にあったことになる。
「『納税によって財政支出が賄われる』という考え方は、この1点だけを見ても明らかに間違っている」
とMMTは指摘する。
「政府は通貨という借用証書を発行し、納税を通じてそれを回収している」というのが、MMT流の理解なのである。
●国債と貨幣は同じもの
MMTではまた、「貨幣と国債は本質的に同じものである」と考える。
一般に、「国債とは政府の借金であり、貨幣とは中央銀行が提供する価値交換のためのインフラである」と理解されている。
だがMMTでは上述のように、貨幣とは負債であり、政府と中央銀行は一体のものとみなしている。
国債と貨幣の違いは、
・国債には利子がつくが、貨幣にはつかない
・貨幣はあらゆる市場で交換に用いられているが、国債は金融市場でしか交換に用いられない
・国債には償還期限がある
ことである。
国債が一定期間後に「償還される」とは、国債が政府の手で貨幣に置き変えられるということである。これは、
「国債は一定期間後に貨幣に変化する」
と言っているのに等しい。
実際には市場に出回った国債は、買いオペレーションによって中央銀行に購入された時点で事実上、貨幣に変化する。
買いオペが行われると、売り手には国債と同価値の貨幣が引き渡される。
政府が発行した国債は、この時点で中央銀行が発行する貨幣に変わったのである。
国債につけられた利子は以後、中央銀行の収入となるが、中央銀行の収入は政府に上納されている。つまり中央銀行に購入された国債の利子は、消滅したに等しい。
その後、中央銀行が保管する国債に償還期限が来ると、政府は借換債を発行してその国債の償還を先延ばしにする。この作業は「政府財政が黒字化して発行済の国債の一部が償還される」という、ごくたまにしか起こらない事態が発生しないかぎり繰り返され、中央銀行に保管された国債は、そのまま死蔵され続ける。
利子もなければ移動もしない。存在しないのと同じだ。残るのは、民間市場に放出された貨幣のみである。
このように見ていくと、「政府が国債を発行する」とは、「中央銀行が通貨を発行する」ことと、実質的に等しい。
これがMMTの主張である。
●財政は赤字でなければならない
「国債と通貨は実質的に同じものである」
というMMTの視点からすると、
「国債の発行は通貨の発行に等しい」
ということになる。すると、
「政府の国債発行量は、市場における通貨のニーズに応じて決められるべきである」
ということになる。
つまり、
市場で通貨が過剰であるならば、政府は財政を黒字化して新規国債の発行を止め、税収により既発の国債を償還することで、市場の通貨量を削減する必要がある。
逆に市場で通貨が不足しているならば、政府はより多くの財政赤字を計上して赤字国債を追加発行し、市場により多くの通貨を供給する必要がある。
ということだ。
もし全ての財政支出が納税によって賄われるものであれば、世の中には納税分の通貨しか存在しないことになる。それでは民間経済は機能しない。世の中は納税に必要な額をはるかに越える通貨を必要としている。それは納税額を越える政府の財政支出、言い換えれば財政赤字によって供給されている。
(実際には、市場の大部分の通貨は金融機関による融資と、その際に行われる信用創造によって供給されている。
通貨は、融資されることで増える。
預金者が銀行に預けたお金は、銀行の融資によって借り手の手に渡る。借り手が100万円借りれば、借り手の口座に100万円が振り込まれる。この100万円は建前上、預金者が預けたお金の一部ということになっている。
しかしこのとき、預金者の口座のお金は別に100万円減ったりはしない。そんなことになったら大騒ぎだ。
預金者の口座の金額はもとのまま、借り手の口座の金額だけが100万円増える。
つまり、世の中のお金が100万円増えたわけだ。
こう言うと必ず「嘘だ! そんなことが起きるはずがない」という人が出てくるのだが、別に嘘ではない。お金は融資されると、本当に増えるのである。これを「銀行の信用創造機能」と言っている。「信用」などと意味不明の言葉を使っているが、要は「銀行のお金創造機能」という意味である。
景気がよくなると銀行の貸し出しは増え、世の中のお金はどんどん増えて、ますます景気がよくなる。あちこちで札束が飛び交う世の中になる。
バブルである。
逆に景気が怪しくなって銀行が「貸し剥がし」を始めると、世の中のお金は一気に減ってしまう。こうなるとあちこちでお金が足りなくなって、大変な騒ぎになる。
バブルの崩壊である。
このように世の中の通貨の量は民間金融機関の融資によって大きく違ってしまうのだが、その貸し出しのもととなるのはやはり、政府が創造した貨幣である。「世の中の全てのお金はもとは政府の財政支出から生まれている」というのは、そういう意味である)
経済成長によって民間経済の規模が大きくなれば、その分だけ必要とされる通貨の量も増える。銀行が貸し出すにも、預金が必要だ。つまり政府は経済成長に見合うだけの通貨を、新たに民間に供給しなくてはならない。そのためには財政支出を納税分以上に拡大する必要がある。
つまり、財政を赤字にしなければならない。
「経済が成長している限り、政府は財政赤字を続けなくてはならない」
というのが、MMTの主張である。
●財政政策には採用不能
ここまでのMMTの主張は、従来までの経済理論とは全く異なる視点から展開され、その論理は一貫しており、かつ明快である。一読して、目を開かれる思いがする。
MMTが主権国家の財政赤字に対してきわめて許容的であることは、見てきた通りだ。
ただ問題はその先にある。
市場のニーズに応じた一定量の財政赤字が必要であるとして、ではそれはどの程度が適切なのか。市場の通貨ニーズは、どのような指標によって測られるべきなのか。
主流派経済学で一般的な貨幣数量説においては、「物価の水準は社会に流通する貨幣の総量とその流通速度によって決定される」と考える。
これに従うならば、通貨ニーズを計測するための指標は物価上昇率ということになる。インフレであれば通貨が過剰であり、デフレであれば通貨が不足であるということだ。物価上昇率に関し、主流派経済学においては、経済の健全な発達を促す上では0よりもやや上、2%程度が適当であると考えられている。
ただし貨幣数量説においては、過度な財政赤字は制御不能なインフレを引き起こすと考えられるので、物価上昇率のコントロールは制御が容易な金融政策に任せ、支出硬直性の高い財政は物価に対しできる限り中立的であるべきだということになっている。この場合の中立的とは、市場の通貨量を過剰にしないため、累積財政赤字を増やさないことを意味する。
だがMMTは貨幣数量説を支持しない。
MMTにおいて貨幣は交換を記録する借用証書にすぎず、それ自体は商品として価値を持たないと考えている。借用証書にすぎないはずの貨幣の供給量がダイレクトに物価に影響を及ぼすとする貨幣数量説は、MMTの概念とは整合しない。
「点棒が増えようが減ろうが、ゲームのレートとは関係ない」
ということだ。
一方、主流派経済学の命題の一つである貨幣中立説では、「名目貨幣量の変化は物価には影響しても、モノやサービス同士の実質的な交換比率には何の影響も及ぼさない」と説く。こちらはMMTとも整合する。MMTは実際、財政赤字に対してと同様、インフレに対してもきわめて許容的であって、「年率数十%程度のインフレが、経済にさほど大きな問題をもたらすことはない」という姿勢である。
貨幣が借用証書にすぎないとするなら、その供給量=財政赤字の幅は、物価に何の影響も与えないのだろうか。もしMMTがそう主張するとしたら、それは経済史に刻まれた事実に反している。
第一次世界大戦後のドイツで、第二次大戦後の日本で、あるいは財政破綻した南米やアフリカの一部の国で、過剰な財政赤字が破壊的なハイパーインフレをもたらすことは繰り返し観察されている。
一方で物価上昇率が財政赤字の規模にリニアに反応しないことは、近年の日本の例を見ても明らかである。
財政赤字とインフレの関係について、MMTの主張は明確ではない。
MMT論者たちは、政府が膨大な財政赤字を積み重ね、市場に大量の貨幣を供給しているにも関わらず一向にデフレから脱出できないでいるという、貨幣数量説に疑念を抱かせるような日本経済の現状に対して、自説の傍証として歓迎している。しかしその状況を説明できるような、貨幣の量と物価についての独自の法則を開陳(かいちん)することはしていない。「過剰な財政赤字はインフレをもたらす恐れがある」というだけだ。適切な物価上昇率がどの程度であり、それを維持するための財政赤字の規模がどの程度であり、市場の通貨ニーズをどのように計測すればいいのかという点について、MMTから明確な主張は聞かれない。
明らかにMMTは、貨幣数量説を否定しつつも、それに代わるような貨幣供給量と物価の関係についての法則を発見したわけではないのだ。
代わりに主張されているのは、「完全雇用が達成されるレベルまで、新規の国債発行(=財政赤字)を伴う財政支出の拡大は許容されるべきだ」という議論である。それを聞く限り、MMTでは財政赤字の規定要因として、インフレ率よりも雇用統計のほうが重要であると言っているように見える。
MTTのこの主張は、筆者の目から見ても根拠不明で、社会主義思想に影響されて偏向しているようにも思われ、MMTが主流派から受け入れられない大きな要因となっている。
学説としてのMMTの課題は、貨幣供給量と物価の関係についての明確な関係性を見い出せず、財政赤字の幅を規定する指標が欠如していることにある。今の状態のままでは政策担当者が財政政策の判断基準としてMMTを採用することは不可能だ。
こうした大きな弱点を抱えながらも、
「お金とは借用証書である。国債も通貨も同じものである」
というMMTの主張は斬新で、納得性がある。
今後、各国政府における財政についての理解は、MMTの主張を踏み台として大きく変わっていくことになるだろう。