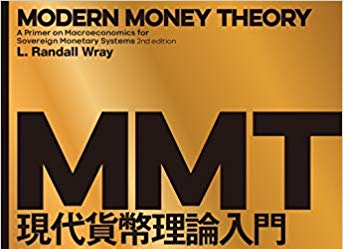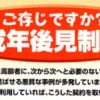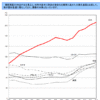目次
●この投稿のきっかけ
先年、「一般社団法人 後見の杜」を主催する宮内康二代表の知己を得て、日本の成年後見制度の現状についてくわしくお話をうかがう機会があった。
宮内代表は早稲田大学卒業後、米国南カリフォルニア大学に留学。ケアマネジメントや高齢者の社会参加、後見制度などを研究対象とする「老人学(gerontology)」を学んだ。帰国後、政府の委託を受けて後見制度についての研究を行い、東京大学医学系研究科で教鞭を執るなどした後、「後見の杜」を創設。著書に『成年後見制度の闇』(共著 飛鳥新社 2018年)等がある。
この問題についての日本を代表する専門家である宮内代表から筆者が教えられたのは、予想を越えて深刻な日本の成年後見制度の実態だった。
以下はその内容である。
なお本エントリーは宮内代表より掲載の許可をいただいているが、代表による事前の内容チェックは一切なく、文中の誤記、事実関係の間違い等はすべて久保田の責による。
●成年後見制度とは
「成年後見人」と言われても、「なんのこと?」という人も多いだろう。
「成年後見制度」とは、認知症などにより資産の管理能力を失ってしまった人に対して、本人の代わりに資産管理を行う「後見人」を置く仕組みのこと。
高齢者の他、両親を亡くした障害者も対象となっており、家族や市町村からの申し立てを受けて、各地の家庭裁判所が選任している。
高齢者がボケてきて、自分では預金も下ろせなくなってくると、妻や子供が生活に必要な費用を立て替えなければならなくなる。
「おじいちゃんのために使うお金なんだから、おじいちゃんの口座から引き出そう」と思って銀行の窓口で相談すると、「本人以外の預金引き出しは認められません」と断られ、「成年後見人をつけてください」と言われることになる。
こうした銀行の窓口でのやり取りを通じて、「成年後見人」という言葉を初めて知る人が多い。
「成年後見人ってなんですか。どこに相談したらいいでしょう」
と訊いて紹介されるのが、「地域包括支援センター」または「社会福祉協議会」である。
一人暮らしの親が悪徳商法の標的となり、気がついた家族が警察に相談に行った――といった場合も、やはりこれらの施設を紹介される。
●後見申立代行の法外な手数料
地域包括支援センターは、地域の高齢者をサポートするための拠点として位置づけられている行政施設で、人口3万人につき1つ設置されている。保健師や社会福祉士、ケアマネジャーが常駐し、介護その他の相談を受け付けている。
一方の社会福祉協議会は社会福祉法に基き、社会福祉活動を推進することを目的とした非営利の民間組織で、各自治体に1つある。
こうした施設はどこも地域の弁護士会や司法書士会と密につながっている。そのため「家族が認知症で」といった相談をすると、多くの場合「成年後見人をつけるしかないですね」「手続きのやり方はわかりますか。司法書士の先生か弁護士の先生に頼むといいですよ」とアドバイスされることになる。
相談を受けた職員が弁護士や司法書士と親しくしていて、名刺や電話番号を渡されることもある。
まずここが要注意だ。
成年後見人の申し立ては、特に難しいものではない。
6ページ程度の書類に、「申し立ての事情」「本人の状況」などの項目にチェックマークを入れ、親族の住所氏名を書いて、家庭裁判所の受付に提出するだけ。
書類は家庭裁判所に行けばもらえ、家庭裁判所のホームページから書式をダウンロードすることもできる。誰でも書ける程度の内容で、自分で書いて申し立てを行う分には一円もかからない。
ところが地域包括支援センターや社会福祉協議会で紹介された弁護士などに申し立てを頼むと、驚くほど高額の「申立書類作成手数料」を要求されることがある。
その額はときに数十万円から100万円にも上る。
自分で簡単に書ける書類の作成を代行するだけで数十万円とは、申請者の無知を利用した詐欺的な請求といってよい。実際には弁護士本人はそんな簡単な事務作業は行なわず、事務員にやらせている。
申し立てをする親族は「費用はご本人からいただきます」と言われれば、「どうやっていいかわからないし、こっちの懐は痛まないからいいか」と考え、「じゃあお願いします」と頼んでしまう。
「後見の杜」では、この申立代行業務だけで法曹界にとって年間数十億円の収入源となっていると推定している。
成年後見人の認定で申立書以外に必要なのは、認知症であることを確認するための医師の診断書である。
診断書が出ていても、家庭裁判所が「診断書だけでは認知障害の程度がはっきりしない」と判断した場合、鑑定医に診断を命ずる場合がある。これには10万円程度かかり、その費用は申し立てる側が負担させられる。家庭裁判所では料金を申立人に予納させてから、指定した精神科医に鑑定を指示する。
仮に弁護士に申立書類作成料として70万円支払い、鑑定に10万円かかったとすると、制度の利用開始前に80万円かかってしまう計算になる。しかし成年後見全体にかかる総費用からみれば、それくらいはごく一部にすぎない。
●家族は自分で申し立てても後見人になれない
日本では年間3万から4万件の新たな成年後見が開始されており、全国におよそ20万人の成年後見人がいる。
かつては後見人の9割が妻や子供などによる「親族後見人」だった。しかしここ数年は弁護士・司法書士などによる「専門職後見人」が急増しており、2012年には全体の5割を超え、2016年以降は7割に達している。
専門職の内訳としては弁護士と司法書士で半数近くを占め、それ以外に社会福祉士、行政書士、精神保健福祉士などがある。
なぜこれほど急に専門職後見人の割合が高まったのか。
成年後見の申し立てでは、申立書の中で成年後見人の候補者を指名する。家族が申し立てを行う場合、多くは本人の妻や子供が候補者となる。
申立書の「成年後見人等候補者」の欄には「申立人と同じ」という項目がある。申立人が自分の名前を書くことが多いためだ。そこにチェックマークをつければ、申立人が成年後見人の候補者となる。
自分で申立書を書いてこの欄にチェックを入れた場合はもちろん、弁護士や司法書士に手続きを依頼した場合であっても、「私が後見人になります」と言っていたなら、申し立てた家族としては、「後見人には当然、自分が選任されるだろう」と思う。
ところが実際はそうではない。
多くの家族は申し立てから1月ほどして家庭裁判所から届いた書類を見て、見も知らぬ弁護士や司法書士が後見人になっていることを知り、「なんだこれは」と仰天することになる。
現在の後見制度が発足した2000年からしばらくの間は、申立書に候補として挙げられた人がそのまま後見人に指名されることが普通だった。
ところがここ数年は、成年後見を申し立てた当人が後見人に選ばれず、縁もゆかりもない弁護士や司法書士が家族の意向を無視して後見人に選任されることが当たり前になっている。
たとえ申し立てた本人が行政書士など、専門職後見人にふさわしいと一般に見なされている資格を持っていたとしても、一方的に棄却されてしまう。
申し立てた家族が「なぜ私ではだめなのか」と裁判所に訊いても、説明はない。
過去数年で専門職後見人の割合が飛躍的に高くなった原因は実は、成年後見人の選任権を持つ家庭裁判所が親族を排除し、専門職後見人を優先的に選任していることにある。
家庭裁判所によってはわざわざホームページ上で「成年後見人は原則、親族は選任しない」と明言しているところもある。
なぜなのか。
その理由は以下で説明していきたい。
家族にとって想定外の出来事は、申し立てをした自分が後見人に選任されないということだけではない。
「一度申立書を出したら最後、後から取り下げることは不可能」という事実もその一つだ。
「見ず知らずの弁護士を後見人にされるぐらいだったら、後見人などいらない」と考えて申し立てを取り下げようとしても、家庭裁判所はそれを認めない。一方的に後見人を押し付けられてしまう。
●業界団体が牛耳る後見人選任の仕組み
家庭裁判所によって親族後見人が退けられ、専門職後見人が優先的に選任されている理由は、仕事がない弁護士、司法書士に報酬を与えるためだ。これは後見制度の関係者には周知の事実である。
成年後見人の選任に深く関わっているのが、弁護士や司法書士の業界団体である。
実は弁護士や司法書士といえども、単に資格を持っているというだけで後見人に選任されることはない。
弁護士であれば各地の弁護士会が後見業務についての有料の研修を開催し、それに参加した弁護士だけをリスト化し、後見人候補者として各地の家庭裁判所に提出している。
司法書士なら司法書士連合会の「成年後見センター・リーガルサポート」、社会福祉士なら日本社会福祉士会の「権利擁護センター『ぱあとなあ』」、精神保健福祉士なら日本精神保健福祉士協会の成年後見人ネットワーク「クローバー」、行政書士なら「コスモス成年後見サポートセンター」が、同じことをやっている。
それぞれ士業の資格を持っていても、これらの業界団体に入会して年会費を納め、研修を受けなければ、各地の家庭裁判所に提出される候補者名簿に名前を載せてもらうことはできない。
これらの団体は自団体の会員を優先して後見人に選任するよう、家庭裁判所に陳情を重ねている。万が一家庭裁判所がそれらの団体に入会していない同業者を後見人に選任したりすれば、強く抗議する。
こうした現状は、後見制度がそれぞれの職業団体にとって重要な利権となっていることを端的に示している。
そのようなわけで、たとえ申立人が自分の知人の弁護士を後見人候補として申立書に記入したとしても、それが認められることはまずない。「家族である申立人が推薦する弁護士は、家族の一部と癒着している恐れがある」といった理屈をつけて、その弁護士は棄却され、代わりに各団体が推薦する候補者リストの中から、家庭裁判所が順送りで後見人を選任することになる。該当する専門職が少ない地方部では、県を越えて弁護士や司法書士がやってくることもある。
ある女性が認知症の親の後見人になろうと考え、家庭裁判所に申し立てたところ、自分ではなく、手続きを頼んだ司法書士が後見人に選任された、というケースがある。
申立人が「あなたは、私が後見人になれると言いましたよね?」と司法書士を問い詰めたところ、「家庭裁判所が決めたことなのでしかたない」と言い訳された。
ところが司法書士が提出した申立書の写しを取り寄せてみると、申立人である彼女の名前で、「私は遠くに住んでいるので、後見人には地元の司法書士○○を希望する」という勝手な付記がつけられていた。
このように家庭裁判所と弁護士・司法書士ら法曹関係者は一体となって、認知症の高齢者の家族に成年後見人の選任を申し立てるよう後押しし、申立書を出させておいて、家族の希望は無視して業界団体推薦の後見人を押しつけているのだ。
●被後見人の資産額に応じて振り分けられる専門職後見人
家庭裁判所では、被後見人の資産額により選任する専門職を分ける。
家庭裁判所が決める後見人の基本報酬は、被後見人の金融資産額に応じて高くなる。
一般に管理財産額が1000万円以下なら、月額2万円。
管理財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合は同3~4万円。
5000万円を超える場合は同5~6万円とされているが、上限はなく、年間数百万円というケースもある。
家庭裁判所では報酬が月額5万円を越えるような高額案件については弁護士に優先して振り分け、3~4万円となるケースは司法書士に、それ以下は社会福祉士などに回している。
被後見人がまったくの無資産で生活保護を受けているような場合、専門職後見人の多くは選任を忌避する。生活保護受給者の場合は報酬額が月額100円といった極端な低額となるケースが多く、商売にならないからだ。
宮内代表は「親族でも専門職でもない、一般市民や民営企業による『市民後見人』の育成が必要」と考え、その実現のために活動してきた。その活動に対しては、専門職後見人の主体である弁護士会や司法書士会から様々な圧力が掛けられてきたという。
一般企業による後見制度への参入も、法律的には2000年から可能になっている。
だが企業側がどれほど体制を整えても、弁護士、司法書士の業界団体と組んだ家庭裁判所が参入を認めない。
まともな報酬が見込めそうな被後見人についてはすべて弁護士、司法書士らの業界団体に割り振り、たとえ新規参入企業の社員が認知症の高齢者と仲良くなり、本人の了解をとって後見の申し立てを行った場合であっても、決して選任しない。
一般的な額の報酬が見込めず、他に後見人の引き受け手がいない無資産者や生活保護受給者のみを企業に押し付ける。
司法関係者以外による成年後見ビジネスへの参入に対しては、こうした露骨な業務妨害が当然のように行われている。
(「成年後見の申し立ては、慎重の上にも慎重に(中編)」に続く)
成年後見の申し立ては、慎重の上にも慎重に(中編) ≫