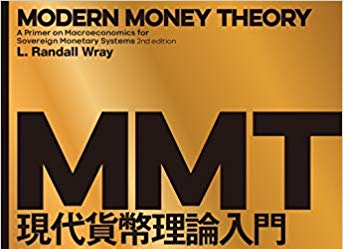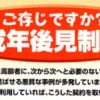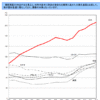目次
●価格が高騰すると広がる食糧危機説
最初にお断りしておくと、本エントリーは筆者が数年前に東京大学大学院の川島博之准教授(当時)に伺った「食糧危機の心配はない」という話の紹介である。
筆者は京都で開かれた研究会に呼んでいただくなど大変お世話になった身なので、文中では「川島先生」と表記させていただく。
以下は取材した内容に、筆者がネット上で確認した最近のデータを一部書き加えたものである。数値や事実関係の誤認等は全て筆者の責に帰す。
川島先生は最近はむしろ中国経済の分析で知られているが、もともとはデータに基づく食糧問題の専門家として、民主党政権の行政刷新会議ワーキンググループのメンバー等も務められた方である。
『世界の食料生産とバイオマスエネルギー―2050年の展望』(東京大学出版会) 『食糧危機をあおってはいけない』(文藝春秋) 『「作りすぎ」が日本の農業をダメにする』(日本経済新聞社)等、この分野で多くの著作がある。

2007~2008年、2011~2012年など、食糧価格の高騰とともにメディアを賑わすのが、
「世界の食糧は不足しつつあり、人類は近い将来、深刻な飢えに直面する」
と主張する「世界食糧危機説」である。
日本では伝統的に「食糧が輸入できなくなり、全ての日本人は存亡の危機に立たされる」という言説が人気だ。
やはり人間の生存本能に訴えるからだろう。日本では長らく第二次大戦後の食糧難の記憶が鮮明で、また農業の保護と食糧自給率の向上を訴える農林水産省の立場からも食糧危機説は都合がよかった。
しかし川島先生は専門であるシステム分析の立場から、「データで検証するかぎり、食糧危機など来ない」と真っ向から危機説を否定している。
食糧危機論者は、
「国連は現在の世界人口76億人が、2050年には98億人に達し、その先もさらに増えると推計している。その一方で世界の食糧生産力はもはや限界に来ている」
と訴える。いわく、
「20世紀後半の耕地の生産性拡大をもたらした機械化、多収量の新品種開発、化学肥料や農薬の投入といった農業技術は既に出尽くし、今や農地に生産性向上の余地はほとんどない」
「アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、アルゼンチンなど、世界の主要穀物輸出国の耕地面積も限界に達している。世界の穀物の作付面積は1981年の7億3000万ヘクタールをピークとして減少に転じ、2007年には6億5000万ヘクタールまで縮小してしまった。原因は工業化と都市化による農地の工業用地、住宅地への転用と、表土の流出、砂漠化、灌漑用水の枯渇等による農地の荒廃である」
「人口増加に伴う家畜数の増加と過放牧により、アフリカ、中近東、中央アジア、中国、モンゴルなどで草地の砂漠化が進行している。乾燥地における1990年代の土壌浸食は世界全体で、穀物作付面積を大きく上回る9億ヘクタールにも達した」
「未開地の残るブラジルでも、これ以上の耕地面積の拡大は環境破壊をもたらす。熱帯雨林の貴重な動植物の多くが絶滅するだけでなく、森林に守られていた土壌が熱帯の強い陽光にさらされることで流出し、大規模な土壌侵蝕が始まる。アマゾンの熱帯雨林の保水効果が失われれば、降水量が減ってブラジル農業に壊滅的な打撃を与えるだろう」
等々。
こうした主張はどこまで事実なのだろうか。
●20世紀の人口爆発と食糧増産
20世紀、中でもその後半、世界人口は爆発的に増加した。
1900年におよそ16億人だった世界人口は1950年には25億人と5割以上も増加し、2000年には61億人と、そこからさらに2倍以上に増えた。100年間で3.8倍であり、これは地球人類史上かつてない人口爆発である。
しかしその間、世界の食糧事情はむしろ好転している。人々は主食である穀物に加え、肉、魚、野菜、果物など、それ以前の時代には考えられなかったほど潤沢で多彩な食材と料理を楽しめるようになった。
どうしてこのような奇跡が起きたのか。
それは世界の食糧生産量が人口の伸びを上回って増加したためであり、食糧生産量が増えたのは、世界の耕地の面積あたりの収穫量(単収)が飛躍的に高まった結果である。そして単収が上がったのは化学肥料、とりわけ窒素肥料の普及によるものである。
植物が必要とする栄養素のうち窒素、リン酸、カリウムを三大栄養素と呼ぶ。その中でも農作物の収量の上限を決めていたのが土壌中の窒素分である。
1909年、ドイツの化学者F・ハーバーが空気中の窒素からアンモニアを合成することに成功、BASF社のK・ボッシュがハーバーの方法を発展させた「ハーバー・ボッシュ法」を開発し、第一次世界大戦直前の1913年、ドイツでアンモニアの大量生産が始まった。
生産されたアンモニアは当初、大戦に向けた火薬の生産に利用されたが、戦後は窒素肥料の生産に転用され、ハーバー・ボッシュ法で生産された窒素肥料は第二次大戦後に世界に普及していく。
その増産効果は絶大だった。
たとえば小麦は過去数千年の間、1ヘクタールあたりの収量は1トン程度だった。ところが20世紀の後半、窒素肥料が投入されるようになると収量が一気に増加し、西ヨーロッパの一部では1ヘクタールあたり8トンを越えるまでになった。
ヨーロッパでは第二次世界大戦後、人口が5億人から7億人へと約4割増加している。しかし農地面積あたりの生産量が5倍以上に増えたことで、人口一人あたりでは戦前の3倍を超える小麦が収穫されるようになった。
ヨーロッパは戦前には小麦が足りずアルゼンチンなどから輸入していたのだが、戦後は逆に余った小麦を域外に輸出するようになる。それでもまだ余ってしまうため、これまで人が食べていた小麦を家畜にも与えるようになった。結果、食肉の生産量も域内需要を越えて大きく増加、こちらも輸出するようになった。
人類が家畜の肉を存分に食べられるようになったのは、化学肥料のおかげなのだ。
米はもともと小麦より単収が大きいが、戦前の日本での米の1ヘクタールあたりの収量は3トン前後だった。
日本では明治維新のときに3300万人程度だった人口が終戦時に7200万人と2倍以上となるなど、19世紀から20世紀にかけて人口が急速に増加した。このため国内生産だけでは食糧需要を満たせなくなり、大正から昭和前期にかけては不足分を中国大陸から輸入していた。
第二次大戦後、日本の人口はさらに増加し、1967年には1億人を突破する。明治維新からの80年で3倍以上に増えたのだ。
しかしこれほどの人口急増にもかかわらず、日本では1967年以降は逆に米が余るようになった。
化学肥料の普及により、農地の単収が2倍以上に高まったためだ。
米の生産が過剰になったため、1970年からは減反政策を始めている。
国連食糧農業機関(FAO)は2011年の報告書「THE STATE OF THE WORLD’S LAND AND WATER RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE」において、
「世界の耕地面積は1961年の13.7億ヘクタールから2009年の15.3億ヘクタールまで、50年間で12%しか増加しなかった。しかし投入資材施用量の増加、農業の機械化と灌漑が農地の生産力を急速に向上させ、世界の農業生産は過去50年間で2.5~3倍に増加した」
と述べている。
農業機械導入による労働生産性の向上と、化学肥料・農薬の投入、作物の品種改良、灌漑による土地生産性(単収)の増加により、人類は100年間で3.8倍という人類史上未曾有の人口爆発と、一人ひとりの栄養状態の改善を両立させることに成功したのである。
●農業大国の食糧生産余力
化学肥料の投入量と農地の単収は比例しており、投入量の大きい地域ほど単収も高い。
だが1ヘクタールあたりの窒素肥料の投入量が100キロを超えているのは、2009年時点でも西ヨーロッパ、北ヨーロッパ、北米、東アジアしかない。
これらの地域では化学肥料投入による単収の増加はほぼ限界に達している。
一方、オセアニア、南米、東南アジア、中央アジア、アフリカの大部分では窒素肥料の投入量は1ヘクタールあたり60キロ以下に留まっており、単収も低い。
これらの地域では農地の生産性向上にコストをかけない、粗放的な農業が中心となっており、化学肥料の追加投入により耕地面積あたりの収量を現在の数倍に増やす余地を残している。
「農地に耕作と灌漑を施し、多収量品種を植えて化学肥料と農薬を大量投入し、土地生産性を最大化する」
という日本で一般的な集約型の農業は、オーストラリアやアルゼンチン、ブラジルといった世界の農業大国では行われていない。
理由はコスト的に見合わないからだ。
これらの国では農地が広大で人が少ない。少ない人手でより広い土地を農地化するため、栽培にはできるだけ手間をかけない。
オーストラリアの小麦の種まきは、種もみを積んだ小型飛行機で農地の上空に飛び、上から蒔いて終わりである。
収穫は穀物が実ってきた時期を見計らい、大型のコンバインで一区画ずつ刈り取っていく。
肥料は撒かず、耕作もほとんどしない。肥料はコストがかかるし、耕運機で農地を耕すのにも人と金がいるからだ。
もちろん灌漑もしない。灌漑には莫大な投資と管理費用が必要だ。米と違い、小麦やトウモロコシはさほど水を必要としない。
1ヘクタールあたりの収量は1トン程度であっても、農地が広いので収穫量は膨大だ。自然任せの天水農法なので降水量による収穫量の変動は大きくなるが、施肥や耕作を行って単位面積あたりの収量を上げていくより、余計な手間や費用を投じずにより広い土地に作付したほうが利益率は高くなる。
もし世界的に穀物の需要が増して市場価格が上昇すれば、現在は粗放的な農業を行っているこれらの農業大国でも農地に化学肥料が投入されるようになり、一気に単収が上がるだろう。
逆に言えば世界の農業大国はどこも、それだけ生産余力が大きいということだ。
●自給率を高める中国とインド
人口に対し農地面積が不足して食糧自給率が低い国では、経済成長とともに化学肥料の投入量が増える。これは日本だけでなく世界的な現象である。
たとえば世界1位の14億の人口を持つ中国がそうだ。
レスター・ブラウン著『誰が中国を養うのか?』に代表されるように、1990年代に流布した食糧危機説では、「中国は2000年代には世界最大の穀物輸入国になる」と予想されていた。だが実際は2000年代に入ってから中国は逆に穀物自給率を上げている。
農水省のレポート『人口大国における食糧需給の状況』では、中国の化学肥料の投入量と穀物の単収の推移をグラフ化している。それによれば中国の耕地面積あたりの化学肥料の投入量は、1978年を100としたとき2000年代には500以上と5倍に増加した。
これに伴い1970年に1ヘクタールあたり3.4トンであった中国の米の単収は、1990年台後半には6.3トンと2倍近くに増加、同じく小麦も1.1トンから4.3トンへと4倍に増加している。
結果、2000年代に入ってからの中国の米、小麦、畜産物、野菜についての自給率は96%から101%となっており、自国の人口を養うのに必要な食糧を基本的に自国生産でまかなうようになっている。
例外は大豆で、これについては自給率が低下傾向にあり、2016年時点で13%と極端に低い。
中国で米、小麦の自給率が100%前後なのは、中国政府が食糧安全保障と農民保護の観点から多額の予算を組んで価格保証を行っているためである。家畜の飼料となるトウモロコシについても同様の補助がある。
中国の農家1戸あたりの農地面積は0.48ヘクタールしかなく、日本や韓国と比べても3分の1以下に留まる(2008年時点。農水省『日中韓の自由貿易協定の調査・分析』による)。このことから中国の穀物生産コストはブラジルやオーストラリアなど世界の農業大国と比べて高いものと推測されるが、これについてはデータがない。
世界市場での価格競争力がないため、米、小麦とも輸出は基本的に行っていない。
これは日本で米の自給率がほぼ100%で、輸出がほぼ0なのと同じ状況だ。
中国政府も日本政府も、穀物の生産余力は十分あるものの、100%を越えて作りすぎるとその分だけ政府の財政負担が増すので、いかに「ぎりぎり100%」に持っていくかに腐心しているのである。
2019年6月の日経新聞記事は、「中国の大豆生産は大規模化が遅れ、国産大豆の価格は輸入品に比べて1割高く、面積あたりの生産量もアメリカの4割にとどまる」としている。
生産コストが国際価格を上回る一方で、大豆に対する補助は手薄だった。それは中国において大豆はこれまで主要作物と考えられてこなかったためだ。
この状況も日本に近い。
結果、国内の農民は価格保証のつく米、小麦、トウモロコシに作付けをシフトし、油脂の原料・家畜の飼料として需要が急増してきた大豆については価格競争力に勝るアメリカ産、ブラジル産の輸入に頼る形が定着していった。
コストの安い大豆由来の飼料が広まった結果、国内食肉消費量の増加にもかかわらず、これまで家畜飼料の中心であったトウモロコシが余るようになり、過剰在庫対策のため中国政府は2016年に最低価格保証から生産者補助金の支払いに政策変更している(農畜産業振興機構『中国の穀物需給動向』より)。
中国は2001年に世界貿易機関(WPO)に加盟したが、現在まで発展途上国扱いを維持し、手厚い国内農業保護政策も目こぼしされてきた。
もしWPOでの中国の扱いが先進国に変わり、米、小麦、トウモロコシについても政府補助をやめ市場開放を行うことになれば、中国の食糧自給率は劇的に低下するだろう。
しかし中国政府に今のところその気はないようだ。
中国農業科学院は2018年に「2035年までに食用穀物自給率100%を達成し、主要畜産品および水産物についても自給率90%以上を維持する」と発表している(『人民網日本語版』より)。
中国農業科学院がこのような発表を行ったのは、同年に中国への大豆と牛肉の輸出国であるアメリカとの関係が悪化したことが理由だろう。食糧安全保障への不安を払拭するためともとれるし、アメリカ農民の支持が必要なトランプ政権に対し、「これからは輸入をやめて自給する」と宣言し、圧力を掛ける意図があったようにも思われる。
前出の日経新聞記事によれば、中国政府は現在、国産大豆増産の方針を掲げており、2019年6月には農業農村省次官が「2020年に生産量1900万トンをめざす」と述べている。これは2018年の2割増にあたる。しかし一方で増産に必要な予算措置は実施できておらず、省によっては19年の大豆生産への補助金は18年よりむしろ減額しているという。
「JBプレス」に発表された川島先生の記事『大豆貿易に意外な事実、貿易戦争は米国の勝利が濃厚』も、
「中国はアメリカ産大豆に関税をかけてアメリカ政府を恫喝しようとしたが、少なくとも当面はアメリカ産大豆を輸入せざるを得ないだろう」
との見方である。
中国は、14億の人口を支えてあまりある食糧生産余力を持っている。
中国政府がその気になれば、数年内に大豆の自給率を100%近くに高めることは難しくない。要は価格保証をするかどうかの問題である。
ただ実行すれば多額の財政負担が必要になる。上の記事で見るかぎり、中国政府にそこまでやる気はないようだ。
米中貿易摩擦を受けて米国産大豆に関税を上乗せし、一方で生産補助金の増額に動かないのは、中国政府が大豆を国民の政府支持率に大きく関わるほどの問題と見なしていないことの表れといえる。
ネット上では大豆自給率の低下をもって、「中国の農地は荒廃し、増えた人口を支えられなくなっている」といった言辞を散見するが、見当はずれである。
人口13億と世界2位で、近い将来に中国を越えて人口世界1位となることが確実視される、インドの食糧事情はどうか。
インドでは南東部は米を、北西部は小麦を主食としている。
インドでは1950年に3億人台だった人口が2000年に10億人を、2019年現在では13億人を越えるという、急速な人口増加が今も継続している。
20世紀後半は人口増加に食糧生産力が追いつかず、1960年代には飢饉も起きている。このためかつてのインドでは食糧、中でも主食である米と小麦の自給を悲願としていた(農水省『インドにおける農業政策の方向性』による)。
飢饉後の1970年代以降、インドの農業生産高は年を追って増加していった。
前出の『人口大国における食糧需給の状況』によれば、1970年に1ヘクタールあたり1.7トンであった米の単収は2000年代には3.0トンと2倍近くに増え、小麦は同1.2トンから2.7トンと2倍以上に増加している。
結果、1970年に6300万トンであった米の生産量は2000年に1億2700万トンと2倍に増え、小麦は2000万トンから7600万トンと3倍以上に増えた。
2011年以降のインドは米、小麦、雑穀、豆類すべてで自給率100%を達成し、最大の主食穀物である米については自給率110%に達し、年間1000万トンを超える世界最大級の輸出国となっている。(農水省『インドの農林水産業の現状及び農業政策』より)
インドが穀物の自給率を100%以上に高めて輸出もしていることは、インドの穀物生産コストが中国などより低く、国際価格で販売しても利益が出せる水準であることを示している。
インドの場合、食糧自給率100%を達成した現在でもなお耕地面積あたりの化学肥料の投入量は低く、中国と比較した単収も米が中国の5割、小麦は6割と大きな差がある。インドが現在の中国なみに農法を近代化するだけで穀物生産量はほぼ2倍となり、人口が今の13億人台から2050年に16億人台(国連予測による)に増えたとしても、必要な穀物を自給し、今と同様の大量輸出を続けることが可能だ。
ユーラシア大陸中央部を占める、旧ソ連圏の食糧事情はどうだろうか。
旧ソ連圏、現在の独立国家共同体(CIS)一帯は、冷戦時代の1970年代から80年代にかけて、世界最大の小麦輸入国だった。当時のソ連はアメリカを中心に海外から年間およそ3000万トンの小麦を輸入する、西側諸国にとっての「お得意様」だったのである。
旧ソ連地域ではベルリンの壁崩壊後、政治的混乱によってさらに農業生産量が落ちた。
しかし市場経済が浸透した結果、現在では逆にソ連時代よりはるかに収穫量が増え、年間1000万トンの小麦の輸出国となっている。
それでも旧ソ連地域の単収は、ロシアの場合で1ヘクタールあたり2.1トン(2011~2015年平均)と西ヨーロッパはもちろん中国・インドに比べても低く、生産余力は非常に大きい。
南米やオーストラリアなどの農業大国に限らず、中国、インド、ロシアといったアジアの大国も、現状のさらに何倍か食糧生産を増やす余地を残しているということだ。
以上を概観するだけで、世界人口が90億になろうと100億になろうと食糧供給力に関しては全く問題ないことがわかる。
●耕作放棄地の増加は食糧需給に影響しない
食糧危機説では、
「世界の農地はどんどん減っている。それは経済成長によって農地が工場や宅地に変えられてしまったためだ」
といった、まことしやかな説明が登場する。
これは先のFAOの「50年間で12%農地が増えた」という報告と矛盾するものだ。
しかし世界全体で作付面積、つまり実際に耕作されている農地の面積が減っていることは事実である。
その原因は主に先進国で生産調整のため休耕したり、耕作放棄された農地が増えていることにある。
日本では近年、耕作放棄地についての報道が多く、耕作放棄地の増加は由々しき社会問題とされている。
2015年度には耕地面積450万ヘクタールに対し、耕作放棄地はその1割近い42万ヘクタールに達した(内閣府『農地・耕作放棄地面積の推移』より)。その面積の大きさを印象づけるため、しばしば「埼玉県と同じ」「滋賀県と同じ」といったフレーズで語られている。
ところがここに、あまり知られていない事実がある。
日本には耕作放棄地の他に、それにはカウントされない非作付農地である休耕地(休耕田)がある。その休耕地の面積は実は、耕作放棄地よりはるかに広いのだ。
「政府統計(e-Stat)平成30年作物統計調査」によれば、2018年時点の日本の田の面積は240万5000ヘクタール、畑が201万4000ヘクタールで、合計で2015年より少し減って442万ヘクタールとなっている。
一方で同年の水稲作付面積は147万haで、田の面積の61%に留まる。これは日本の田んぼの3分の1以上、93万ヘクタールが休耕田となっていることを示す。
休耕田は生産調整の結果である。米あまり対策のため、政府が農家に補償金を払って耕作をやめてもらっている農地なのだ。
その面積は日本の耕作放棄地の2倍以上にも達している。
これは何を意味しているのだろうか。
はっきり言ってしまうと、
「日本では全体の3分の1以上の田んぼが余っている」
ということである。
耕作放棄地は全農地の1割近くまで増えているが、そのために日本で米が不足したとか、野菜が不足したという話は聞かない。
それは当然のことだ。
日本には休耕田だけで耕作放棄地の2倍以上もの農地があるのだから、もし耕作放棄地が増えて農作物が不足するようなら、今は休ませている土地で耕作を再開すればいい。
また耕作放棄地は別に「荒廃した農地」ではない。
荒廃農地は「現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地」であり、すぐに耕作を再開することはできない。こうした土地は2014年時点で27万6000ヘクタールある(ただし、うち半分の13万2000ヘクタールは再生利用可能とされている)。
耕作放棄地は「以前耕作していた土地で、過去1年以上作物を作付けず、この数年の間に再び作付けする考えのない農地」であり、農家の自己申告に基づく。
こちらはその気になれば短期間で耕作を再開できる土地だ。
その意味では耕作放棄地が今の2倍に増えたとしても、日本の食糧安全保障には何の影響もないことになる。
耕作放棄地の多くは中山間地と言われる、傾斜地に造成された水田や畑である。
こうした土地は農業機械を入れにくく、生産性が低い。手間がかかる割に生産量が上がらないためコスト高で、そうした地域での農業は商業ベースには乗らない。だから売り出したとしても誰も買わない。
今は農地の単収が上がり、生産性の高い平地の農地だけで日本人全員が食べるのに十分な米が取れるようになっている。平地で作る米だけで余ってしまうからこそ、優良農地に対してまで補償金を払って耕作をやめてもらっているのだ。それをしなければ米の値崩れや政府が負担している保管コストの増加を招いてしまう。
そんな状況では、山間の生産性の低い耕地をあえて耕す意味はない。
生産コストが商業ベースに乗らない土地で耕作を続けるとしたら、その土地のすぐそばに住み自家消費用の作物を作るしかない。それをしたくないなら耕作をやめる他ない。
耕作放棄は、経済合理性が機能した結果なのである。
国民生活にも国民の安全保障にも何の影響もないのに、なぜ政府やメディアは耕作放棄地が増えていることを問題視し、「なんとかしなければ」と言い合うのだろうか。
そこには「保護すべき対象が減ると票や権益が減る」という政治家や農水省の思惑が見え隠れする。一方で記事を読む側の日本人にも、一定の共感が生まれている。農地の減少を嫌う感情には、データや合理性では説明できない、多分に本能的な問題があるのだろう。
単収増加の結果として休耕地が増えることは、日本だけでなく先進国共通の現象だ。
北米にはアメリカとカナダを合わせておよそ9500万ヘクタールの休耕地があり、農家には耕作を停止する代償として政府から補償金が支払われている。
アメリカは自由市場を信奉する国なので、こうした休耕制度の多くには「土壌侵食の防止」「環境保全」といった名目がつけられている。しかしそれは建前にすぎない。本当の目的は生産過剰による穀物価格の暴落を防ぎ、生産コストが高い農地で営農する農家を保護することである。
ただし日本と違い、北米の休耕地制度に強制力はない。
北米の農家は企業家である。穀物価格が低迷している間は政府から補助金をもらって生産を停止しているが、穀物の市場価格が上昇し、生産した場合の利益が補償金を上回ると判断すると、政府との契約を打ち切って生産を再開する。
食糧供給力という面から見れば、休耕しているが放棄はされていない農地は、全て生産余力とカウントしてよい。
この種の休耕地はヨーロッパにも多く、世界全体で3億5000万ヘクタールに達する。
世界の農地はそれほど余っているのである。
●局所的な水資源の枯渇と農地の侵食
食糧危機説では、森林伐採や地下水の汲み上げによる環境破壊がクローズアップされる。
たとえば以下のようなものだ。
「現在、世界中で過放牧や森林伐採に起因する砂漠化が進行している。中国では既に国土の27%以上、250万平方キロが砂漠化してしまった」
「世界75ヶ国の乾燥地帯・半乾燥地帯で、フランス国土に匹敵する6200万ヘクタールの灌漑農地が塩害で劣化している。インドのインダス川、ガンジス川流域では塩害による損害が小麦の40%、米の45%にも達した」
「日本の国土の1.2倍の面積を持ち、アメリカ中西部・南西部の穀倉地帯8州の農業を支えているオガララ帯水層の地下水位が過剰灌漑によって低下しており、地下水脈が枯渇しかけている」
「1960年代までは日本の東北地方とほぼ同じ面積があった中央アジアのアラル海が過剰灌漑のため干上がり、周辺地域では漁業が壊滅、農地も砂漠化が進んで荒廃している」
これらの事例は個々には事実である。ただそれら全てを合わせても、世界の休耕地面積にははるかに及ばず、食糧需給に影響を及ぼすほどの問題にはならない。
これまで見てきたように、砂漠化が進んでいるとされる中国では2000年代に入って食糧生産が順調に伸びて穀物の基本的な自給を達成しているし、塩害で甚大な被害が出ているとされるインドは2000年代に食糧生産が増えて食糧輸出大国となっている。
地下水脈が枯渇しかけているとされるアメリカのオガララ帯水層の地下水を利用する農地は合計で520万ヘクタールで、アメリカ全土の1億6000万ヘクタール(総務省『世界の統計2018』より)の耕地の3%強に相当する。これに対し、アメリカには保全休耕プログラム(CRP)に登録されているだけでそれより広い908万ヘクタールの休耕地が存在する。
なお現在ではこの地域で維持可能な農業を行うため、オガララ帯水層の上に位置する各州が協力し、水資源の保全を図る管理プログラムが実施されている。結果、地下水位の低下は抑えられ、グレートプレーンズ北東部の穀倉地帯では水位は既に上昇に転じている。
旧ソ連のカザフスタンとトルクメニスタンに接するアラル海は、灌漑のための過剰な取水によって面積が1960年当時の10%にまで縮まってしまった。これは環境破壊の典型例として世界的に知られている。
この周辺の地域はもともと降雨量が少なく、FAOでは栽培適地面積を600万ヘクタールと推定している。しかし旧ソ連時代、この地域にはアラル海を水源として、適正面積の6倍にも達する3610万ヘクタールの灌漑農地が造成された。
旧ソ連の官僚機構による、地域の実情を無視した計画経済の結果である。
アラル海から取水したとしても、造成された農地面積の維持は降雨量の制約から不可能で、造成された灌漑農地の多くはその後、放棄せざるをえなかった。ただこの灌漑農地はもともと綿(コットン)の生産のために作られたものであり、その縮小により世界の食糧需給に影響が出ることはなかった。
現在ではカザフスタン側の小アラル海では堤防の建設などにより一時に比べ水位が上昇し、漁業も復活している。
カザフスタンの人口は1800万人で現在、旧ソ連圏ではウクライナ、ロシアに次ぐ穀物輸出国である。
一方、トルクメニスタン側では塩害は収まったものの、大アラル海の大部分が失われ、復旧は困難と見られている。トルクメニスタンはもともと砂漠気候で農業生産力は小さく、人口も500万人と少ない。食糧輸入国ではあるが、天然ガス・石油というエネルギー資源に恵まれ、外貨収入は多く所得水準も高い。
両国とも食糧不足に悩むことはないだろう。
結局、食糧危機説で取り上げられる「農地の劣化」は、世界の食糧需給を左右するほどの問題ではないのだ。
●肥料は枯渇しない
食糧危機説でよく耳にするのが、「肥料は枯渇しかけている」という話である。
これは事実だろうか。
前述のように植物の三大栄養素は窒素、カリウム、リンである。
このうち収量の増加に最も効果が大きかった窒素肥料は空気中の窒素を固定することで製造されており、原料は無尽蔵といえる。
カリウムは現在は主に岩塩の鉱床から採取されている。岩塩鉱床はそれ自体が豊富な上、カリウムは海水中にも大量に存在するため、こちらも枯渇の心配はない。
三大肥料で唯一問題となりうるのがリン(リン酸)である。
リンは生物の体を構成する上では必須の元素だが、存在量は少なく、化石や鳥の糞など生物由来の鉱物資源から採取されている。
2007年から2008年にかけての食糧価格の高騰局面ではリン肥料の市場価格も急上昇し、「資源の不足のためリンの生産量・消費量は数十年のうちにピークに達し、以後急減する」という「リンのピーク仮説」が広く信じられた。
ところがその後、この説の前提を完全に覆すような統計の変更があった。
リンの資源量について世界でほぼ唯一の公的調査機関であったアメリカ地質調査所では、2010年まで世界のリン鉱石の経済的鉱量(1トン当たり100ドル未満で採掘・選鉱できる鉱石の埋蔵量)を57億トンと推定してきた。
しかしこの年、国際肥料開発センターが「リン鉱石の経済的鉱量はモロッコだけで510億トン存在する」と報告。さらに「ロシアやアルジェリア、セネガルなどでも従来より多くの資源量がある」とした。
アメリカ地質調査所も報告の正しさを認め、その後、リン鉱石の推定経済的鉱量をそれまでの10倍以上となる650億トンに変更したのだ。
国際肥料開発センターによれば、採掘選鉱コストが採算ベースに乗らない(トン当たり100ドル以上)ものまで含めたリン鉱石の資源量は現在、2900億トンと推定されている。
(『西尾道徳の環境保全型農業レポート NO.234 リン鉱石埋蔵量の推定値が大幅に増加』より)
少し前の2010年まで「このままではあと60年から130年で枯渇する」とされていたリン鉱石の資源は、今の採掘量のまま数千年間堀り続けられる量にまで一気に増えてしまった。
もともとリンは窒素のように空気中に放出されてしまうことはなく、土に吸着されやすい。一定年数継続的に施肥すれば、その後も土壌の中で高い濃度を保つ。
このため長年にわたりリン肥料を農地に投入してきたヨーロッパやアメリカなどでは、1980年代以降は使用量を減らしている。
日本の場合も戦後、大量の肥料が農地に投入され、既に日本の農地の多くはリン酸過剰状態になっているとされる。農水省は昭和30年代に肥料投入の基準を決めて以降、50年以上もそれを変えていないが、いずれこの基準も変更されるだろう。
今後はこれまで化学肥料を大量に投入してきた地域ではリンの需要は低下していくと考えられる。
もちろんこれまで化学肥料をあまり使ってこなかった地域では、新たに生産量を増やす必要が出ればリン肥料の投入量は増えるだろう。
そうはいっても世界の農地面積は過去50年間で12%しか増えておらず、世界の食糧大国が需要に合わせて休耕地を設け供給をしぼっている現状では、農地が今後大きく増える可能性もない。一定面積の農地に一定量のリン肥料が投入されれば、土壌に滞留するというリンの性質上、その後はもう新たな投入は必要なくなる。
以上より現状で肥料の枯渇により食糧危機が起きることは、ありえないと言える。
人類にとってそれより先に心配すべき問題が山ほどあることは間違いないだろう。