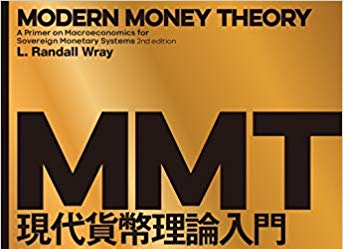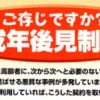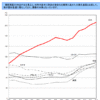(承前 「成年後見の申し立ては、慎重の上にも慎重に(中編)」より)
目次
●専門職後見人の被後見人への侮蔑的態度
現在の後見制度は、2000年の介護保険の制度化に合わせて創設されたものである。
それまでは認知症の人に対しては禁治産制度で対応していた。しかし介護保険では入居者と施設の関係が「措置」から「契約」に変わったため、「契約といっても、認知症ではできない」「それでは欧米で一般的な後見制度を作ろう」ということで急遽、後見制度が創設されたという経緯がある。
しかし法曹関係者、特に高齢の弁護士には、「被後見人=禁治産者」というイメージが刷り込まれているようで、被後見人に対して侮蔑的な態度を取る者が少なくないという。
中には親族の目がない場所で、認知症の被後見人の胸ぐらを掴んだり蹴りを入れたりする者もいる。そうした行為のほとんどは他人に見つかることはない。見咎められるのは被後見人が入居している施設の介護職員がたまたま目にした場合などに限られ、それもよほど目に余るものでなければ、公の場での告発には至らない。
専門職後見人のそうした態度は、被後見人の人権を無視した非人道的な扱いに如実に表れる。
たとえば専門職後見人が家族に無断で被後見人を介護施設に入居させ、その施設の名前すら家族に教えようとしなかっため、子供たちが親の死に目に会えなくなってしまったというケースがある。
あるいは後見人が介護施設と組み、被後見人を入居させた上、2年間にわたり面会謝絶としてしまった事例がある。
亡くなった後に残された被後見人の手記には、
「お腹が空いた」
「お腹が空いた」
という言葉が書き連ねてあった。
まさに人として最低の所業といえるだろう。
こうしたケースを見ると、現在の後見制度の人権無視の実態は禁治産制度時代以下ではないかと疑われてくる。
●多発する専門職後見人による横領事件
後見人による横領等の事件は例年、相当な件数に上るものと見られるが、犯罪件数についての数字は公表されていない。
仮に後見人関連の統計に示されている「解任」事例が犯罪に相当するとすれば、2000年度の制度開始から2015年度までの16年間で4390件に達する。
同期間中の後見制度の利用総数は約40万件なので、総数の1%で解任事由に相当する横領等の事件が発生している計算だ。
解任事例の多くは親族後見人によるものだが、実際には専門職後見人による横領も統計をはるかに上回る数に達すると見られる。なぜなら専門職後見人の場合、横領を行っても解任や刑事告発に至る割合はごくわずかでしかないからだ。
専門職後見人の不正に気づいて告発するのは、ほとんどが親族である。しかし後見人には被後見人の家族に対して業務内容を報告する義務はないので、家族が後見人による横領に気づくのは、誰の目にも明らかなほど問題が大きくなった場合に限られる。
特に被後見人に家族がいない場合は完全なノーチェックになってしまう。そうしたケースで横領が発覚することはまずない。
せいぜい年に一度の後見事務報告の際、コピーして添付することになっている預金通帳の数字が書き換えられていることに家庭裁判所が気づき、不正行為が発覚することがある程度だ。
いやしくも法曹関係者が通帳の偽造をするなど信じ難いことだが、実際に刑事事件になったケースを見ると、業務上横領、背任に加え、文書偽造が罪状に数えられていることがしばしばある。
横領など不正行為を行っていると疑われた専門職後見人に対して、親族から解任請求が出された場合、家庭裁判所による調査が行われる。
しかし調査の結果、不正が強く疑われた場合であっても、ほとんどの場合は家庭裁判所から辞任勧告が出されて終わりになる。本人が横領した金を返して後見人を辞任することで、「お咎めなし」となってしまうのだ。
規定上、専門職後見人は一度解任されると二度と後見人になれない。本業で稼げず後見人で食べている弁護士や司法書士にとってこれは一大事であり、また家庭裁判所側も自分が選任した後見人なので事を荒立てたくないという意識が働き、辞任で済ませてしまうことが一般的になっているのだ。
結果、一度横領を働いた弁護士や司法書士が何の罰を受けることもなく、繰り返し家庭裁判所から後見人として選任されることになる。
辞任の件数については2015年度の1年間で「申出」が1万751件となっており、うち97%が辞任を認められている。日本の後見人の数は約20万人だから、選任された後見人のおよそ5%が毎年辞任している計算だ。
辞任の理由は、後見制度が始まった当初は後見人の病気または事故、引っ越しによるものがほとんどだった。しかしここ数年はその多くが、上記のような刑事告発にまでは至らない実質的横領によるものとみられる。
●調査人制度の矛盾
後見人の業務が適正に行われていない疑いが出てきた場合、家庭裁判所は「調査人」を選任して調査を行う。
ここで疑問な点がある。
調査人に対する報酬が、被後見人の財産の中から支払われているのだ。その費用は1件で20万円にもなる。
家庭裁判所が選任した後見人が問題を起こし、それを調べるための費用を被害者である被後見人の財産から徴収するというのは、どう考えてもおかしな話だ。
もともと家庭裁判所には、家庭裁判所調査官が所属している。家族の意向を無視して自ら選任した専門職後見人の不正を調べるのであれば、その調査官を使い、無償で調査を行うのがあるべき姿のはずである。
それ以上に大きな問題がある。
調査業務を委託される調査人は基本的に、専門職後見人と同じく弁護士なのである。
弁護士の世界は狭い。裁判所に選任された調査人から調査対象である後見人への情報のリークは日常的に起きている。
若手弁護士が後見人をしている先輩格の弁護士の調査を委託され、当の本人に「先輩、ヤバいですよ。オレんところに調査依頼きてますよ」と教える。注進を受けた弁護士のほうは、「そうか、わかった」と、横領したカネをこっそり返して後見人を辞任する。そんな馴れ合いが横行しているのだ。
まさに「泥棒を調べるのに泥棒を使う」ような話である。狭い業界で生きている弁護士の調査を別の弁護士に担当させるという制度設計そのものが、根本的に間違っている。
後見人の横領の規模が大きく悪質で、辞任では済まずに解任されるケースがある。
解任された元後見人が横領した財産を返そうとしない場合、新たに選任された後見人は被後見人に代わって奪われた財産を取り返さなければならないはずだ。
ところが実際には新任の後見人には、前任の後見人の横領についての回収義務がない。
後見人同士が弁護士、司法書士など同業なので、「仲間内から取れない」という事情があるのだという。
こんなバカな話はない。が、それがまかり通っているのが後見制度の世界なのだ。
●法曹関係者の中でも質が低い専門職後見人
専門職後見人による犯罪が頻発する理由はなぜなのか。
そこには「後見人を請け負っている弁護士や司法書士には、もともと本業がうまくいっていない者が多い」という現実がある。
後見業務は典型的な「非訟非訴」事件で、行政に近い業務である。弁護士の場合、後見業務がやりたくてその職を志す者はいない。訴訟等で忙しい弁護士は自分からは後見業務を受けたがらないのが普通だ。
後見人を引き受けている弁護士の多くは高齢者か若手で、事務所の経費をまかなうための運転資金が不足し、やむなく後見人を引き受けている。もともと金に困っているため「今月50万円足りない。ちょっと借りて後で返そう」などと考え、簡単に犯罪行為に手を染めてしまう。
先に被後見人に対する専門職後見人の侮蔑的態度に触れたが、彼らの中でももっとも横柄なのが、各地の弁護士会の会長など名誉職にある弁護士だという。
こうした弁護士もしばしば後見人に選任されている。それは後見業務で日銭を稼ぐ必要があるためだ。
名誉職に就こうと考えて選挙に出るような弁護士には、一等地に大きな事務所を構えている者が多い。
本人の腕がよければいいが、結果がきびしく問われる訴訟事件を勝ち切る力がなく、若い弁護士たちに見放されて出ていかれてしまうと、月に200~300万円もかかる事務所コストが維持できなくなる。
そこで事務所を維持する費用を稼ぐため、後見業務の受託を申し込むのだ。
この種の弁護士たちの感覚には異常なものがあり、横領を指摘されても平然と「ちょっと拝借しただけだ」という態度をとる。「法曹関係者という以前に、社会人としてどうなのか」と感じる人間が少なくない。
●いかにして家庭の悲劇を回避するか
今の日本で成年後見を申し立てるとは、家庭裁判所に選任されてくる法定後見人に家庭の資産を押さえられ、家計の全権を奪われることに等しい。
家計は分断され、被後見人の財産は顔も見たことがない弁護士や司法書士の判断でいかようにも処分されたり、家族のために使うことを止められたりすることになる。
こうした事態を避けるために、我々一般人はどうしたらいいのか。
やむを得ず成年後見を申し立てる場合でも、家庭裁判所による一方的な専門職後見人選任を避けるための裏技が一つある。
申し立ての際、被後見人となる人の財産を「不明」とするのだ。
資産額不明ということは、無資産の可能性があるということ。そうした被後見人は専門職後見人が忌避するため、申立人がそのまま後見人に選任されることが期待できる。
後見人に選任されると、それから1か月以内に被後見人の財産目録を作成し家庭裁判所に提出する必要があり、そこで資産額が明らかになる。
「けっこうあるじゃないか」と嫌味を言われるだろうが、そこは適当に流しておけばよい。
より抜本的な対策は、「任意後見人制度」を利用することである。
日本には家庭裁判所が一方的に選任する「法定後見人」とは別に、被後見人が元気なうちに将来に備えて後見人を決めておく制度がある。そこで決められた後見人を「任意後見人」と呼ぶ。
任意後見人には家族でも知人でも、被後見人となる本人が誰でも好きな人を選ぶことができる。
妻や息子など家族に依頼する人が多いが、「お金のことだから他人がいい」と、あえて第三者を選ぶ人もいる。
任意後見人は一度決めても、本人の気が変わったらいつでも変更できる。
予め後見人を決めておけば、家族も「どんな人間がやってくるかわからない」という恐怖から逃れることができる。
「後見の杜」でも、「70歳になったら任意後見人を立てる」ことを勧めている。
任意後見人を選任するには、本人の認知能力がしっかりしているうちに公正証書を作成し、後見人を登記しておくことが必要だ。
公正証書は全国280か所にある公証人役場で作成する。手数料が5万円ほどかかり、本人と後見人候補が一緒に公証人役場に赴く必要がある。
高齢者の中には「まだ当分はなんとかなるだろう」と思っている人が多い。だが自分が将来どうなるかなど予想できないものだ。任意後見人は、まだ頭がはっきりしているうちに選んでこそ意味がある。銀行で預金が下ろせなくなるほど自分の頭が衰えてしまうことを想像できる人は少ない。
「うちは息子がいるから大丈夫」という人もいるが、これも大きな間違いである。
中には本人の認知障害が進み、「うちはもう手遅れだ」と思っている家庭もあるかもしれない。
認知症が始まってからでも症状が軽度であれば、任意後見人を選任することは不可能ではない。自分の名前が書け、口頭で住所が言えて、「お金についてはご長男さんにすべてお任せするということでいいですか?」という公証人の質問に「はい」と答えられれば、任意後見人の選任は認められる。
家族で話し合い、本人の調子のいいときを見計らって公証人役場に連れていけば、チャンスはあるだろう。
ただし、これらの方法を使って親族を成年後見人とすることに成功しても、それに対して家庭裁判所は確実に成年後見監督人を選任してくる。その点は覚悟しておかねばならない。
●法曹界は認知症高齢者の資産に狙いを定めている
2016年、「成年後見制度の一層の活用」を趣旨とする「成年後見制度利用促進法」が議員立法により成立、施行された。この法律に基づき、2017年3月、「成年後見制度利用促進基本計画」が閣議決定されている。
この法律制定の音頭を取ったのは公明党だが、背後でこれを推進していたのは、全国各地の司法書士会を束ねる「司法書士会連合会」である。
法曹界は自らの利権を拡大するため、各地の家庭裁判所と弁護士会、司法書士会が一体となって政治に取り入り、成年後見制度の普及を促進しようとしている。
この問題は誰にとっても決して他人事ではない。
全ての人は歳を取り、いずれ認知能力が衰える。自分や家族がそうなったときに備え、元気なうちから対策を立てておかなければ、家族に悲劇が訪れることになる。
今の日本では被後見人もその家族も、法定後見人を自ら選ぶことができない。
家庭裁判所が不正行為に手を染めるような劣悪な後見人を選任してきた場合も、それを拒絶する権利は本人にも家族にもない。
告発の末、悪質な専門職後見人の辞任もしくは解任に成功したとしても、すぐにまた家庭裁判所が業界団体のリストから選んできた専門職後見人をつけられてしまう。
被害に遭った家族が「もう後見人などごめんだ」と思ったとしても、その意向が考慮されることはない。
こうした現状を考えれば、たとえ夫や親が認知障害になったとしても、成年後見の申し立てには慎重の上にも慎重でなければならない。
はっきり言えば、避けられるかぎり極力避けることだ。
そして万が一に備え、70歳になったら任意後見人を立てておこう。
それが高齢者の資産に狙いを定めている法曹関係者から一般人が身を護るための、最善の方法である。
以上の内容は筆者が宮内代表からうかがった話をもとに、筆者が自分で行った調査の内容を加えたものである。
より正確で詳細な内容を知りたい方は、ぜひ下で紹介している宮内代表の近著を手にしてほしい。そして同時にその著書に対して寄せられた読者の方々の書評もぜひ、目にしてほしい。
(追記)
2019年3月、成年後見制度の利用促進をはかる国の専門家会議の場で最高裁は「成年後見人には身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示した。またこれまで限定的だった成年後見人の交代についても現状を改め、状況に応じて柔軟に交代・追加選任を行うものとした。これらの見解は既に2019年1月に各地の家庭裁判所に通知を行ったとしている(「朝日新聞」記事より)。
この新たな最高裁方針は、2010年以降に専門職後見人が増え続ける一方であった現状を大きく変える可能性がある。
実際に各地の家庭裁判所でどのような運用が行われるかは現時点では明らかではないが、引き続き状況を確認し、本記事でも報告していきたいと思う。