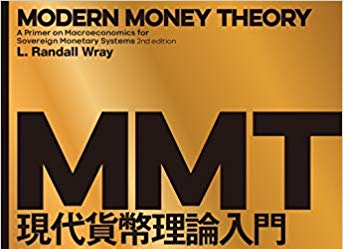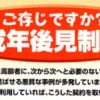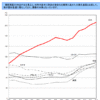目次
●知能も学力も半分は遺伝
今回は心理学者ジュディス・リッチ・ハリスの『子育ての大誤解』という本の紹介である。

本書はざっくり説明すると、
「『子どもは親の育て方次第』と思っている人が多いが、そんな考えは事実無根の『子育て神話』にすぎない」
「子どもは3~15歳ぐらいまでに過ごした子ども集団で一生を方向づけする」
という内容で、現在子育て中の身としては非常におもしろかった。
日本では2000年に最初に出版され、2017年に橘玲氏による新訳が出ている。筆者が本書の存在を知ったのも橘氏自身の著書を通じてである。
ただこの本、話がテーマごとに整理されておらず、あちこちで同じ主張が繰り返されていてわかりづらい。自分の理解のためにもちょっと整理しておこう、というのが本エントリーの趣旨だ。
行動遺伝学という学問分野がある。一卵性双生児と二卵性双生児の違い、片方が養子に出された一卵性双生児同士の違い、血のつながった兄弟と養子の兄弟の違い等を調べることで、知能や性格、体格、運動能力などのどの程度が遺伝で、どの程度が環境によるものなのかを明らかにしていくものだ。
こうした研究は北欧をはじめ世界各国で行われており、日本では慶応大の安藤寿康教授や東京大学教育学部附属中の研究が有名だ。
安藤教授の『日本人の9割が知らない遺伝の真実』という本によると、身長や指紋は98%が遺伝で決まる。ただ環境の影響もないわけではなく、一卵性双生児でも指紋はわずかに異なり、ATMの指紋照合機でもその違いは判別できるという。
体重は身長よりは低いが、それでも88%は遺伝で決まる。
これは少し意外な結果だ。
体重は食生活で変化するし、ダイエットすれば数キロから数十キロ減ってしまう。それでも基本的には遺伝で決まっているらしい。
知能指数(IQ)は遺伝が54%。学力はもう少し低いが50%以上が遺伝だという。
学力は勉強次第でいくらでも上下するものなのに、知能指数と学力とで遺伝の影響の差が少ないのも意外な気がする。
たぶん「どれくらいがんばって勉強するか」にも遺伝が関わっているのだろう。
●家庭の違いや保育施設の違いは子どもの発達には無関係
遺伝を除いた残りが環境の影響となる。
行動遺伝学では環境のうち、兄弟をより似せていくような環境を「共有環境」、兄弟の違いを作るような環境を「非共有環境」と呼んで区別している。
ごく大ざっぱに言えば、共有環境とは家庭環境のこと。
同じ家庭内では兄弟、特に双子はほぼ同じ扱いを受けている。二人が同じ扱いを受ければ、それは二人をより似させる方向に影響を与えるはずだ。
非共有環境とは兄弟が別々に影響を受けたこと。
同じ家庭に育ったとしても、親が兄弟で扱いを変えれば、それはそれぞれにとって別の経験、非共有環境ということになる。
双子や養子で違いを調べてみると、家庭に代表される共有環境の影響は世の中で想像されているよりずっと小さいことがわかった。
一卵性双生児の片方が別の家庭に養子に出されても、身長も体重もほとんど変わらない。学力や性格もよく似ている。
逆に血のつながらない養子がある家庭にもらわれ、その家の子と一緒に育てられても、身長や体重はもちろん、学力も性格も全然似てこない。
ハリス風に言えば、
「子どもがスミス家で育てられようが、ジョーンズ家で育てられようがその差はまったくないか、あってもわずかである」
ということ。
育て方による学力の違いなど、ないと同じなのだという。
こう断言されると、意外という他はない。
またハリスは、
「研究資料によると、専門家により評価された保育園の質の違いはほとんどの子どもたちの発達になんら影響はない。もし影響していたとしても微々たるものであることが証明されている」
ともいう。
どの保育園に入れようが、子どもの発達には何の関係もない。
これも驚きの結果だ。
幼児教育に熱心な人にはショックかもしれないが、これらは世界各地で行われた別々の研究を通じて繰り返し確かめられている、疑いようのない事実だという。
家庭環境だけでなく、保育施設の違いも子どもの発達に影響を与えないとすれば、教育熱心なパパやママが幼児用の教材を買い込んだり、懸命になって幼稚園選びをしている意味はどこにあるのだろう。
●子どもの性格は子育てでは変えられない
行動遺伝学に基づく調査結果によれば、やさしいとか外交的とか攻撃的といった性格の違いにも、家庭での育て方の影響は全く見られない。
性格はざっくり50%が遺伝で決まり、残りは非共有環境で決まる。これは調査で明らかになっている。
ニュージーランドの研究では、同年代の他の子どもたちより衝動的で怒りやすかった3歳児、課業に集中するのが苦手だった3歳児は、その性格を大人になっても維持する傾向があり、成長したときケンカや犯罪、喫煙など「健康を害する行動」が多く見られた。
犯罪者によく見られる攻撃性の高さ、衝動性の高さ、他人の気持ちへの鈍感さといった性格特性は、度が過ぎると子ども時代には「行動障害」と診断され、成人すると「反社会的人格障害」とされる。
こうした性格は研究により遺伝することがわかっている。
性格の半分が遺伝としても、残り半分については環境の影響があるわけだ。
だが調査の結果から、性格に影響を与えるのは共有環境ではなく非共有環境のみであることが判明している。
養子と実子の比較研究などから、
「同じ家庭で、同じ親によって育てられても、そのことは成人後のきょうだいの性格になんら影響を及ぼしてはいない」
「体外受精によって生まれた子どもたちの親は最も優秀な育児を施しているとされるが、子ども自身は感情、行動、親子関係に関する測定値のいずれにおいても、他の家庭の子どもとなんら変わりない」
といったことが明らかになっているのだ。
つまり家庭での育て方は、成人後の性格には関係ないのだ。
よく「虐待は連鎖する」と言われる。
実際に親から虐待を受けて育った人は、家庭を作ったとき自分の子どもを虐待する確率が高いことがわかっている。
また虐待を受けた子どもは、虐待と無縁の子どもに比べて、攻撃性が高く、友人関係を築くのも、それを維持するのも苦手で、学力も低いことがわかっている。
しかしそうした傾向が「虐待」という行為から生じたという証拠は見つかっていない。
つまり、
「親から虐待されたから自分の子を虐待する」
のではなく、
「子どもを虐待するような性格を親から受け継いだから自分の子を虐待する」
と考えられるのだという。
アメリカの「意識が高い系」の家庭では「体罰を与えると子どもが攻撃的な性格になる」と信じられている。
これに対し心理学者マージョリー・ガンノウとキャリー・マリナーは、
「子どもたちのほとんどに関しては、体罰が子どもに攻撃性を教えているという主張は根拠に欠けると思われる」
と結論している。
アジア系アメリカ人の親はヨーロッパ系アメリカ人の親に比べて子どもへの体罰が多いが、アジア系の子どもたちはヨーロッパ系の子どもたちに比べて攻撃的ではない。
家庭で度重なる体罰を受けてきた子どもたちが、体罰を受けたことがない子どもたちに比べて、特にケンカの回数が多いということもなかった。
体罰を与えるから子どもが攻撃的になるのではなく、体罰を好む親の性格が子どもに遺伝するため、体罰を受けている子どもには攻撃的な性格が多くなっていると考えられるのだ。
日本でも育児カウンセラーが勧めている、
「ほめて育ててモチベーションを引き出す」
「絵本の読み聞かせでコミュニケーション能力を育てる」
「親がたびたび抱きしめてあげることでやさしい子に育つ」
といったアメリカ発の子育て法についても、効果があるという証拠は見つかっていない。
確かに相関関係を調べると、抱きしめられることの多い子は、たびたび体罰を受ける子より性格的に健全な傾向がある。
だがそれは原因と結果が逆なのだ。
調査の結果は、
「抱きしめられることの多い子はやさしい子になり、体罰を受けることの多い子は困った子になりやすい」
のではなく、
「やさしい性格の子は抱きしめられることが多く、困った性格の子は体罰を受けやすい」
ことを示している。
ハリスは母親としての自分の経験から、
「親は2人の子どもを同じようには育てない」
と断言している。
なぜなら子どもはそれぞれ違うので、同じように育てようと思っても不可能だから。
おとなしい子はあまり叱らないし、いたずらな子はしょっちゅう叱る。
笑顔がかわいい子はどうしてもかわいがるし、無愛想な子はあまりかわいがらない。
「自閉症の赤ちゃんは親と視線を合わせることはない。微笑み返すこともなく、親の姿を見ても喜ぶそぶりを見せない。親としては自分の存在を喜んでくれない赤ちゃんを心から歓迎することは難しい」
「特定の子どもに対して親がどう振る舞うかはその子どもの年齢、容姿、現状、現在および過去の品行、知能、健康状態によって変わってくる」
という。
このように、
「本人の遺伝により周囲の環境が変わり、その環境に本人が影響を受けること」
を「間接遺伝子作用」と呼ぶ。
ハリスは子育てのやり方と子どもの性格が一見関係しているように見えるのは、この間接遺伝子作用の結果であって、
「親の育て方によって子どもの性格が変わってくる」
という広く信じられている考えは、
「母親に余計なプレッシャーをかけるだけの『子育て神話』にすぎない」
と切り捨てている。
●長男も次男も一人っ子も、性格に変わりはない
日本では、
「一人っ子と兄弟のいる子では性格が違う」
「長男と次男では性格が違う」
と広く信じられてきた。
これは欧米でも同じらしい。
アメリカの場合、
「上の子は責任感があり、感受性が豊かで人に頼る傾向がある」
と見られている。
ところが近年の研究によれば、そうした思い込みは事実でないことがわかっている。
成人向けの性格検査をいくら行っても、出生順位による統計的な違いは何も出てこないのだ。
「最近行われた大規模で緻密な研究では成人後の第一子とそれ以降の子どもの間には性格の違いはまったく見られなかった」
「過去一五年間で実施された研究では一人っ子と二人もしくは三人きょうだいの子どもとの間には恒常的な差は何も認められていない」
という。
にわかには信じられない気もするが、とにかく研究調査では、
「兄弟がいてもいなくても、兄弟の中の上でも下でも、本人の性格とは関係がない」
ということになっている。
これもまた、これまでの思い込みを覆す意外な事実だ。
●家庭で伝えられる文化もある
性格や学力とは違うが、「家庭の中だけで伝えられていく文化もある」ことは、ハリスも認めている。
たとえば宗教や料理など。
職業の選択についても家庭の影響は大きい。医者の子どもが医者になるケースが多いことは日本ではよく知られているが、アメリカでも同じ傾向があるようだ。
洋の東西を問わず、息子が父親と同じ職業を選ぶ確率は、そうでない人がその職業を選ぶ確率より高いのだ。
音楽の場合も、一般的に音楽好きの親であれば、その子どもも音楽好きな子になる傾向があるという。
ただそれは文化というより、遺伝の結果の可能性が高い。
先に触れた慶応大の安藤教授の研究では、
「音楽、数学、スポーツ、執筆などの才能は、ほとんどが遺伝で決まる」
という結果が出ている。
特に音楽は相関係数が0.9を越えており、ほぼ「生まれついての才能が全て」という世界だ。
そしてそれ以外のわずかな要因も全て非共有環境で、家庭での育て方は全く影響していないことがわかっている。
同じ家庭で育ったからといって音楽の才能がない人が音楽家になるわけではない。別々の家庭で育っても音楽の才能は変わらない。
しかしこれだけ遺伝の影響が強い音楽でも、非共有環境によって全く違った結果が生まれることがある。
ミネソタ大学の研究で、乳児期に離れ離れになり、それぞれ別の養父母に育てられた一卵性双生児のケースがあった。
一人はコンサート・ピアニストになり、その腕前はミネソタ・オーケストラをバックに独奏を披露するほどだ。もう一人は音符すら読めない。
養母の一人は家でピアノ教室を開いている音楽教師だった。もう一方の親は音楽とはまったく関わりがなかった。
当然誰もが、「ピアノ教師に育てられた子がピアニストになり、音楽と関わりない親に育てられた方は音符も読めなくなってしまったのだろう」と思う。
「双方の家庭の教育内容の違いが子どもの将来に影響したのだ」と思うからだ。
ところが意外なことに、ピアニストを育てたのは音楽と関係ない親の方だったのだ。
逆にピアノ教師に育てられた娘は音符も読めなかった。
この正反対の結果は、遺伝では説明できず、環境の差だったことは明らかだ。
ピアノ教師である母親はレッスンは行ったものの、強要はしなかった。もう一方の養母はピアノを習わせただけでなく、環境づくりに熱心に取り組んだというが、先にも断ったように、音楽に共有環境つまり育て方は関係しない。
育て方と関係ないからこそ、親の職業から想像されるのとは真逆の結果が生じたのだろう。
同じ遺伝を持つ二人のうち、何が一人をピアニストにし、もう一人を音符も読めない素人にしたのだろう。
ハリスはこの差を、「集団内での差別化」によって説明している。
家庭という集団において、母がピアノ教師の娘は、同じ楽器を選べば、母親と競合することになってしまう。だから母との差別化のために、娘はピアノの練習を避けたのだ、というのだ。
まあこれについては仮説のレベルを出ないだろう。
そもそもハリスは「子どもの将来は家庭と関係ない」説を主張しているのに、家庭環境の違いによってこれほど大きな差が生まれたと説明している時点で自己矛盾である。
同じエピソードを紹介した橘玲氏は、
「ピアニストの親を持った娘の周囲には音楽の才能に優れた子が大勢いたため、娘はその中で自分を差別化しようと、音楽以外の特色を身に着けようとしたのではないか」
と推理している。
●霊長類にイクメンはいない
行動心理学の研究からわかってきたのは、子どもの人格の形成において、家庭の影響はごく小さいという意外な事実だった。
ハリスはその理由を、文明以前の人類の育児環境に求めている。
霊長類はほとんど父親が育児に関わることがないが、これは婚姻のスタイルによるものらしい。
霊長類の中で遺伝的に一番人間に近いのがチンパンジーだ。
彼らは群れを作って生活している。群れの中ではメスは言い寄るオスを拒まない。
人気のあるメスが発情すると、オスは押し合いへし合いして交尾の順番待ちをするのだそうだ。
こうしたスタイルを乱婚型の婚姻形態という。
男女のペアが決まっていないので、子どもが生まれても父親が誰かわからない。
このためオスのチンパンジーは、特定の子の育児には関わろうとしない。育児は全て母親任せだ。
その代わりオスは、もしかすると自分の子かもしれない群れの中の子どもは公平に、やさしく扱う。
これは自分の子でない子どもは殺してしまうライオンやクマなどに比べれば、種の保存に適したやり方といえる。
たまにオスが特定の子どもやその母にエサをあげたりすることもあるが、それは父親としての愛情の発露ではなくて、交尾のために母親に取り入ろうとする求愛行動の一種とされる。
チンパンジーの母子は大変仲がいいので、
「母を得んとすれば、まず子から」
というオスの戦略なのだ。
人間もかなり昔はチンパンジーに近い、乱婚型社会を作っていたらしい。
そのためなのか、伝統的社会では今も子どもたちはひとまとめにされ、大人は自分の子かどうかあまり区別せずに扱う。
大人の男たちは育児には一切関わらない。父親が子どもの遊び相手になるようなこともない。チンパンジーと同じく、全て母親任せだ。
その代わり子どもが何か悪さをしているのを発見すると、大人なら誰でもその子を諭すことができる。
村中みんなで子どもを育てる。
それが人類の伝統だった。
人類も近年は一夫一妻制が確立され、子どもの父親が誰なのかがわかるようになった(もっとも研究によると、今でも一割くらい、実の父親が思っていた人と違うというケースがあるそうだが)。
最近は父親が育児に参加することも奨励されている。
しかし子育ては伝統的な父親の役割ではない。
最近の「イクメン」ブームは、霊長類の祖先から続く人類の伝統とはだいぶ違うのである。
さらに言えば伝統社会の親たちには、子どもをほめて育てようなどという高い意識は全くない。自分が叱るとき、子どもにいちいち理由を説明するような面倒なこともしない。
「伝統的な社会では、親が子どもをほめることはめったになく、子どもが間違った行動をとれば、罰に処すか脅す。その罰も、子どもの意図に関わりなく、行動の結果に対して処される」
つまり「腹が立ったらポカッとやる」が10万年以上続いた、人類の子育て法の基本だったのだ。
「ほめて育てる」などというやり方は、人類の長い歴史の中でごく最近に始まった、非伝統的な思いつきにすぎないのである。
●狩猟採集時代の子育ては3歳まで
チンパンジーの世界では、子育ては母親の役目で、母親は次の子が生まれるまで前の子の面倒をみる。
母子は育児が終わってからもずっと仲がいい。
これらは人間も同じだ。
伝統的社会では、人間の母親は次の子が生まれるまでしか育児しない。
というのも父親の手も借りず一人で育てなければならないので、赤ちゃん一人で手いっぱいだからだ。
しかも伝統的社会は多産多死で、妊娠可能になればすぐ次の子をはらむのが普通だった。
「伝統的社会では産後二年以内に妊娠することはまずない。二歳半から三歳ごろまでは母乳を飲みつづける。
母親はふたたび妊娠したとわかると突然に離乳する。
新たな赤ちゃんが生まれる頃には三歳くらいになる上の子は母親の胸の中から永久に追放される」
かつて人間の子どもはこのようにして、下の子が生まれたとたん母親から引き離されていた。
母親から引き離された幼児はその後、少し年上の子たちからなる子どもグループに加わる。
狩猟採集時代はもちろん農耕が始まってからも、人は長いことあまり人口の多くない集落で暮らしていたので、周囲に同年齢の子はほとんどいなかった。
乳離れして母から離れた子どもは、年齢に幅のある子どもたちの集団に加わり、年上の子どもたちと一緒に行動していたのだ。
伝統社会では、こうした遊び集団は親戚同士で構成されることが多い。
「たいていは年上のきょうだいがその子の面倒をみることになる。その子自身は五歳か六歳である。兄や姉は自分が近所の子どもと遊ぶときには弟や妹を引き連れていく」
兄弟でなく従兄弟(いとこ)や、若い叔母や叔父が同じグループにいることもある。どの場合でもグループ内で年長の者が年少の者の面倒を見る。
●昔、子どもは子どもに育てられた
子ども集団の年齢層はその社会の人口密度によって変わる。
2歳半から12歳までのこともあれば、6歳までのこともある。子どもの数が十分あれば、年長の子どもたちは幼い子どもたちとは別のグループをつくるのだ。
子ども集団の中ではみな仲がよく、年長者は言われなくても年下の子どもたちに食べ物を分け与え、他のグループの子から守ってやろうとする。
小さな子を危険から守ったり、ルールを教えて一緒に遊ぶのは大人ではなく、年長の子たちの役割だった。
年長の子どもたちは、ときには命がけで小さな子どもを守ろうとした。
チンパンジー研究家のジェーン・グールドの著書には、アフリカの6歳の男の子の話が出てくる。
彼が面倒をみていた小さな弟がオスのチンパンジーにさらわれてしまった。
男の子は必死でチンパンジーを追いかけて、そのため自分も襲われて大怪我を負ってしまったが、それでも弟を取り戻したという。
守ってやる一方で、年上の子どもがグループを仕切るのは当然のことだった。
上の子の言うことをきかない生意気なガキは、ぶん殴られて教育される。
「彼らの教え方はやさしくはない。力ずくはもとより、からかったり、バカにしたりするのも当たり前で、理屈に基づくことはない」
年下の子たちもその関係を受け入れていた。
「若いオスのチンパンジーは自分より年長のオスに、たとえ殴られようともひたすらついてまわる。これは若い人間の男の子にも当てはまる。幼い少年たちは年長のお兄ちゃんたちから荒い扱いを受けても、お兄ちゃんたちと一緒にいることを好む」
ところが今どきの親は、そういう関係が当たり前のことだとわかっていない。
ハリスは、
「アメリカの親たちは兄姉が弟妹を支配するのが自然なこととはわからず、子どもは対等であるべきだとして弟妹の味方をするため、兄姉の目には親が弟妹ばかりをかわいがっているように映る」
と、現代の先進国で親が兄弟の関係に口を挟もうとすることを、人間本来のあり方ではないと批判している。
●子どもの成長には仲間が不可欠
ハリスは本書で、「子どもの社会化の大部分は子どもたち自身で行われる」という、「集団社会化説」を提唱している。
「子どもたちは自分がある集団に属すると意識し、その集団の態度、行動、話し方、服装、身の飾り方を真似ることによって、ふさわしい行動とは何かを知る。子どもたちはたいてい、自動的に、そして自発的にそれを行う。彼らは仲間たちと同じようになりたいのだ」
「親を模倣するのは、親が正常にもしくはその社会を象徴するように行動しているとき、その社会に住む他の人々が行動するように行動しているときだけなのだ」
とする。
子どもは家の中と外で態度を使い分けている。
家族には外のことをあまり話したがらないし、外では自分の家の話はしたがらない。
学校でいじめにあってもそれを親に伝えないことが多いし、家で虐待を受けていても家の外の人には話したがらない。
親が家の外で子ども仲間がいるところに出てくると、子どもは落ち着かなくなる。自分が今どちらのルールに従うべきかわからなくなるからだ。
だが成長するにつれ、子どもは親より仲間のルールに従うようになる。
「子どもたちが歳を重ねるにつれて、同年代の集団に対して忠誠を表明することがますます重要になってくる。
思春期の子どもたちは家族で買い物に行くと、親の前後一〇歩ほど離れたところを歩く。仲間たちにその姿を目撃されたときに「私はこの人たちとは違うのだ」という立場を明確にするためなのだ。
この行為は子どもたちが親を愛しているかどうかとは関係ない」
伝統的な社会では幼い子どもたちは、自分の周囲の年長の子どもたちを見、その真似をして物事を覚えていく。
乳離れが済んだ子どもの教育に親が出る幕はないのだ。
「文字のない社会では、生きていくための知恵のほとんどは模倣を通じて学習される」
「何かを教えるときも言葉による説明はめったになく、大人がやることを目で見て覚えることが当然とされる」
周りの仲間を真似することは、今の時代でも子どもには本能として身についている。
1931年のこと、心理学者のケロッグ夫妻は生後10ヶ月の息子を、生後7ヶ月半のチンパンジーと一緒に育ててみることにした。
チンパンジーの子には人間の赤ちゃんの服を着せ、食事も同じにし、一緒に歯を磨き、同じように昼寝させ、お風呂にも入れた。
赤ちゃんとチンパンジーは仲良くなった。それはよかったのだが、問題は男の子が何かとチンパンジーを真似するようになったことだった。
一緒に柱を噛んだり、人間の言葉を覚える代わりに、食事のときに咆哮したりするようになってしまったのだ。
チンパンジーを自分の仲間とみなし、模倣すべき対象としたわけである。
さすがにこれはやばいということで、実験は9ヶ月で打ち切りになった。
我が子を実験台にするとは、さすが学者である。
幸いこの男の子はサルのような大人にはならず、名門ハーバード大学の医学部を卒業したという。
サルでも犬でも、成長期に近くに仲間がいないと社会性が身につかず、大人になってから他のサルや犬と仲良くやっていくことができなくなってしまう。
集団生活をする哺乳類では、成長期に仲間が近くにいないと、後々大きな問題になるのだ。
人間も同じで、特に4歳までに親しい仲間を持つことが重要だという研究がある。
4歳以前に孤児院に入り、お互いに愛着を抱かないように育てられた子どもは、友達と親密な関係を築く能力を失ってしまった。しかし4歳以降に孤児院に入った子どもにはそうした影響は少なかった。
子供時代を家の中だけで過ごした人は、青年期以降に心理的な問題が出る危険性が高いという。