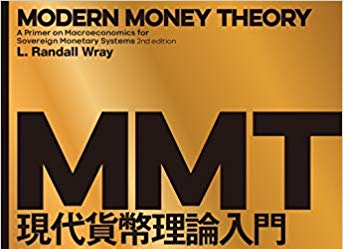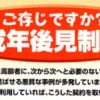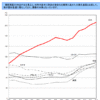目次
●持続可能性のない日本の自作農
本記事のテーマは、
「農地の個人所有と分割相続を前提とする農業には、持続可能性がない。したがって現在の日本では、自作農には持続可能性がない」
ということである。
ここに男性の戸主が個人で田畑を所有し、家族で耕作する農家があったとする。
戸主が死亡すると、日本の民法の規定では、耕地は妻と子どもたちに分けられることになる。
子どもが複数いて、その1人が娘ならば、相続の時点で他家に嫁いでいるだろう。嫁いだ先が同じ村落内の農家であれば、元の田畑を分割して、娘の夫が耕すことは可能だろう。それでも耕すための土地が分散してしまうと、農作業の効率は落ちる。
元の家では娘に分けた分、耕地が減ることになる。民法の規定通りとすれば、妻が2分の1、子どもたちが2分の1なので、子どもが2人ならば4分の1が失われる。土地が減れば生産高もそれに応じて減る。それまでの生産高が一家4人の生活に必要十分だったとしたら、3人分の生活しか賄えなくなる。
子どもの1人が息子で、その息子が農家の嫁をもらい、その嫁に相続で親から同じだけの土地が譲られたとすると、面積という点では前と同じになる。ただし嫁が同じ村落から来たのでない限り、その土地を耕すためには農期の間、毎日のように嫁の故郷に出向いて耕作しなければならない。嫁の出身地が遠方であったら、これは不可能だ。たとえ同じ村落内であっても、土地が分かれた分、農作業の効率は落ちる。
もし近隣の農家以外から息子の嫁を娶ると、耕作可能な土地は相続で減ったままになり、2代、3代とそれが続くと、農業で生活することは難しくなる。
娘を農家以外や、農家であっても遠方の家に嫁にやったとすると、娘に分割された土地は耕作者を失い、耕作放棄されることになる。
実家に現金が十分にあれば買い取ることも可能だが、そうした農家は必ずしも多くはない。また農業生産性の高い土地の多くは、農業によってそこから得られる利益に比べて高価であり、買い取っても経済的にペイしない。このため特別な事情がない限り、土地はそのまま耕作放棄されることになる。
現在の日本では就業者に占める農家の割合は3%程度でしかなく、農家の娘が同じ村落内の農家に嫁ぐ可能性は低い。このため基本的には農家で相続が発生するたび、耕作放棄地が増えていくことになる。
これを防ぐため仮に近隣の農家同士で婚姻を繰り返したとしても、土地は一代ごとに分割されるので、数代を経ると耕作の効率は著しく落ちてしまう。近隣同士での婚姻を繰り返すことは、配偶者選択の自由を狭めるだけでなく、何代かするうちに血族婚を回避できなくなり、遺伝的にも問題が多い。
このように現行の民法の下では、農地を個人が所有する限り、農業には持続可能性がない。相続のたびに土地は無限に細分化され、耕作地の放棄が続き、やがて消滅することになる。これは制度的に避けられない。
●なぜ長子相続制が生まれたか
現行民法以前(第二次大戦前)の日本では、農地は家督相続が基本だった。
家督相続とは、戸主が亡くなった場合に長男ひとりが全ての遺産を相続する制度である。
ウィキペディア「長子相続」では、「前近代社会では相続によって継承されるものは個人的な私有財産ではなく家産であると考えられていた。相続の第一目的は直系家族の維持(家の存続)であるとされ、それに最も適合的だったのが長子相続であった」と記述されている。
世界にも近代以前、長子相続が一般的だった地域は多いが、平等相続の地域も多かった。
「ヨーロッパの伝統的家族と相続」という研究記事では、19世紀以前のヨーロッパについて、「親の意志に基づく相続(ベルギー、オランダ、イギリス東部など)」「一子相続(北欧、ドイツ、フランス南部、イギリス西部など)」「平等相続(フランス北部、イタリア中部・北部、スペイン南部、東欧、ロシアなど)」があったとし、平等相続をさらに「核家族」「共同体家族」に分けている。
西欧中世の農村では、面積を測量した上で耕地をブロックに分け、各農家に平等に分配していた(フーフェ)という。ただし各農家は1家族だけではなく、内部では実質的な支配層と労働者に分かれていた。
一方ロシアなどでは血族が共同体を作り、耕地は共同体の共有地とされていた。
このように耕地が一族あるいは村落の共同所有である場合、平等相続であっても世代ごとに耕地が細分化されることはないため、農業生産力は世代を越えて持続できる。
この点は中国も同様で、血族が互いに近接して居住し共同体を作って、耕地や家畜を共有し、相続は諸子均分制、つまり平等相続だった。
研究記事「中国の家族制度の変遷」は、
「中国は古い家族主義の歴史を持つものの、核家族的な関係へと細分化することなく現在、宗族といわれるような大家族的関係を維持し続けることになる。その理由は、日本と違い、中国には本家・分家という別がないことが大きい。父の家産は息子たち全員に均等に分割される。従って、住居単位は小家族ではあるが、そのように細分化された家産ではやっていけないので必然的に、生活用具や農作業を相互援助しあう関係を続けていくことになる」
という。
人類の歴史を振り返ると、狩猟採集生活の間は相続など考える必要はなかった。
農耕以前の人類は血族を中心とする共同体を作って生活し、共同体がそれぞれの「縄張り」を他の共同体から守っていた。
その後、農業が始まってもしばらくの間、社会の形は共同体中心のままで、耕地も共同体に帰属するものだった。その場合は相続による土地分割の問題は発生しない。
ロシアや中国では、その状態が近代直前まで続いた。
しかし日本やドイツのように血族共同体の構成単位が細分化され、「家」を中心とした社会に変化すると、長子あるいは親の決定による一子相続制が一般化してくる。そうしなければ「家産」である耕地が細分化され、維持不能になってしまうからだ。
一子相続は誰の目から見ても公平な制度とは言い難いが、農業を主とするイエ社会において生産を維持するためには、他に選択肢はなかった。
●自作農の存続を不可能にした現行民法
戦後の1947年に改定された現行民法は、近代西欧流の個人主義、個人による私有財産制を前提としつつ、均等相続を規定した。
個人間の平等を優先する現行民法は、旧来の「家」を生産単位とする農業社会を全否定するものだった。この法律に従う限り、上で見たように「家」に帰属する耕地は世代を追うごとに細分化され、数世代のうちに農業で生活を維持することは不可能になってしまう。
だがこの法律を制定した当時の為政者たちに、そうした理解は希薄だったようだ。
逆に戦後まもなくから現在に至るまで、政治家や官僚は自らその崩壊を後押ししたイエ中心の農村社会をなんとか維持しようと、矛盾した努力を続けているように見える。
民法改正と同じ1947年、農地改革が実施され、地主の所有する小作地のおよそ8割が強制的に小作人に譲渡され、小作人のほとんどが自作農へ転換を果たした。戦前までの農村で進行していた農地の大土地所有者への集約が一転し、農地は一気に細分化された。誕生したのは大量の、農業で生活をぎりぎり維持できる程度の小規模自作農である。
1952年には農地法が制定され、「農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護」するという「自作農主義」を掲げ、地主や法人による農地所有を否定した。
民法によって自作農の世代を超えた存続を不可能にしておきながら、農地法によって自作農主義を掲げるというのは、絶望的に矛盾した政策であり、成功する可能性は皆無である。
農地を個人の所有物とし、自作農による生産に固執すれば、民法の相続規定による農地分割が進み、生産効率は低下し、日本の農家の大部分を占める小規模自作農では、一世代後には専業農家として生活を維持することが不可能となる。
実際に日本の農村ではそのようになった。
こうした施策を行う一方で、政府は農地の細分化によって生産効率が向上しないことを問題視し、1961年に制定した農業基本法では、「農業従事者が他産業従事者と均衡する所得を確保できる規模拡大の推進」が謳われた。
だが農地法で農地の所有権の移転にきびしく制限を課していたため、当然ながら農地の集約は進まなかった。
政府は自分たちが法律で強制的に農地を細分化し、農地の売買を制限しておいて、「農地の集約が進まないから農業生産が効率化しない。専業農家の生活が成り立たない」と言っていたのである。
耕作放棄地の増加も、民法改正によって当然に予測された結果だが、これについても政府は「耕作放棄地の解消及び発生防止が喫緊の課題(『耕作放棄地の現状について 平成23年 農林水産省』より)」として問題視している。
自家撞着としか言いようがない。
●日本農業に残された生存戦略
農業における最重要の生産財は土地である。土地は一定以下の面積に分割されると生産性が大きく低下する性質を持つ。一定面積以上のまとまった土地がなければ、農業で生計を立てることは困難である。
民法が相続により土地の分割を強制している以上、農地を個人所有する形での農業は世代を超えた持続可能性を持たない。したがって現行民法を前提として持続可能な農業をめざすなら、農地は個人所有としてはならない。
個人所有以外の農地の所有形態としては、
・共同体の所有とする
・政府あるいは自治体の所有とする
・法人の所有とする
という三つの形が考えられる。
このうち共同体所有は、私有財産制を大前提とする現行民法下では困難である。
政府または自治体が農地を所有し、これを耕作者に貸し出し、耕作者が高齢等で耕作不能となった場合には新たな耕作者を募集する、という形は検討に値すると思われるが、共産主義を連想させるためか、ほとんど議論の対象にもなっていない。
現実的な唯一の農業存続策は、農地を法人の所有とすることである。
法人による農地所有には、二つの形がある。
一つは既存の農家が家業を法人化すること。個人の名義となっている農地を法人名義とし、自らはその法人の出資者として議決権(株式)を持つ形とする。
法人化により、農業という事業の経営者と農地の所有者が分離される。相続が発生した場合も農地は分割を免れ、株式が分割されることになる。株式であれば、相続人が何人いても問題はない。数代の相続を経て株の所有者がいくら増えようと、農地はまとまったまま残り、実際にそこを耕作するのは農業法人の経営者ということになる。
法人同士であれば株式の譲渡により合併・買収することができる。意欲のある耕作者が農地を拡大したり、高齢等の理由で一つの法人から耕作者がいなくなった場合に近隣の法人が耕作を引き継いだりすることが容易になる。農水省が志向する農家の規模拡大にもつながる。
これが農業を法人化する一つの形であり、もう一つは他業界の企業や投資家が出資して農業法人を作り、耕作者を雇用する形である。
農業の法人化の障害となってきたのが、自作農主義を掲げて作られた農地法だった。
ただ農地法も2000年代に入って、自作農主義の看板は降ろさないまま、法人化を許容する方向に向かっている。
農地法は2009年に改定され、農地の賃借権を原則自由化し、株式会社であっても法人の売上の過半が農業に係るものであれば、農業経営を可能とした。
ここで想定されたのは、上で挙げた二つの形態のうち、農家が家業を法人化することだけだった。
構成員については「農業関係者が4分の3以上」「農業に無関係な者は不可」といった要件を、役員については「役員の過半が農業に常時従事する構成員」といった要件をつけ、一般企業が農地を取得して農業を始めることは事実上、禁じられていた。
その後、2016年に農地法が再改正され、一般企業(法人)の農地所有に対する規制を緩和した。
改正農地法は第一条で「耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、(中略)農地を効率的に利用する耕作者による(中略)農地についての権利の取得を促進」するとしており、農業を行う企業の構成員については「農業関係者が2分の1超」「農業関係者以外の者が2分の1未満」、役員については「役員の過半が農業に常時従事する構成員、かつ役員か重要な使用人の1人以上が農作業に従事」と、要件が緩和された。
これまで禁じてきた外部の出資による農業法人の設立にも、わずかながら道を開いた形となっている。
2016年改正後の農地法の規定でも、農地所有適格法人を「売上の過半が農業であることを要する」とした要件は残り、農業を業としない一般企業が農地所有適格法人になることは今も不可能である。
一般企業の農地所有適格法人に対する議決権割合は2分の1未満とされているため、子会社を作って農業を始めることもできない。
また設立された法人が実際に農地を所有するには、各市町村に設置されている農業委員会に許可を得る必要があり、農地の所有者に譲渡の意向があっても農業委員会が反対すれば農地は取得できないとか、農地所有適格法人の株主は株式の譲渡制限を受け、自由に処分できないため、投資から収益を上げる方法が限られているといった制限もある。
こうした制限の下で、2009年の改定前には1万社程度だった農地所有適格法人の数は、2018年に1万8000社となった。
農家(経営体としての認定農業者)の数は2018年時点で24万軒以上あるので、その1割にも満たない。
●日本農業には輝ける未来がある
農水省『農業労働力に関する統計』によれば、2018年時点の農業就業人口は175万人であり、2010年の261万人から33%減少している。平均年齢は66.8歳で、こちらは2010年比で1歳しか変わっていない。
統計からは高齢化がほぼ限界に達し、体力の衰えた農業従事者がリタイアする一方、その子ども世代は農業を継いでいないことが伺える。
8年間で3分の1がいなくなるという農業従事者の減少は今後も続き、それに応じて耕作放棄地も増加の一途を辿るだろう。
これからの農業はGPS付きの農業機械による無人での耕作や種まき、ドローンによる目視チェックや農薬散布、ロボットによる収穫、無菌管理された野菜工場といったAI化、無人化、人件費削減によるコストダウンが進む。
そのためには億単位の投資が必要だ。
平均年齢67歳で後継ぎもいない農家が、そのような投資を行う可能性はない。そもそも個人で持つ土地を耕している自作農にとって、無人化投資は金額的に無理がある。
今後の日本農業は法人が担うしかないのだ。
高齢の農家にとって、どうせ子どもが後を継がないのであれば、わざわざ法人化して農地を守る意味はない。したがって農家の法人化は今後もわずかずつしか進まないだろう。
日本の農業を守るためには、農業以外の分野から参入してくる企業に頼らなければならない。
そのためにはまず、他の産業と同様に農業においても個人ではなく法人が生産の主体となることを公に認め、農地法を撤廃または抜本改正して、農業法人の構成員や役員の要件、出資の規制といった民間企業の農業への参入障壁をなくし、農業委員会による農地譲渡の審査を廃止、耕作放棄地への課税を強化して不耕作地主に譲渡を促し、農地の集約と効率的な利用を促進する必要がある。
日本の自動車産業は世界に冠たる実績を残してきたが、それは「会社」という枠組みがあっての話である。
「会社」という枠組みの下で従業員たちがモノづくりの知識と知恵を共有し、研究開発や生産性向上に巨額の資本を投下することで初めて、個人単位では不可能なイノベーションを実現させる環境が整う。
もし第二次大戦後、法律で「工場は作業者みずからが所有することを最も適当であると認めて、その権利を保護する」などと定め、法人による工場の運営を否定していたら、どうなっていたか。想像してみてほしい。
日本の自動車産業は高いコストと低い技術力で諸外国に比べて全く競争力を持たない「三ちゃん工場」ばかりとなり、政府から莫大な援助と保護策を受けながら自給率は3割を切り、高齢者ばかりで誰も後を継ごうとしないという悲惨な状況になっていただろう。
それは今の日本の農業の姿である。
農業の発展を阻んでいた法の足かせが外されれば、農業生産の主たる担い手は企業となり、各企業がそれぞれの生産物の拡販とブランド力を競い合うことで、生産コストは大きく低下し、品質は向上し、農薬の使用量も激減するだろう。
製造業でそうであったように、農業においても日本人ならではのモノづくりの才能が開花し、日本の農産物は世界から注目される輸出産業となってゆく。
願わくば筆者の寿命が尽きぬうちに、それが現実とならんことを。