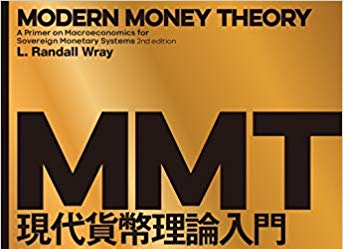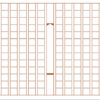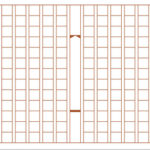目次
●「げてもの」を食べてきた
先日、池袋の中華料理屋に大勢で出かけて、いろいろなものを食べてきた。
素材の動物の名前を挙げると、牛、豚、羊、犬、鶏、アヒル、鴨、ワタリガニ、蛙、タウナギなど。
部位としては、普通の肉の他、胃、腸、舌(タン)、腎臓、それにペニスなどもあった。
普通の日本人の感覚からすると、「げてもの」ということになるだろう。
このときは男女20人ぐらいいたが、女性の中には内臓(モツ)系の食材が苦手だったり、「犬の肉は食べられない」という人もいた。
筆者も子供の頃は、内臓はグロテスクな感じがして好きでなかったし、犬が大好きだったので、
「犬の肉を食べるなんて、野蛮人のすることだ」
と思っていた。
「クジラの捕獲は絶対禁止するべきだ」
「イルカみたいに愛らしい生き物を殺すなんて」
とも思っていた。
小学生の頃の筆者は、なけなしの小遣いで自然保護雑誌を買ったりしていた、動物愛護系の子供だったのだ。
大人になった今はどうかというと、当時とは多くの点で考え方が変わっている。
それは「食べるとは何か」ということを、自分なりに考えた結果である。
食べるとは、生きることである。
それは同時に、殺すことでもある。
私たちが日常的に食べている牛や豚や鶏は、それぞれの飼育施設で大切に育てられた後、殺されて解体され、肉として売られている。
筆者を含めて都会に住むほとんどの人は、自分が食べる動物を自分の手で殺した経験がない。そんなことはまっぴらだと思っている。
筆者もわざわざ自分で牛や豚を殺しに行こうとは思わない。
が、自分が日々食べている肉が、もとは生きていて、誰かが殺してくれたからこそ、こうして食べられるのだということは、常に忘れてはいけないとも思っている。
●全ての部位を食べつくす食文化
羊とともに暮らす遊牧民の人たちは、殺した動物を頭から尻尾の先まで全て食べるという。
それは無駄は出さないという合理主義であるとともに、それ以上に、大切に育ててきた動物への供養という意識があるのではないかと、筆者は感じる。
おいしい部分だけをちょこっと食べ、残りを「いらない」と捨ててしまうのは、大切に育ててきて、食べるために殺した動物に対して、とても申し訳ないこと。「命」に対する冒涜ではないのか。
そんな意識があるのではないかと思うのだ。
先日、テレビでトルコの食文化を紹介している番組があって、そこではレストランで蒸した羊の頭が出されていた。
お客は火の通った羊の頭を手でバラして、頭蓋骨をせせったり、目玉をすすったりしている。脳は特に柔らかくて、おいしいそうである。
子供の頃であれば、筆者はその光景を見て、
「わあ、気持ち悪い」
と目を背けていたと思う。
今は、見事な食文化だと感じる。
先日行った店では、たとえば牛のペニスを炒めたものを食べた。
クセをなくすために、いろいろな香辛料や香味野菜と一緒に調理した料理である。
正直に言うと、それでもたいしておいしいとは思わなかったのだが、一頭の牛や豚を、頭の先から尻尾の先まで全て残さず、おいしく食べられるよう調理を工夫していることはよくわかった。
このあたりが中華料理のすごいところだと思う。
以前に新宿の居酒屋で豚の睾丸や子宮を食べたことがあるが、それは刺身のように生肉をスライスしてニンニク醤油を添えただけで、この時の中華料理のように、「この素材をなんとかしておいしく食べてやろう」という情熱は感じられなかった。
おそらく普通は捨てるかペットフードにしてしまっているクズ肉を安くもらってきて、「きわもの」として出しているだけなのだろう。
日本であれば捨ててしまっているような部位も、なんとか工夫を凝らして食べようとする中国の人たちの姿勢はすばらしいと思う。
そうしなければ、命ある生き物を食べるために殺したのに、その一部を無駄に捨てることになってしまうからだ。
●殺さなければ食べられない
遊牧民の人たちは、客が来ると羊を屠殺する。
大切に育ててきた羊は彼らにとって何よりも貴重な財産で、お客さまをもてなすためにそれを殺すのは、最大の歓迎の気持ちの表れなのだという。
ところが日本人の中には、自分たちのために彼らが羊を殺して解体するのを見ると、「きゃあ」と言って逃げてしまい、後になって戻ってきて、肉だけをつつく人がいるそうだ。
自分が殺さないばかりか、人が殺すことも蔑む人に、殺した生き物を食べる資格があるのだろうか?
そういう人はきっと胴体の肉は食べても、顔や頭の肉には手をつけようとしないだろう。
自分が動物の死骸を食べているのだという事実に、向き合うことが嫌だろうから。
大切に育てた生き物を自分の手で殺すというのは、悲しいことである。
普段、当たり前に鶏肉を食べている人でも、自宅で鶏を飼い、名前をつけてペットのようにかわいがって育てたら、殺して食べることには強い抵抗を感じるはずだ。
ましてかわいらしい子豚や子羊ともなれば、屠殺の経験のない人には、まず殺せないだろう。
都会の人々が食べている牛や鶏、子豚や仔牛は、どこかで誰かがそうやって大切に育て、食べる人たちに代わって殺してくれた生き物たちである。
お金を払って食べ物を買っている私たちは、そういう楽しくない作業を他人に押しつけていることに、思いをいたす義務があるのではないだろうか。
●「かわいい生き物」は食べてはいけない?
犬や猫を食べることに抗議する人たちは、それらの動物は飼って可愛がるものであって、食べるものではないと主張する。
犬や猫は「かわいい動物」なのだから、食べてはいけないと言うのである。
筆者も犬や猫は可愛いと思うし、犬については、ずっと飼っていた。
だが「牛や豚は食べ物なのだから殺してもよく、犬や猫は可愛がるものだから食べてはいけない」という考え方には、強い抵抗を感じる。
牛であれ、犬であれ、猫であれ、豚であれ、命の重さに変わりはない。
人間は神ではなく、この地球上の食物連鎖の一環をなす、生物の一種にすぎない。
その人間が自分の美醜の感覚に基づいて、ある生き物を「かわいいから殺してはいけない」と決め、別な生き物を「かわいくないから殺してもいい」と決めるのは、傲慢で幼児的な態度であると思う。
以前、やはりテレビ番組で、東北地方で食肉用の馬を飼う農家のドキュメンタリーを見たことがある。
昔ながらの日本の馬は、農耕や荷役に使われていたのだが、機械化が進んでそうした需要はなくなってしまった。
今は食肉用に細々と飼われているのみなのだ。
馬を飼う農家は、買ってきた子馬を育て、食肉用として出荷する。
取材された農家で飼っていた馬は一頭だけで、家族同様に大切に世話をされていた。
馬はとても利口な動物で、感情も豊かである。
その農家の馬は、名前をつけられて大事に育てられていて、人なつこい甘えんぼうに育っていた。
「今まで育てた馬コの中で、一等めんこい」
と農家のご主人は話していた。
だが食用として飼われている以上、いずれ別れの日がやってくる。
今日が出荷という日。
利口な馬は、回りの人間たちの雰囲気から自分の運命を悟ったのだろう。
厩(うまや)の敷き藁(わら)にうずくまってしまい、引っ張ってもなかなか立とうとしない。
それでも無理に立たされ、トラックに乗せられて、競りにかけられるために市場に運ばれていった。
なんでも食べる筆者は馬肉も好きで、ときどき食べる。
その番組を見て、
「ああ、自分はああいう馬を食べているのだな」
と実感した。
自分は食べることだけを楽しんで、育て、別れ、殺すという悲しい作業を自分以外の人たちに押しつけている。
そのことの罪を、感じないではいられなかった。
だが、だから馬肉を食べるのはやめようとは思わない。
そうした考え方は、突き詰めてゆけば「生きる」ことの否定につながると思うからだ。
農業の機械化が進み、自動車社会になった今、古来からの日本馬は、もし肉も食べられないということになれば、誰も飼う人がいなくなって、絶滅してしまうだろう。
大人になった今では、西欧諸国の人たちが韓国で犬を食べることを非難したり、中国で猫を食べることを非難したりすることには、共感できなくなってしまった。
同じように自然保護団体の人たちが、
「牛は食べてもいいが、クジラは食べてはいけない」
と言い張ることにも、今では抵抗を感じる。
筆者は鯨肉はたいして好きではないし――皮は好きであるが――なくても全然気にはならない。
それでも、過去何千年もクジラを食べてきた民族に対して、「クジラを殺すな」という、自分たちが最近思いついた考えを押しつけようとするのは、おかしいと思う。
●家畜は食べてよく、野生動物はいけない?
作家のC.W.ニコルさんの本で読んだのだと思うが、こんな話が印象に残っている。
白人の自然愛護団体が、極北地方のイヌイット(エスキモー)の人たちの狩猟をやめさせようとして、
「野生の動物を殺すのは罪深いことだ。牛や豚を食べればいい」
と教え諭そうとした。
「クジラやアザラシを殺すのは罪で、牛や豚を殺すのは罪ではないのか」
イヌイットの人が聞き返した。
「そうだ。牛や豚は食べるために飼われているのだから、殺しても罪ではない」
それを聞いたイヌイットの長老が、こんな話をした。
「あなたたちのいう牛や豚は、生まれた時から柵と小屋の中に閉じこめられ、自分が食べられるために生かされ、いずれ殺されて食べられることを知りながら飼われている。
わたしたちが狩る動物は、自然の中で生まれ、自由に原野を走り回り、殺される瞬間まで自分が死ぬことを知らずに生きている。
あなたが動物だったら、二つのうちどちらの生き方を選ぶだろうか」
そう言われた愛護団体の人は、
「おまえたちは文明を否定するのか」
と顔を赤くして怒り出したそうである。
野蛮なエスキモーを教育してやろうと思って来たのに、言うことを聞かないので、腹を立てたのだろう。
クジラの命も、牛の命も、命に違いはない。
クジラの中では小さいミンククジラからでも、1頭から牛10頭分以上の食肉がとれるという。
牛を10頭殺すのと、ミンククジラを1頭殺すのとは、どちらが命に対する罪が深いと言えるだろうか。
誰にも答えが出せるはずはない。
世界の多くの文化の中の一つにすぎない自分たちの文化に根ざした価値観を、唯一絶対だと思い込み、その価値観から外れた文化を非難したり「野蛮だ」と蔑んだりするのは、愚かな態度である。
インドのヒンドゥ教徒は牛を神聖な生き物として食べないが、もしヒンドゥ教徒がアメリカの牧場に行って、柵を全部壊して牛を逃がしてしまったら、アメリカ人たちは激怒するのではないだろうか。
自分たちの価値観に基づいた思い込みを、異なる文化を持った人々に押しつけようとするなら、押しつけられた相手が怒るのは当然のことである。
●菜食なら殺生はしていない?
「動物を殺すのは罪深いことだから」
といって、菜食主義を実践する人たちもいる。
筆者は、自分の欲望をストイックに抑え、生き方にあえて枠をはめること自体は、立派なことだと思う。
そのうち自分も試してみるかもしれない。
が、一方でその人たちが、
「野菜だけ食べていれば、殺すという罪は背負わないで済む」
と考えているのだとすれば、それは生きるということの本質から目を背けた、自己満足にすぎないとも感じる。
植物だけを食べていれば、本当に「殺生はしていない」ことになるのだろうか?
決してそんなことはない。
なぜなら植物もまた生き物であり、命ある存在だからだ。
たとえばここに、ひとかけらのニンジンがあったとする。
ニンジンのひとかけらを培養液に浸せば、やがて根や葉が出て、一本まるごとのニンジンに再生していく。
ニンジンも、また全ての植物も、細胞の一つ一つが生きているのだ。
植物には感覚がないと思っている人がいる。
決してそんなことはない。
微弱な電流を測定できる装置で木やサボテンを調べると、植物が外界に反応していることがよくわかるそうだ。
以前に自分をひどく傷つけた動物がまた近くにやってくると、植物は警戒し、全身にさざなみのような電流が感知される。
傷つけられた時にも、鋭い電流を発する。
植物は悲鳴を上げているのである。
人がニンジンのかけらを口に入れ、噛み砕く時、ニンジンは悲鳴を上げている。
「やめてくれ、助けてくれ! おれを食うな、殺さないでくれっ」
そう叫んでいるのである。
噛み砕かれた瞬間、ニンジンは、
「ぎゃああっ」
と断末魔の悲鳴を上げているのである。
ひとかけらのニンジンを構成する何千、何万という細胞が、一斉に死の苦痛を訴えているのである。
ただ人間の耳にその声が聞こえないにすぎない。
●生きるとは、殺すことである
聞こえなければいい、見えなければいいというのであれば、他人に生き物を殺させおいて、
「自分は食べるだけだから、殺しの罪は冒していない」
と考えるのと同じことだ。
人間は他の生き物を殺し、食べることによって、初めて生きていられる存在なのである。
「生きるとは食べることであり、食べるとは殺すことである」
「つまり、生きるとは、殺すことである」
その事実から目を背けてはならないと、筆者は感じる。
人間に限らない。
全ての動物は、他の生き物を食べることによって存在している。
地球上にはかつて、植物しか存在しなかった時代があった。
そのうちに増えすぎた植物によって大気中の酸素濃度が上昇しすぎ、全生命が絶滅の危機に瀕した。
そこに誕生したのが動物だった。
動物が動くのは、動けない仲間を食べるためである。
動物は、殺すために生まれたのだ。
動物が生まれ、植物を食べるようになったことで、植物は減り、地球の酸素濃度も低下して、生命の絶滅の危機は救われた。
やがて動けない仲間を食べていた動物を、さらに食べる動物(肉食動物)が現れ、動物はさまざまな種類に多様な進化を遂げていく。
同じように植物も、食べられないために巨大化し、あるいは固い皮に身を固め、あるいは水の中から地表へと逃れ、全ての地球表面を覆う数多くの種類に分化していった。
生き物を食べる生き物が現れたことで、地球は絶滅から救われ、多種多様な生命があふれる、命の楽園となっていった。
生きること、食べること、殺すこと。
それらはどれも自然の営みであり、誇ることでも恥じることでもないのだと、筆者は考えている。