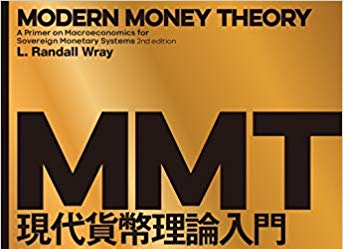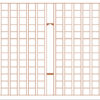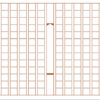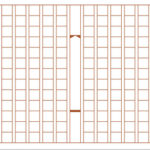目次
●物書きとしての原点
自分が物書きになった原点はどこかと振り返ると、初めて日記を書いた小学3年生に遡る。
当時、担任だった若い男の先生が作文指導に熱心で、
「先生、あのね」
で始まる日記をクラスの全員に毎日家で書かせ、次の日の朝に提出させていた。
先生はその日の下校時間までに提出された日記全部に目を通して、赤ペンで感想を書き入れて全員に返していた。
さらにその中から出来がよかった日記をいくつか集め、それをプリントにして毎週配ることもしていた。そのプリントに取り上げられた日記は国語の時間に先生が読み上げて、「ここがよかった」とよくできた点を褒めてくれるのだ。
今と違い1学年の人数が数百人、1クラスの人数も50人以上いた時代である。プリントにしてもPCはもちろんワープロもなかった頃で、先生は生徒の日記を自分で鉄筆を使ってガリ版(謄写版 とうしゃばん)に写して、ローラーでインクを塗って自分で印刷していたのだ。
あれは大変だったと思う。
先生がそれほど作文指導に熱心だったので、生徒たちはもちろん先生に褒めてほしくて、なんとか読み上げてもらおうと、毎日がんばって日記を書いていた。
あの1年間、毎日一生懸命に日記を書いて、何度か先生に読み上げてもらえる栄光にも浴し、うれしさいっぱいで、
「そうか。ボクは作文が得意なんだ!」
と思い込んだことが、筆者の今日につながっているという気がする。
もっともこの先生は作文には超熱心だった一方、算数にはまるで関心がなくて、練習問題もまともにやらず教科書を読み上げて終わり、という風だった。
おかげで筆者は小学3年を境に算数が苦手になってしまい、その後もずっと文系人生を歩むことになる。当時は今のように公文式や補習塾に通うのは一般的ではなかったので、あのときのクラスの生徒は全員国語が得意で算数が苦手になり、文系に進んだのではないかと思う。
もしあのときの先生が算数の指導に熱心で、作文に関心のない人だったら、筆者は今頃理系に進んで、全く別の人生を歩んでいたかもしれない。
良くも悪くも、幼いときの学校の先生の影響はまことに大きい。
●「書き方」を教えない学校
成人してライターになってから何度か小学校を取材する機会があり、作文指導で有名な先生のお話もうかがうことができた。
小学校の先生にとって子どもの作文指導は重要な課題の一つである。教員学校でも教え方を学ぶし、先生同士の勉強会で指導法を話し合うこともあるという。
お話をうかがって、筆者が小学3年生のときにやっていた「先生、あのね」という書き出しで日記を書くことも、定番の作文指導法の一つなのだと知った。
以下に紹介するのは、取材当時平和学園という小学校の校長を勤められていた、岡崎一実先生からうかがった作文指導法である。
岡崎先生は公立小学校で20年間教鞭を執った後に私立小学校に移った方で、今は別な小学校でやはり校長を勤めておられるようだ。
なにしろ作文指導で有名な先生のお話を文章にまとめるということで、原稿を見ていただくときは「きびしくチェックされそう」と緊張したことを覚えている。
岡崎先生は小学生の頃、作文が苦手だったという。
「日記を書け」と言われても、最初に「今日ぼくは」と書いて、そこで手が止まってしまう。あとは作文の時間の間ずっと、うんうんうなっているだけ。
「今振り返って、なぜ作文が書けなかったのかと考えると、『書き方を教わっていなかったから』ではないかと思っています」
と先生は言う。
小学校の作文では「自由に書きなさい」とか「思ったままを書きなさい」と言われて原稿用紙を渡されるのだが、それは子どもにとっては泳げないのにプールに突き落とされるも同然。泳ぎ方がわからないのに「好きに泳げ」と言われても、溺れるしかない。
岡崎先生によれば、
「自由にやらせるというと聞こえはいいのですが、どうやって書けばいいのか、具体的な書き方を教えてもらえないまま作文をさせられて、何も書けずに苦労している子供たちがたくさんいます。でも『どう書くか』をきちんと教えられれば、誰でも作文は書けるようになります」
とのことだ。
余談だが、よい先生になるには「自分も最初は苦手だった」「始めたときは何もわからなかった」という経験は大切なことだと思う。
筆者の場合、「パパに国語のことを聞いてもなんにも役に立たない」と妻から怒られている。自分が作文に苦労したとか、読解に悩んだという記憶がないので、子どもがなぜわからないのか、なぜ書けないのかよくわからず、まともに指導できないのだ。
逆に言うとなぜ今自分がちゃんと書けているのかもよくわかっていない。これは筆者にとっては大きな弱点なので、このブログでは「どうしたら書けるのか」「書けないとしたら、どこに理由があるのか」を、みなさんと一緒に考えていきたいと思っている。
●内容を「一番書きたいこと」に絞る
「作文は一般にはどうやって書くかという『書き方』と、何を書くかという『内容』に分けられます。ただこの二つは密接に関連しています」
と、先生。
内容について言うと、大事なのは「自分は何が言いたいのか」と考え、書くポイントをそこに絞り込むこと。
「行事作文」と言われる作文がある。運動会や遠足の後で、それについての作文を書くことだ。この場合、放っておくと子どもたちは、当日の朝何時に起きたとか、朝ごはんに何を食べたかといった話から始めて、その日に起きた出来事を順を追って書き続ける。
結果、肝心の行事の開始時に辿りつくまでに大量の文章を書くはめになり、本番前に疲れきってしまうのだ。
そこで先生は「一番書きたいことを一つだけ書きなさい」と指導する。
当日の朝起きて最初に何をしたなど、どうでもいい話は省く。
運動会についての作文なら、たとえば50メートル走で一番になったこととか、お昼に家族みんなでお弁当を食べたこととか、運動会の中で一番楽しかったこと、一番おもしろかったこと、あるいは一番くやしかったこと、一番感動したことを、一つだけ選んで書く。
夏休みの宿題で作文を書くことも多い。
「家族で行った旅行について書こう」と決めた場合でも、何も言わないと子どもは「一日目はどこに行き、二日目にはどこに行き」と、だらだら続けてしまう。
そうではなく、その旅行で一番印象に残った出来事にポイントを絞って書くよう指導する。
日記の場合も同様だ。
何も注意をしないでいると、その日の出来事をとりとめなく書き連ねてくる子ばかりになる。
それを防ぐため、先生の場合はあえて「日記」とは呼ばず、「ドキドキノート」「発見ノート」という呼び方をして、「一日の出来事全部ではなく、その日に一番感動したこと、一番印象に残ったことを書く」という意識づけをしていくという。
思い起こすと小3のときに筆者が先生に提出していたのも、「日記」ではなく「手紙ノート」という名前だった。「生徒から先生に出す手紙」という位置づけだったわけである。
書くことが一つだけになると、起きたことを書くだけでは一行で終わってしまう。
そうならないために組み立てを考え、起きたことの背景をきちんと描き込むよう指導する。
自分にとってなぜそれが重要だったのかを読み手にわかってもらえるよう、どこから書き出すか、何を取り上げ、何を省くかを考え、クライマックスの出来事では自分の心理や回りの人の反応まできっちり書き込むようにする。
子どもの作文に大人が期待するのは、「経験を通じた成長」である。
作文を通じて、読んだ人に「ああ、この子はこの経験を通じて、こういうことを学んだのだな」と感じてもらえるよう、出来事を通じた自分の心の変化を、読み手にわかるよう描写することがポイントだ。
ポイントを絞って要点だけに紙数を費やす。
「これは実は大人でもできていない人が多いです」
とのことだ。
それはそうだろう。子どものときに学校で作文の書き方を習わなかったら、多くの人はその後に習うことはないのだから。
●「使ってはいけない言葉」を決めて書かせる
作文の書き方は、大きく「構成」と「文章」に分かれる。
構成については、「内容」でも指摘したように、「自分は何を言いたいのか」というメインテーマを意識し、それを訴えるために必要な出来事や心理描写が何になるのかという材料を選び、それぞれをどう配置していくかという組み立てを考える。
文章については、それぞれの子どもなりの文章スタイルを身につけるために、「あえて書き方に枠をはめる」指導を行う。
「まず型を身につけさせる」という方法論だ。
たとえば「今日」「ぼくは、わたしは」「思いました」といった子どもの作文特有の言葉は、できるだけ使わないように指示する。
何も指導しないで日記を書かせると、多くの子は「今日ぼくは~して、よかったと思いました。」といった定型的な文章を書いてくる。ほとんど全員が「今日」「ぼくは、わたしは」で文章を始めるのだ。
「『じゃあ「今日」「ぼくは」を消して読んでみるよ』と言って子供たちの文章を読み上げてみると、なくても特に問題なく意味が通じることがわかります。そこで次に子供たちに『「今日」と「ぼくは」を使わないで書いてごらん』と言って、それらの言葉を禁句とした上で書かせてみると、それまでとは文章が大きく変わってきます」
みんなが使っていた言葉を禁句とすることは、それまでの文の書き方の否定となる。制限がつくことで子どもたちが書き方を工夫するようになるのだ。
「これは良い文章を書くための第一歩で、非常に効果的な方法です」
とのこと。
冒頭で紹介した日記の書き出しの言葉を「先生あのね。」と決めてしまうというやり方も「枠をはめる」方法の一つで、まず「先生」と書くことで読み手の存在をしっかり意識させ、「あのね」というフレンドリーな言葉で書き出すことによって、子どもの作文が陥りがちな「ぼくは今日~しました」という文が延々続くダメパターンを回避する狙いがある。小学校低学年でよく使うという。
「でも」という接続詞も子どもたちに禁止する言葉の一つ。
書き方の指導をされていない子どもは文章の組み立てなどは考えずに、思いついた順に文を書き並べていく。
典型が「~だった。でも~だと思った。でも~だった」というような「でも」を使ってつなぐ文章。
「でも」は順接(andの意味)にも、逆接(butの意味)にもとれるので、だらだらと文を書き足していくのに都合がよいのだ。
「~が、」も両方の意味に使え、これを使ってだらだら文を続ける人は大人にも少なくない。
文と次の文との関係が順接なのか逆接なのか、論理構成を考えずに脈絡なく文を書き続けると、何を訴えたいのかわからなくなってしまう。
「『でも』というのは本来は逆接の接続詞で、文章全体のうち後半を強調するときに用います。しかし意図してそれを仕掛けるのであればいいのですが、何も考えずに一つの作文の中で何度も使うとポイントがわからなくなってしまうので、作文ではあえて逆接の接続詞は使わず、文と文のつながりを順接に限定してしまうのです」
これも「何が一番言いたいことなのか」というポイントを絞らせるため。
「きれい」「すごい」「たくさん」といった感想に類する形容詞もできるだけ使わないようにする。
これはより具体的な描写を促すため。
「『きれい』というのは、書いた人の感想です。そうではなく、どうきれいだったのかを具体的に描写してほしいのです。『きれいな花がありました』ではなく、何色のどんな花があったのか、読んだ人が書いた人の経験を追体験できるように描写しなければ伝わりません」
子どもたちはともすれば「それを見て自分がいかに感動したか」を伝えようとするが、お母さん相手にはそれでよくても、一般の読者にはそれでは共感してもらえない。
自分の感想を抑えて具体的な描写に換えることで、書き手の見た光景が読んだ人の目に浮かび、聞いた音が読んだ人の耳にも聞こえるようになれば、読む人に強い印象を残すことができる。より多くの人に感動が伝わる文章になるのだ。
「自分の感動を押しつける文章ではなく、読み手の心に感動を残す文章が、優れた文章なのです」
●数字や音、匂い、手触りの描写を入れる
具体的な描写をするためのコツの一つは、数字を積極的に使うこと。
「たくさん」という感想的な形容詞より、「何個ぐらい」と具体的な数字を挙げるほうが、「大きい」というより「何メートルぐらい」としたほうが、書き手が目にしたものの姿が読む人に正確に伝わる。
数字を入れた描写をするためには、書くときに「数字を入れよう」と思うだけでは十分ではない。対象を見るときから視点としての「数」を意識する必要がある。
たとえばタンポポの綿毛がフワッと風に舞ったとき、数を意識していなければ「わあ、たくさんの綿毛」としか感じられない。
しかし普段から「印象的なことは作文にしなくちゃ」「作文にするときには具体的な数を入れなきゃ」という頭があると、「わあ、すてき!」と感じたとたん、「この光景を作文にしよう」「そうか、書くときは『たくさん』じゃダメなんだっけ。えっと、これって何個ぐらいあるんだろう。何十個? それとも何百個?」と考え、飛んでいる綿毛の数をざっとでもいいから見て取ろうと努力することになる。
ハチの巣を見て、「わあ、たくさんの働きバチ!」と思ったときも同じ。「これって何匹くらいいるんだろう」と考え、ハチの数を数え始める。
「作文にする」「数字を入れる」という意識を持つことで、文章を書く上で大切な観察力が高められるのだ。
具体的の描写のコツをもう一つ挙げると、「自分の耳で聞いた音をそのまま表現する」ことがある。
たとえば雨の音を「ざあざあ」という定型的な擬音語で表現するだけでは、ありきたりの文章にしかならない。
大事なのは雨の音が世の中でどう表現されているかではなく、自分にとってどう聞こえたかなのだ。
それを表現するために、「この音って、字で書くときはどう書けばいいだろう」と考えながら聞く。これは日頃何気なく聞いている音を真剣に聞き直すことにつながる。
そして聞こえたと思った音をそのまま文字にしてみる。「ぴちん、ぴちん」でも「しゃぼしゃぼ」でもいい。それをすることで子どもたちのオリジナルなセンス、表現力が磨かれていく。
「私の作文指導の根底には、『書き方に枠をはめることで、物を見る目が身につく』という考えがあります」
と岡崎先生はいう。
感想的な形容詞を禁止して具体的な描写を課すことで、子どもたちは目で見たこと、耳に聞こえたこと、匂い、手触りなどを文章化しようと、五感を働かせて対象を観察するようになる。
よい文章を書くためには、注意深く物を見、真剣に音を聞くという日頃からの努力が大切なのだ。
●会話文から始めてみる
読みやすい作文を書く上で先生のお勧めの一つが、「」のついた会話文から始めること。
会話文の場合、耳で聞いた内容をそのまま書けばいい。
目で見たことを書くためには、情報を自分の中に一度取り込んだ上で、頭を使ってそれを文章化しなければならない。これはそうした作業に慣れていない子どもにはハードルが高い。
その点、聞いたことを書くのであれば、聞こえてきた言葉をそのまま書けばいいので簡単だ。しかも読み手にとっても入り込みやすく、臨場感が出てくる。
「子供たちに『今日、ぼくは』を使わないように指導すると、自然と会話文が文章の頭に来ることが多くなります。作文の苦手な子ほどその傾向が強いようです」
と先生。
冒頭に来る会話はもちろん、印象的なものがよい。先生は子どもたちが自分が聞いて「おもしろい!」と思った会話を使うように勧めている。
会話文を使うことも、子どもたちの観察力を高めることにつながる。
それまで聞き流していた家族や友達との会話も、「これ、作文に使えないかな」と思えば聞き方が違ってくる。
「おもしろい話、ないかな」と注意して聞くようになり、「あ、これいい」と思った会話は覚えておき、文章にしようとする。それを繰り返すうちに、「おもしろい話って、こういうものなんだ」という感覚がつかめてくる。
「おもしろい言葉のやりとりを文章にしてみることは、観察力を高めるだけでなく、文章力を高める上でも役に立ちます」
とのことだ。