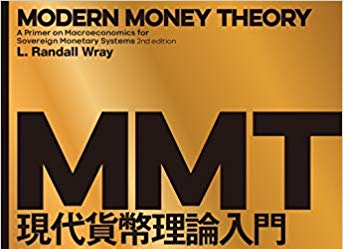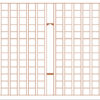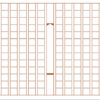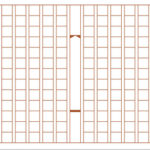『論語』は儒学の祖、孔子とその弟子たちとの問答を、孔子の死後に弟子たちがまとめた書である。
その意義と歴史的な影響の大きさについては、今さら筆者が論ずるまでもないだろう。
この『論語』の冒頭を飾る「学而篇第一」の、中でも最初の一文が、
子曰、学而時習之、不亦説乎。
有朋自遠方来、不亦楽乎。
人不知而不慍、不亦君子乎。
という有名な文章である。
書き下し文にすると、
子(し)曰(いわ)く、学びて時に之(これ)を習う、亦(また)説(よろこ)ばしからずや。
朋(とも)有り遠方より来たる、また楽しからずや。
人知らずして慍(うら)まず、また君子ならずや。
となる。
筆者が初めて読んだのは、たぶん小学生の頃だろう。
その当時、あるいは今も、この文章の意味は以下のように解釈されていた。
孔子はおっしゃった。
「学問を学んで時々それを復習する、喜ばしいことではないか。
友達が遠くから来てくれる、楽しいことではないか。
人に名を知られないからといって恨んだりしない、君子ではないか。」
筆者は最初にこれを読んだときから、
「なんだかしっくりこないな」
と首をかしげていた。
3つの行の意味がつながっておらず、何が言いたいのかよくわからない。
なぜこの文が『論語』の冒頭に置かれているのか、その意図もわからない。
同じような違和感をこの訳文に感じた人は少なくないだろう。
今の時代だけでなく、百済から『論語』が初めて日本に伝わったとされる応神天皇の時代(3世紀終わり頃)から今日までのおよそ1700年間、読んだ日本人の多くが冒頭のこの一文に座りの悪い印象を抱いたのではないか。
筆者はそれは「学問を学んで……」以下の解釈が誤訳であったためだと考えている。
そう考えるようになったのは、仕事の関係で『論語の活学』(安岡正篤 プレジデント社)という論語の解説書を読んでからことだ。
安岡正篤は大正から昭和にかけて「宰相の指導者」と謳われた思想家である。
東洋思想の研究者としても大変著名な人物だ。
『論語の活学』中で安岡は「学んで時に之を習う」の従来からの解釈に対し、「『時=ときどき』ではどうも意味がおかしい」と感じ、古今の注釈を調べた末に、「『その時代、その時勢に応じて』と解釈するのがよいだろう」と述べている(『論語の活学』P137~139)。
安岡も筆者と同じく、それまでの「学而時習之」の解釈が不自然と感じた一人だったのだ。
だが安岡が述べるように解釈すると、「その時代に応じて復習する」ということになり、これもまたなんともすっきりしない。
結局、「時」の解釈だけが問題ではないのだ。
ここはそれに続く「習」の解釈にも問題がある。
『論語の活学』を読みながら、筆者はそう感じた。
そして次の瞬間、「ああ、わかった」と思った。
「習」は象形文字で、上は鳥の羽を表し、下は口と息を表すとされる。
そのもともとの意味は「ひな鳥が羽を動かして飛び方を習う」ことで、転じて「くりかえし真似をして身につける」ことを意味するようになった。
「学習」という言葉がある。
この言葉の中では二通りの行動がセットになっている。
一つは「学ぶ」であり、これは先生が話すことを聞いたり、書物に書いてあることを読んで、頭で理解することを意味する。
もう一つが「習う」であり、これは実際に自分が手を動かして先生の真似をし、教わったことを身につけることを意味する。
漢字を覚えるときには、まず先生が黒板に字を書いてみせる。生徒たちはそれを見て「ああやって書くのだな」と頭で理解する。
それが「学」である。
次にそれを真似て自分で何度も字を書いてみて、字の書き方を身につけていく。
それが「習」である。
算数でいうなら、計算のやり方を先生が教え、それを理解するところまでが「学」で、自分で計算問題をいくつも解いて、計算のやり方を身につけることが「習」となる。
「学」と「習」がセットでなければ、学問は身につかない。
頭で理解するだけでなく、自分で実際にやってみることで、初めて教わったことが自分の血肉となるのだ。
つまり、そういうことだ。
「学而時習之」の「習」とは、「復習すること」ではない。
「孔子に学んだ学問を、自分でやってみることで真に身につける」
という意味なのである。
そう解釈した瞬間、この文章全体の意味、孔子がこの一文で言わんとしたこと、そしてこの文章が『論語』の冒頭に置かれた意図が、筆者の頭の中に鮮やかに飛び込んできた。
孔子の教えた学問とは、「治世の術」であり、「為政者の心得」である。
学校の中で実践することは決してできない。
孔子の教えを自分の手で行うためには、いずこかの国で人民を治める地位に就かなければならない。
つまり、仕官しなければならない。
孔子とその弟子たちにとって、仕官することは憧れであった。『論語』の「子罕第九」に、
子貢曰、有美玉於斯。
韞匱而藏諸、求善賈而沽諸。
子曰、沽之哉、沽之哉。
我待賈者也。
という一節がある。
「ここに美玉があります。これを匱(ひつ)におさめてしまっておきましょうか、それとも良い買い手を求めて売りましょうか」と尋ねた弟子の子貢(しこう)に向かって、孔子は「売るとも、売るとも。私は買い手を待っているんだ」と言っている。
美玉というのは孔子のことで、子貢は師匠を美しい玉にたとえて、「先生は仕官したいんですか、それとも静かに学問していたいんですか」と尋ねたわけである。
それに対して孔子は、「もちろん仕官したいさ」と前のめりに答えている。
「泰伯第八」にも、以下のような一文がある。
子曰、三年學、不至於穀、不易得也。
先生はおっしゃった。「三年学問をして俸禄に気持ちが向かわないということは、なかなかない」
俸禄とは給料のことで、「仕官したい」と願うことを意味する。
中国の人は日本人に比べて、実用主義的な考えが強いようだ。
学問のために学問するという発想はあまりなく、なんらかの利益を求めて学問する人がほとんどなのだ。
そうした考え方からすれば、「いくら学問したって、実際にそれを使えないんじゃ意味がないじゃないか」ということになる。
孔子に弟子入りしようとする者たちもみな、孔子の下で学んだという実績を作った上で、どこかの国に仕官して俸禄を得たいと考えていた。だから弟子入りして3年も経つと、「そろそろ仕官したい」と思って腰が落ち着かなくなる。「そうならない人はめったにいない」というのがこの文の意味で、行間から孔子の嘆きが伝わってくるようだ。
おそらく孔子の名声とコネにすがって官職にありつきたいと思って寄ってきた者も多かったのだろう。
実際には仕官は、めったに訪れない幸運だった。
孔子自身、若い頃は倉庫番や家畜係などをやらされていて、生まれ故郷の魯(ろ)の国でちゃんとした官位を得たのは50歳を過ぎてからのことだ。
一度、30代半ばに斉(せい)の景公(けいこう)に召し抱えてもらえそうになったのだが、そのときは晏嬰(あんえい)という宰相に反対されて叶わなかった。さぞがっかりしたことだろう。
ようやく魯で得た地位も、政治的な事情からほんの数年で辞めざる得なくなり、50代も半ばを過ぎてから弟子とともに諸国巡遊の旅に出た。
このときは晋(しん)、衛(えい)、曹(そう)、宋(そう)、鄭(てい)、陳(ちん)、蔡(さい)といった国で仕官を目指したが、どこにも拾ってもらえず、最後は故郷の魯に戻って、そこで弟子たちと学問しながら74歳で亡くなっている。
先生自身がこうなのだから、まして弟子たちが仕官するチャンスはほとんどなかった。
そもそも孔子は、諸国の高官とコネクションを作って自分や弟子を売り込んで――といった活動がおよそ苦手な人だった。
中国では古来、役人にものを頼むには相応の付け届けが必要とされていた。
逆に言えば古代中国における官職とは、その地位にあるだけで自動的に蓄財できる、利権そのものだった。
科挙以前、中国で役人になるための方法とは任官活動を行い、要所に金を渡して口添えしてもらうことだった。任官に使った金は、任官してからの付け届けで取り戻すのである。
だが孔子は自分や弟子が官職に就くために金を渡すようなことは、一切しなかっただろう。そうした「公」の誤ったあり方を正すために学問をしていたのである。
自分が散々金を使い、苦労して今の地位を得た役人たちから見れば、
「こいつら、一銭も使わないで官職に就こうっていう気か? 学者か何か知らないが、そりゃ虫がよすぎだろう」
という感覚だったに違いない。
「利より義を優先させねばならない」と説くような人だから、孔子はいくら官職が欲しくとも、そのために自分の教えを曲げるようなことは断じてしなかった。弟子たちが俸禄欲しさに「仕官、仕官」と目の色を変えている姿も、苦々しく思っていたに違いない。
一方の弟子たちは、いくら勉強してもそれを使う場がない状況に不満を募らせていたはずである。
ただ弟子の中には、そうした「先に就職ありき」の連中とは対極にある者もいた。
たとえば顔回(顔淵)である。
『論語』の「雍也篇第六」で、孔子は顔回を褒めている。
子曰、賢哉回也。
一箪食、一瓢飲、在陋巷。
人不堪其憂、回也不改其楽、賢哉回也。
先生はおっしゃった。「回は賢人だね。
弁当箱一杯のご飯とお椀一杯の水で、狭い路地の家に暮らしている。
普通の人ならその憂いに耐えられないところだが、回は学問する楽しみをやめようとはしない。回は賢人だね。」
顔回は貧乏をものともせずに学問に励む人だった。
孔子は仕官できなくても貧乏暮らしでも不満を言わないこの弟子を愛し、「未聞好学者也(顔回の他に学問が好きといえる者はいない)」とまで言っている。
そういった背景を踏まえた筆者の「学而時習之」の解釈は、以下の通りである。
「学問を修めた上で仕官し、学んだことを時勢に応じて実際にやってみることができたら、それはうれしいことだろう。
学問の世界で有名になり、同じように学問を探求する仲間たちが遠くから会いに来てくれるほどになったら、それは楽しいことだろう。
だが私は、いくらがんばっても無名のままで、それでも世の中を恨んだりしないで学問の道を究め続けようとする者こそ、本当の偉人だと思うのだ。」
「学而時習之」以下3行からなる文が主張する内容は、最後の1行の「人不知而不慍、不亦君子乎(人に知られないでも恨まない人こそ君子なのだ)」に集約されている。
文の構成を論理的に考えるなら、前の2行は最後の1行の「人不知」と対極の状況を表現しているとみるのが妥当だ。
つまり名声を得て、その結果、高い地位に就いて学んだ治世の術を実践したり、天下の学者たちが名声を慕って集まってくる様を描写しているのだ。
そして「そうなったら確かに楽しいだろう。だが」と、前2行と対比させて最後の1行を打ち出し、結論を強調している。
「時」についてはここでは「時勢に応じて」と安岡説を採ったが、「時」を「時を得て」、つまり「まさにそれをすべき時に」あるいは「チャンスを得て」と解釈することも可能と思う。
いずれにしてもこの一文で孔子は、
「学問とは仕官のためにするものではなく、
有名になるためにするものでもない。
学問それ自体に究めるべき価値があるのだ」
と論じているのだ。
それは仕官することで頭がいっぱいで、腰を据えて学問に打ち込まない弟子たちに向けた苦言である。
そう解釈することで初めて、全巻の冒頭という『論語』全体の編纂意図を強く打ち出すべき場所に「学而時習之」の一文が置かれた意味が、得心できてくる。
先に触れた顔回は、孔子より30歳ほど年下だったが、孔子を残して先に死んでしまった。
「先進第十一」に、「子哭之慟(孔子は慟哭してその死を悲しんだ)」とある。
顔回の家は貧しかったので、彼のためにちゃんとした棺を作ってやることもできなかった。
おそらく孔子は愛弟子の仕官を見届けて、
「みんなごらん。ずっと貧しい中で勉強を続けていた顔回が、最後には立派な官位を得ることができた。誰にも知られていないと思っていても、天は努力する人をちゃんと見ていてくれるのだ」
と言いたかったはずである。
顔回自身も最後はそうなると信じて励んでいたのではないか。
だが師弟の願いは叶わぬまま終わってしまった。
孔子が声を上げて泣いたのは、もしかすると最愛の弟子にさえきちんとした仕事を世話することができず、赤貧のまま死なせてしまった、師としての自分の不甲斐なさに打ちのめされていたのかもしれない。
こうして見てくると「学而時習之」以下の一文も、あるいは顔回を念頭に置いて語られた言葉ではないかと思えてくる。
筆者は天啓のようにこの解釈が閃いて以降、それが正解であることを確信するようになった。
しかし筆者の新解釈が正しいとすれば、これまで数えきれないほどの学者がそれを講じてきた『論語』の、その中でも最もよく知られた最初の一文が、過去1700年の間ずっと間違って理解されてきたことになってしまう。
日本で『論語』に関わる人たちにそれを受け入れてもらうのは、簡単なことではないだろう。
一方で1700年間見過ごされてきた『論語』の解釈の誤りが正されるとすれば、学問的に大きな意義がある。
筆者の希望は本記事を読まれたみなさんに、どのような解釈が合理的か、ご自身で判断してもらうことである。
拙文が『論語』研究の前進にわずかでも役立てば、それに過ぎる光栄はない。