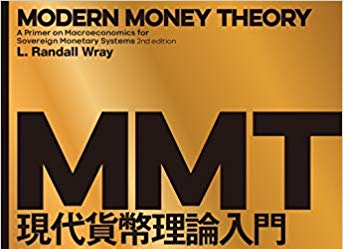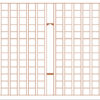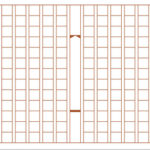目次
●ライターは自分がどうやって書いているのかわかっていない
筆者の本業はライターである。
この仕事をやっていて思うのは、ライターというのは大工などと同じで、職人なのだということ。
職人は徒弟制度で育つ。若いうちに先輩たちの働く仕事場に放り込まれ、使い走りをしながら先輩のしていることを眺めて、そのうち簡単な仕事をやらされる。うまくできないと怒鳴られたり、実害のあるような失敗をしてぶん殴られたりしながら、だんだん一人前になっていく。
事情は物書きも変わらない。
先人の書いた文章を読み、それを参考に見よう見まねで書いているうちに少しずつ上達し、やがて仕事で使ってもらえるようになる。仕事になったら締切があるので、それに追われて日々懸命に書き続ける。編集者に文句を言われて書き直し、真っ赤に文章を修正されてがっくりし、読者から「ここがおもしろかった」といったリアクションを受けて喜び、「どう書いたら気に入ってもらえるのか」と思い悩みながら書いているうちに、いつの間にか一人前扱いされるようになっていく。
だいたいみんな、そんなものだろうと思う。
でも自分がどのようにして一人前になったのか本当のところはよくわかっていないし、自分の文章の書き方を方法論として把握しているわけでもない。
だからもし人に「本の書き方を教えろ」と言われたら、「たくさん本を読んで、いいと思った文を真似して書いてみる」ぐらいしか言えない。
結局、自分が体系的に技術を習った記憶がないので、どう教えていいかもわからないのだ。大工から紙漉きまで大抵の職人が「先輩のやり方を見て覚えろ」「技は盗むものだ」などと称して弟子や後輩の教育を放棄しているのと同じである。
筆者も以前、「本を書きたいというみなさんにやり方を教えてあげてほしい」などと頼まれて、はたと困ったことがある。
そう言われて初めて、自分がどうやって書いているのか自分自身がまるでわかっていないことに気がついた。
あわてて世の中の文章指南の本を端から読んでみたが、なかなかピンとくるものがない。
結局そのときは、読んだ本の中から使えそうな部分を引っ張り出してつなぎ合わせ、もっともらしい解説をしてお茶を濁したのだが、それを聞いてそれまで本が書けなかった人が書けるようになったなどとは、いくらうぬぼれの強い筆者でもさすがに思えなかった。
まあ講演を頼んできた人も講演を受けた人も、一度話を聞いただけで本が書けるようになるとは思っていなかっただろうが。
しかし、これではいかにも情けない。
以来、「どうやったら初心者でも本一冊が書けるようになるのか」は筆者にとっての研究課題になった。
本ブログでも「本の書き方」をメインテーマの一つとして、折に触れて文章の書き方や構成のやり方について考えてみたいと思う。
記念すべき第一回として、まず「話すように書く」技術について考えてみる。
●本を書くことはプレゼンに似ている
普通の人にとって、「話すこと」はそう難しくない。大抵の人は毎日誰かと話している。
一方、普通の人にとって「書くこと」は面倒だ。手を使って文字を書くという物理的行為自体が面倒だし、ちゃんとした文章にしようと思うといろいろ頭を使わねばならず、さらに骨が折れる。
話す方がずっと楽だ。だから本作りにライターが使われるのである。
書き方の指南本などで、「話すように書きなさい」と書かれているのを目にすることがある。
なるほど話すように書けたら楽だろう。読むほうも読みやすいだろう。
ご趣旨はもっともだが、ではそう言っている本人が「どうやったら話すように書けようになるのか」についてちゃんと説明してくれているのかというと、少なくとも筆者の読んだ限りでは誰もしていなかった。筆者は「話すように書く」方法についてきちんと説明している本をまだ見たことがない。
実は「話す」といっても、家族や知り合いと日常的な会話を交わすのと、本にできるような大量の情報を首尾一貫した形で話すのとは、まるで違う作業である。
みなさんも学校の発表や会社のプレゼンなどで、聴衆を相手に話す機会があるだろう。そういうときの「話す」は普段の会話で話すこととは違う。発表する内容を準備するのは死ぬほど面倒だし、「きちんと話さなければ」と思うと発声から身振り手振り、言葉の選び方まで気を使わなくてはならず、これもまた嫌になるくらい面倒だ。
だから世の中には上手なプレゼンのコツを説く本がたくさん出ている。
「まとまった内容を人に伝える」という意味では、本を書くこととプレゼンすることは共通している。
だからプレゼンのコツは本を書くコツとも一部、共通している。もちろん話すことと書くことの違いはあるし、1時間程度が多いプレゼンと本1冊とではボリュームも違うから、全く同じというわけにはいかない。しかし上手なプレゼンをする上での心得は、本を書く上でも参考になることが多い。
●プレゼンのコツは聞き手を意識すること
その一つが「聴衆を意識すること」だ。
これは本の場合は「読者を意識すること」となる。
「当たり前だ」って?
いやいや、決してそうではない。
日常の会話では相手があって話している。一言しゃべるごとに相手から反応があり、それを聞いて今度は自分がそれに反応することで、会話が続いていく。
プレゼンではそうではない。
聴衆は不特定多数。そのうちの決まった誰かに話しているわけではない。話すのはこちらだけで、相手は――よほど会場全体が盛り上がったときは別として――いちいち返事を返してはこない。
そうなると慣れていない話し手は、つい聴衆の反応を確認せずに、前もって考えていた通りに話を進めてしまう。
これがプレゼン失敗の大きな原因だ。話を聞く側の聴衆はそういう話し手の態度を見て無視された気分になり、すっかり白けてしまう。
話のうまい人はそこが違う。
話しながら常に聴衆の反応を感じ取り、聞き手の注意力が途切れそうになるとみるや話を切って間を置いたり、強調したいポイントを話した後に「いかがかな?」という表情で聴衆を見回したり。事前に用意した台本には縛られずに、受けそうな方、受けそうな方に話を展開していき、受けを取ったら、笑いや喝采が静まったタイミングでまた本題に話を戻していく人もいる。会場の反応に合わせた緩急自在のリズムとテンポで聴衆の心をつかみ、話を盛り上げていくのだ。
前に、話がおもしろいことで出版業界ではよく知られている、東証上場企業の連続増収増益記録を今も更新中のさる有名企業の創業会長さんの講演を聞く機会があった。この人などは自分が話すというより目の前の相手とコミュニケーションしているような感じだった。
この会長さんはキャラが立っているということで、現役の偉いさんなのにテレビのバラエティ番組などにも呼ばれて出演しているのだが、そういうときは「台本を渡されても、見ない」と言っておられた。
仕事が忙しくて読む時間がないのかと思うとそうではなくて、「いや、見ても覚えられないから」とのこと。なまじ「台本通りにしゃべらなきゃ」などと思うと、頭が真っ白になって言葉が止まってしまうのだという。
ではどうするかというと、最初の一言だけは台本通りに言って、後はアドリブでリアクションしているそうだ。
適当なことを言ってボケていれば、そこはテレビのバラエティ、プロの芸人たちがうまいこと突っ込んで笑いを取ってくれるので、自分は一緒になって、「いや、あはは」などと笑いながら頭を掻いていればいい。それでつつがなく番組は進行していく。
事前に頭で考えた台本より、アドリブでの相手との当意即妙のやりとりのほうがはるかに場が盛り上がるのだ。
こうしたプレゼンの心得は、文章を書く場合にも大いに役に立つ。
もちろん文章を書くときには読み手はその場にいない。従って一行書くごとに読者の顔色を伺って反応を確かめるなどということはできない。
しかし、一行書くごとに読者の反応を想像することはできる。
実はそれこそが「読者を意識する」ということなのだ。そしてそれが「話すように書く」コツでもある。
●自分で自分に「つっこみ」
ただ「読者の反応を想像する」というだけでは漠然としすぎて、何をしていいのかわからないと思う。
筆者がお勧めするのは、「一行書くごとに読者の『つっこみ』が入ると想像し、『自分ならどうつっこむか』を考える」という方法である。
実はこの方法はあるとき筆者が自分で思いついたのだが、調べてみたらプレゼンの練習方法としてはポピュラーなもののようで、プレゼンの教科書にも書かれている。自分が一番最初に思いついたと思っていた筆者は、それを知ってがっかりしてしまった。
プレゼンの場合は、たとえばこんな風に使う。
まずは舞台に出ていき、話を始めるために口を開く直前。
演台に立ったあなたの顔を見て聴衆が思い浮かべるのは、
「こいつ何者だ?」
という疑問=つっこみである。
もちろんあなたが有名人なら別だ。聴衆がみなあなたを知っていて、あなたの登場を待ちわびているようなら、つっこみなど気にせずに、
「みなさんこんばんわ! お待ちかねの○○です! (大歓声) ああ、どうもどうも。(余裕をかまして)いやいや来る途中の道が渋滞しちゃってね。なんとかぎりぎり会場に辿りつきました。ああいうのを見ると日本も景気いいのかなって思いますよ。それはともかく、こうして今夜みなさんにお会いできて、ぼくはうれしいです!」
と期待に応えてやればよい。
しかし大部分のみなさんは、少なくとも初めて講演するときには、そんなにメジャーな人間ではないはずだ。
その場合は聴衆の疑問=つっこみに応え、自分が何者か説明せねばならない。でもってここは聴衆をがっかりさせてテンションを下げないよう、自己紹介を通じて自分がいかにこの講演のスピーカーにふさわしく、聴衆の期待に応えそれを上回るレベルの講演をこれから全力でぶちかます予定であって、その用意が万全であることをアピールしなければならない。
「みなさんこんばんわ。わたしがご紹介にあずかりました○○です。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございました! わたしは本日お話しする予定の××についてすでにうん十年のキャリアを積み重ねており、これまでの活動を通じて多くの感謝の声をいただいております。みなさんご期待ください! 僭越ながらこのわたしが今日ここへ来た以上、みなさんの時間をムダはさせませんよ!」
というような具合だ。
あなたが聴衆の疑問に応えて自己紹介すると、聴衆は次にこんな風に思い浮かべる。
「ほう、なるほど。おまえが何者であるかはわかった。じゃ、それで、おまえはオレに何を教えてくれるんだ? 入場料2500円も払ったんだ、もとは取らせてくれるんだろうな」
これもつっこみだ。
あなたはこのつっこみに対して、自分がこれから話すべき内容を一言で紹介し、いかにその効用が大きいかを訴えていく。
――と、プレゼンの場合はこんな具合に一言しゃべるごとに聴衆のつっこみを予想し、次の一言がそのつっこみに対する適切なリアクションとなるよう話を展開していく。
それによって聴衆の一人ひとりは、話し手がまさに自分に向かって話してくれていると感じ、身を乗り出して聞き入ってくれるというわけである。
●一文ごとに自分でつっこみを考える
本を書く場合も、基本はプレゼンと同じように展開していく。
前に「SRS体験記 後編」という記事で、「読むとはなんぞや」という話をした。
文章を書き、それを読むというとき、書き手の目の前には読み手がいない。だからつい、書くことが一方的な情報発信であるように感じてしまう。だが実際には書くことはコミュニケーションそのものである。読み手は一つの文を読むたびに何かしらのリアクションを心に浮かべている。書き手は読み手との間にコミュニケーションが成立するよう、読み手のリアクションを想像し、次の文章でそれに応えるようにする。
たとえば冒頭に「我輩は猫である。」という文章を書いたとする。
読者の反応は「はあ? 何言ってんだこいつ? 猫ってなんの猫だ?」というところか。
それに対して書き手は「名前はまだない。」と続ける。
すると読者は「名前がない? ああ、野良猫ってことか。なるほど。で?」と反応する。
そこで書き手は、その猫が置かれている状況について、縷縷(るる)説明していくわけである。
下手な書き手だと、最初の一行を飛ばしていきなり野良猫の置かれた状況の説明から入ったりする。それでは読者との間にコミュニケーションが生まれない。尋ねてもいないのに長たらしい猫の説明を押しつけられた読者は、「なんでおれがこんな話を聞かせられなきゃいけないんだ?」と不機嫌になってしまう。
同じように、「筆者の本業はライターである。」という文章を書いたとする。
読者の反応は、「フン、それが?」というところ。言い換えれば「何が言いたいんだ、こいつは」ということだ。
書き手は「この仕事をやっていて思うのは、ライターというのは大工などと同じで、職人なのだということ。」
と続ける。
読者は「職人? 大工と同じ? どういうことだよ」とつっこむ。
それに対して書き手は、
「職人は徒弟制度で育つ。若いうちに先輩たちの働く仕事場に放り込まれ……」云々(うんぬん)と、「職人とはなんぞや」という説明をひとくさりした後、「ライターという職業もそれに似たところがある」という趣旨の文を続ける。
そこまで来ると読者は、「あー、要はそれが言いたかったわけね」と肩をすくめるはずだ。
最初の文章を読んで抱いた疑問が続いての文章を読んでも解消されないと、読者はたちまちイライラしてくる。
書き手が読み手の心に浮かんだ疑問や感想にいつまでも応えようとしないと、つまり読み手が読み進めていっても最初の疑問が解消されないと、読み手は「こいつ、オレがどう感じてるとか気にしてないんじゃね?」と白けてくる。そのうち我慢できなくなって、「だめだ、こいつは」と書き手に見切りをつけ、手にした本を放り出してしまう。
これは会話だったら当然のことだ。
相手の言葉に対してこちらが疑問をぶつけているのに相手に無視されたら、誰だってイラッとする。相手がこちらのいらだちに気づきもしないでその後も手前勝手な持論をぶち続けていたら、そのうちキレてしまって、「てめー、壁とでも話してやがれ」と言い捨ててどこかに行ってしまうだろう。
そう、文章も同じ。「コミュニケーションである」という点で実は会話と文章は同じなのだ。
●頭の中のメモリをできるだけ解放してやる
人間の頭はあまりワーキング・メモリが大きくない。特に言語用のメモリは小さい。これは言語が、もともと音声で伝えられてきたことに起因している。
音声情報は視覚情報に比べて情報量が少ないため、人間の脳の中でもメモリの割り当てが少ないのだ。
このため人は、読んだ文章をいくつも同時に、長いこと記憶していることができない。
ところがある文章に対する疑問を抱き続けるためには、その文章を覚えていなくてならない。これは脳のメモリを大きく占拠する、精神的負荷の大きな行為だ。
不足気味のメモリをできるだけ早く解放してやる、つまり読者の抱く疑問をいつまでも疑問のままで放置しないで、その都度その都度すばやく解消させつつ読み進めるようにしてあげなければ、読者のいらだちは募るばかりだ。
評論家の清水幾太郎は「文章を書くとは、問題に答えることである」と述べた。
筆者流に言うなら、「読者のつっこみに応えるよう書いてゆく」こと。それでなくとも不足気味の脳のメモリをできるだけ早く解放してあげるよう書き進めるのが、文章の基本ではないかと思う。
「文章を読む」という行為は、単に頭の中に情報を入力することだけではない。
文章を読むと、その文章の内容に対して、読者は反射的にさまざまな感想を抱く。
多くの場合、「本当か?」「なぜそれが言える」という疑問(つっこみ)が心に生じる。
この心の声にできるだけ早く応えてあげないと、読者の頭の中にはいつまでも疑問が残り、それにより続く文章を読んで理解しようとする意欲がなくなってしまう。
一つの疑問に答えると、それを読んだ読者の脳内にはすぐに次の疑問が湧いてくる。それにもすぐ応えてやる必要がある。
このようにして、「何か一文を書く→すかさず読者のつっこみが入る」ことを前提に、「読者からのつっこみを想像し、それに応えるよう次の文を書く→すぐ次のつっこみが入る」という形で文章を書き進めていく。
その意味では基本的に「著者はボケ、読者はつっこみ」ということになる。
書き手の想像するつっこみやそれへの対応がうまく読者の反応と一致すると、読者にとっては文章を読みながら抱いた疑問や感想に次々と的確な答が示され続けることになる。これは快感だ。
誰かと話をしていて、「おー、この人とは話が合うな」と感じるのと同じように、「いいな、この本。なんかオレのために書いてあるみたい」と感じ、気持ちよく読み進んでいける。
この「一人つっこみ」は話すように書くこと、つまり書き手と読み手の間で会話を続けるように文章を続けていく上で、とても有用なテクニックであると筆者は感じている。
理想は想定している読者層に合わせてリアクション(つっこみ)を想像すること。ただ実際はプロの書き手でもなかなか難しい。
というのも書く側はつい自分の基準で読者の反応を考えてしまいがちだからだ。
たとえば文中に読者が知らない難しい言葉が出てきて、しかし書き手がそれに気がつかずなんの説明も入れなかったりすると、それだけで読者は違和感を感じ、「んだよ」とむくれてしまう。
読者は自分の疑問に答えてもらえないと拗(す)ねてしまうのだ。
以前ゲームの脚本で「DV」という言葉を使ったときは、セリフを読んだ若手の女性声優から「これ、どうゆう意味ですか?」と訊かれてしまった。
「えーと、ドメスティック・バイオレンスっていって、家庭内暴力のことですが」
「聞いたことないなー。普通使いませんよ、そんな言葉」
「そ、そう? 新聞とかには出てると思うけど」(←言い訳モード)
「新聞取ってないし」
「……なるほど」
力強く言い切られてしまった。
そう、今どきの若いコは新聞なんぞ読まないのである。
こういうつっこみが、人から言われるのではなくて書きながら自分の頭の中に浮かんでくれば最高なのだが、ついつい自分中心になって読者を白けさせてしまう。それはたぶん筆者だけではないだろう。
仕事でライターしていてもできないくらいだから、一般の人に「読者になりきって自分の文章につっこみを入れろ」なんて言っても、無理な相談というもの。
とりあえず「もう一人の自分」でかまわないので、自分の書いた文章に自分でつっこみを入れてみるといい。で、それに応えて次の文章を書き、それへのつっこみを想像して、またそれに応えて書き……
とやっているうちに、それなりの分量が書けてくるはずだ。
書いたものを読み返してみてテンポよく読み進めたら、まずは「話すように書く」の合格ライン到達といえる。