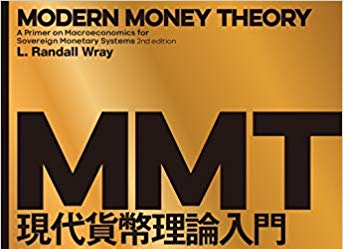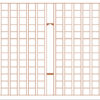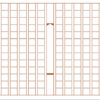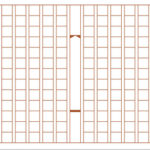目次
●語順で言葉のつながりをわかりやすくする
『日本語の作文技術』という本がある。
朝日新聞の記者だった本多勝一氏が1976年に上梓した、文章本の古典の一つだ。
先の「本の書き方 読みやすい文章とは」では、「わかりやすい文章の基本は一文一義」という、作文の世界における主流というべき主張を紹介したが、この本で本多氏は「正しい日本語の技術があれば、長文でもわかりやすく書ける」と主張している。
そのためには、
「日本語では助詞(てにをは)は文章全体の構造を決めているので、助詞の使い方に注意を払い、文章の論理構造、とりわけ修飾される言葉とされる言葉のつながりを明らかにする」
ことが重要とのことだ。
一例としてこんな文章を挙げている。
例1 私は小林が中村が鈴木が死んだ現場にいたと証言したのかと思った。
はい、わかりませんね、これ。
著者はこの文を、次のように直してみせる。
→2 鈴木が死んだ現場に中村がいたと小林が証言したのかと私は思った。
この直しのポイントは、
「修飾される言葉とされる言葉が『入れ子』になっている状態を、単語の順番を入れ替えることで整理した」
ことだという。
つまり、
「私は+思った」
「小林が+証言した」
「中村が+現場にいた」
「鈴木が+死んだ」
という「主語+述語」の関係がはっきりわかるように、言葉の順番を直したわけだ。
「位置を変えるという操作だけでかなりわかりやすくなる」
と、著者はいうのだが……
わかりやすい……かな。これが?
高名な先生に向かってこんなことを言うのはなんだが……もし筆者がこんな文章を書いて編集に出したら、まず間違いなくつっかえされてしまうだろう。
筆者だったらとりあえず「」を使ってわかりやすくする。
→3 私は小林が「鈴木が死んだ現場に中村がいた」と証言したのかと思った。
地の文に「」をまぜて使うのは、記事を書くときの常套手段。文の区切りがわかりやすくなるし、単調さの回避にも有効だ。
その代わり何も工夫しないと「~と言った。」が繰り返し出てきて鼻についてしまうので、前の記事でも触れたように、「言った」を「述べた」とか「説明した」とか「打ち明けた」とか、この場合のように「証言した」とか、いろいろな言葉で置き換えていく。
上の文については「」を使ったことでかなりマシになったと思うが、これでもまだ読みにくい。
ここは文意に応じて、もっと噛み砕いたほうがいい。
こんな感じだ。
→4 私は小林が「鈴木が死んだ現場に中村がいた」と証言したのかと思ったのだが、彼の証言はそういう内容ではなかったようだ。
→5 「鈴木が死んだ現場に中村がいた」という証言があったのだが、私はそれは小林の証言だとばかり思っていた。
最初の文章が読みにくいと感じるのは、文の構造がはっきりしていないということももちろんあるのだが、それ以上に、書き手が何を言いたい(訴えたい)のかはっきりしない、ということが大きい。
最後の2つの文章のように書き換えることで、文章は長くなるし、嫌いな人の多い接続詞「が」を使うことになるけれども、直す前よりはずっと読みやすくなる。
それは読み手が「あ、こいつ、小林っていうやつの証言内容が意外だったのね」または「あ、こいつ、証言したのが小林じゃなかったのが意外だったのね」と、「そっか、そういうことか」と腹落ちできるようになるからだ。
一方、直す前の文章では、書き手が言いたいのが上の2つのどちらであるかがはっきりしていない。だから「何が言いたいのかよくわからない」「読みにくい」と感じてしまう。
読みやすい文章というのは、「書き手が何を言いたいのかすぐわかる」文章のこと。
それを実現するには文法的な工夫だけでは足りないのだ。
●修飾の順序の原則
もっともここで著者の本多氏が言わんとしたのは、「長い文章を書くときは語順に注意しないとだめだよ」ということであって、その意味で筆者がやっているのは単なる揚げ足取りである。
本多氏はこの『日本語の作文技術』の中で、「修飾の順序の4つの原則」を挙げている。
それは、
1 節を先に、句を後に
2 長い修飾語を前に、短い修飾語を後に
3 大状況から小状況へ 重大なものから重大でないものへ
4 親和度(言葉と言葉のなじみ具合)の強弱により、配置を変える
というもの。
まず「節を先に、句を後に」を見てみよう。
この場合、節は1個以上の述語を含む複文、句は述語を含まない文節を意味する。
「節を先に、句を後に」の原則に則って、「白い紙」「横線の引かれた紙」「厚手の紙」の三つを1文にしてみると、
「横線の引かれた紙」(節)を前に、「白い紙」「厚手の紙」(句)を後に、という形となる。
○ 横線の引かれた厚手の白い紙
× 厚手の横線の引かれた白い紙
なるほど。確かに「○」のほうがわかりやすい。
次に「長い修飾語を前に、短い修飾語を後に」はどうか。
著者は、
「『AがBをCに紹介した』という文では、ABCをどの順番に入れ替えても(合計6パターン)わかりやすさは同じ。ところが『私が震えるほど大嫌いなB』『私の親友のC』という修飾語をつけた場合は、同じではない」
と指摘する。
ここで「長い修飾語を前に、短い修飾語を後に」の原則に従うと、
○ 私が震えるほど大嫌いなBを私の親友のCにAが紹介した
× Aが私が震えるほど大嫌いなBを私の親友のCに紹介した
となる。
こちらは1の「節を先に、句を後に」ほどの違いはない感じだが、それでもどちらかというと「○」のほうがわかりやい。
第三、「大状況から小状況へ 重大なものから重大でないものへ」。
ここでは、
「太郎さんがけがをした」「薬指にけがをした」「ナイフでけがをした」
という三つの文を1つにしてみる。
(「一つにしないでそのまま分けておくほうが、一文一義になって読みやすい」というのはナシね)
もっとも重要=大状況なのは、「『太郎さんが』けがをした」という事実なので、「大状況から小状況へ」という原則に従い、
○ 太郎さんがナイフで薬指にけがをした。
となる。
まあ筆者的には「大状況」云々以前に、「主語を先にするのが原則」と言いたくなってしまうが、この順番自体にはみな文句ないだろう。
最後の第四は、「親和度(言葉と言葉のなじみ具合)の強弱により、配置を変える」。
例として、
× 初夏のみどりがもえる夕日に照り映えた。
という文を挙げている。
この場合「みどり」は「もえる」と親和度が高いため、つい「みどりがもえる」と読んでしまう。そこで誤解の余地がなくなるように、
○ もえる夕日に初夏のみどりが照り映えた。
と配置を変えてやると読みやすくなる。
これも後のほうが読みやすいことに文句はなさそうだ。
もっとも筆者なら読点「、」を入れて、
初夏のみどりが、もえる夕日に照り映えた。
とするか、「もえる」を「燃える」にして、
初夏のみどりが燃える夕日に照り映えた。
で済ましてしまう。
著書が指摘している「みどり」と「もえる」の親和性というのは、「緑」と「萌える」の親和性のことなので、「もえる」を「燃える」としたとたん、誤解の余地はほぼなくなるからだ。
(失礼、これも揚げ足取り)
以上の4原則はいずれも「言われてみれば……なるほど」ではないかと思う。
「装飾語の置き方の順番」などという細かい話は、文章を書き慣れた人はおそらくあまり意識したりせず、「なんとなく」でやっていることが多いと思う。筆者もそうだ。
多くの人が無意識にやっていた装飾語の配置法について、「こういう原則が考えられる」と言語化したのは、たぶん本多氏が初めてだろう。
反対意見があるとしても、とにかく議論の叩き台を作ったことは高く評価されるべきである。
●主語と述語、修飾語と被修飾語を近づける
やはり元新聞記者でジャーナリストの小笠原信之氏が『文章力が身につく本』という著書を出している。そこに上の「修飾の順序の4つの原則」を補助するような指摘があったので、紹介しておこう。
一つは「主語と述語を近づける」という原則。
例 証人は容疑者が店員が外の騒音に気を取られている最中に万引きしたのを見たと言った。
と、先程の例1と似た文章を挙げて、これを「3つの文が3層に重なっている『入れ子文』としている。
入れ子というのはつまり、
「証人は見たと言った」
「容疑者が万引きした」
「店員が外の騒音に気を取られている」
の三つの「主語+述語」が一つの文章の中にあって、しかもそれが、
証人は「容疑者が(店員が外の騒音に気を取られている最中に)万引きしたのを」見たと言った。
というように、「大きなマトリョーシカ人形の中に中くらいの人形が入り、その中くらいの人形の中に小さな人形がはいる」という形になっているということ。
これを著者は、
→ 店員が外の騒音に気を取られている最中に容疑者が万引きしたのを証人は見たと言った。
と直している。
本多氏も同様に直したのだが、そのときは直す際の原則については何も述べていなかった。
小笠原氏はここでの直し方について、「主語と述語を近づけ、主語+述語』の3つの文が順番に登場する形にする」という原則を述べている。
これも「なるほど」である。
ただまあ……
こんな文章があったら、筆者なら迷わず2文に分けて、
証人は「容疑者が万引きしたのを見た」と言った。
証人によれば、「そのとき店員は外の騒音に気を取られている最中だった」とのことである。
とでもしてしまうところだ。
分けたほうが明らかに読みやすい。
単に読みやすいだけでなく、「万引きしたのを見た」が確定的な事実であるのに対し、「店員が外の騒音に気を取られている」には証人の憶測が混ざっているので、一まとめにしないほうがいいという判断もある。
が、どうしても一文にまとめたいという場合は、確かに著者が言うように「証人+見たと言った」「店員+気を取られている」、「容疑者+万引きした」というように、主語と述語をそれぞれ近づけてセットにしてやったほうが、多少は読みやすくなるだろう。
小笠原氏はもう一つ、「副詞と動詞、形容詞と名詞を近づける」という原則も提唱している。
例 きちんと読みやすいように書こう
→ 読みやすいようにきちんと書こう
例 貴重な江戸時代の神保町で見つけた地図
→ 神保町で見つけた江戸時代の貴重な地図
上では「きちんと」という副詞と「書こう」という動詞、「貴重な」という形容詞と「地図」という名詞を近づけている。
このように動詞とそれを修飾する副詞、名詞とそれを修飾する形容詞をできるだけ近づけてセットにしてやることで、「修飾-被修飾」の関係をはっきりさせ、紛れをなくさせているわけだ。
これも「なるほど」である。これには筆者も異論はない。
「一文一義」は、「まぎれ(意味を取り違えること)の少ない文」を書く上での原則である。
ただなんでも細切れにするというのは、小学生の作文指導ではよくても、大人の文章では味気ない。
適度に長文を入れてリズムを変えつつ、かつわかりにくくならないよう言葉の配置に気を配る。
それが世の中で「文章がうまい」と言われている人たちの工夫であるようだ。