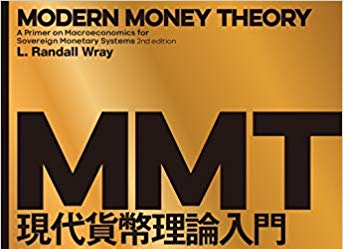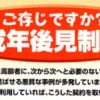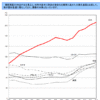目次
●男女7歳にして席を同じゅうせず
子どもは集団をつくる際、年齢や性別が自分と近い者のグループに入りたがる。
「三歳児ですら、自分が女の子か男の子かを自覚し、一般的に同性と遊びたがる。五歳にもなると、小集団を形成して遊ぶようになるが、その集団にはほとんどの場合、同性しか含まれない」
それというのも男の子はいつも自分のやり方を押し通すので、もし女の子が男の子と遊ぼうとすると、男の子のルールで遊ばなければいけなくなるからだ。
「男の子の集団ではリーダーがいて、他の子どもに指示を与える。男の子はそれぞれ上位をめぐって競い合う。自分が負けだと認めることになるので、人に指示を仰ぐことはしない」
一方、女子のグループではお互いを尊重しあう。
「女の子は友人をこき使うのを嫌う。彼女たちは協調性と交替に何かをすることを重んじる」
「女の子は男の子のように、相手に対して敵対心をむき出したりはしない。敵に仕返しをするのなら、自分の友人にも相手に対する敵対心を抱かせるようにする」
そのようなわけで、女の子は女の子同士で遊ぶようになる。
「女の子の多くはかなり早い時期に、自分が男の子に対してあまり影響力がないことを悟る。そのため男の子が女の子を避けはじめる前に、女の子の方が男の子を避けはじめる」
「男女7歳にして席を同じゅうせず」なのである。
こうして男の子と女の子それぞれが別の集団を作ることで、はっきりした男女の違いが生まれる。
集団の中で子どもたちは、「集団の他のメンバーのようになりたい、そして別集団とは一線を画したいと願う」ので、自分から進んで仲間に合わせ、他のグループとは差別化しようとするからだ。
結果、「仲間たちと一緒のとき、男の子は強靭さを、女の子はやさしさを誇示」し、「子どもたちはますます同性の仲間たちに似るようになる」。
ハリスの職場の同僚の4歳の娘さんは、それまでお気に入りだったスニーカーを「オトコの靴」と友達から言われて履かなくなり、別のパパは幼い娘がオモチャのステゴサウルスに向かって「銃で遊べるのは男の子だけなの」と言っているのを耳にした。
こうして男の子は男の子らしく、女の子は女の子らしくなってゆくのだ。
男女のグループでは「誰が偉いか」という価値観も違う。
仲間に認められるのに必要な資質として、「男の子の集団であれば、世界ほぼ全域で、それは体格的に大きく強靭であること、他人を自分の言いなりにさせることができることを意味する。女の子であれば世界ほぼ全域で、容姿端麗であること、やさしいこと、人から好かれることなどを意味する」。
他人を自分の言いなりにさせるとは、つまりリーダーとして他のメンバーに命令するということ。
男の子のグループでは強くてえばっているやつがリーダーに納まる。
ハリスによれば、女の子のグループでは美人で人に好かれる子がリーダーになるらしい。
男子校出身の筆者は、女子のグループがどんなものか全くわからないのだが、ハリスは自分が女性だけに描写が具体的だ。
「上層部にいる女子にはたとえばいつ冬服から夏服に切り替えるかといったことを決定する権限が与えられている。もし下層部に属する女子たちが上層部の女子たちが既に半袖に切替えているのにまだセーターを着て登校しようものなら、それは気恥ずかしいみっともないこととみなされる。上層部より早く夏服に切り替えることも同様にばつが悪い。
これを避けたければ、まったく同じ日に切り替えるしかない。そのためには相当な時間を受話器片手に情報収集のために費やさねばならない」
ということになる。
似たような話は日本でも耳にするから、世界のどこでも同じなのだろう。
このように女子グループのメンバーは他のみんなと同調するのに大わらわなわけだが、リーダーの地位も男子の場合ほど安泰ではない。
というのも「女の子の集団でのリーダー的存在には危険がひそんでいる。生意気だ高慢だと言われるようになるかもしれないからだ」。
どうやら昨日までリーダーだった子が、「生意気だ」ということになっていきなり村八分にされたりすることもあるらしい。
女の子の集団で生きていくのは大変そうだ。
思春期前の子どもたちの間では、男女の間に反目がある。
「異性に対する敵対心は保育園の頃から見られ、小学校では学年を増すごとに強くなっていく」
「ある社会学者が多人種の通う小学校で一定期間観察したところ、昼食時に自分と異なる人種の子どもの隣に座ることはまれで、ましてや異性の隣に座る子は実際誰もいなかった」。
こうした男女別のグループは、思春期になると崩れ始める。
ハリスによれば、思春期には運動系の集団、頭脳系の集団、非行集団など男女両方が含まれる集団が多くなるが、「それらはすべて男の子の基準で動いている。男女が混在する集団では、話すのも笑わせるのも男性の方で、女性は聞き手や笑い手に徹する場合が多い」という。
「男の子が支配している集団の中で、十代の女の子がなんらかの地位に就くためには、男の子が重んじる何かに長けているか、器量がよくなくてはならない。いずれの取り柄にも欠けていれば、彼女はまず無視されてしまうだろう。努力すればどうにかなるというものではない。子どもの頃は女の子の集団でかなり高い位置にいたかもしれないが、器量が悪ければそれは何の役にも立たないのだ」。
そのため一般に女の子の自尊心は、思春期の初めに急降下するという。
「そんなことなら男のグループなんかに入らずに、ずっと女だけのグループを作っていればいいじゃないか」
と筆者などは思うのだが。
●娘を医者にしたいなら女子校がよい
研究によれば、男の子は周りに女の子がいてもしなくても、変わらずに男の子らしくふるまう。
ところが女の子は周りに男の子がいる場合といない場合で、態度や行動が大きく変わる。
男の子がいない間はさほど女っぽくはふるまわない。ところが周りの男の子がいると急に「女の子らしく」ふるまうようになるのだ。
シカゴの私立校に通う中流階級のアフリカ系アメリカ人と、アリゾナ州の居留地のインディアンのホピ族の、それぞれ12歳の女の子たちを観察した報告がある。
「男の子がいないときには、女の子たちは両集団とも真剣にドッジボールに興じた。
ところが男の子たちがゲームに参加したとたん、女の子の遊び方が劇的に変わったのだ。それまではすぐにでも動けるような体勢で準備していたのが、ホピ族の女の子は足を交差させ、腕を組み、恥ずかしそうにして、とても運動などできないかのように立ちすくんでいた。アフリカ系アメリカ人の女の子の方は、ぺちゃくちゃとおしゃべりをはじめ、他の選手をからかった」
こうした女の子の態度の変化は本人も無意識のうちに起きる。この調査では女の子たちはどちらの集団でも、自分たちの行動が変ったことに全く気がついていなかった。
こんなふうに女の子が男の子の前でやる気をなくしてしまったため、
「この年齢では平均的な男の子は平均的な女の子よりも明らかに背が低く体重も軽かったが、それでも男の子は勝てた」
ということになってしまった。
これはジェンダーフリーの社会の実現をめざす人たちには、あまり望ましくない調査結果といえる。
これについてのハリスのアドバイスは、
「子どもを男性的でも女性的でもないように育てたいという親は、子どもの人数が少なすぎて二つ以上の集団をつくれないような地域に転居することだ」
というもの。なぜなら、
「狩猟採集民族の集団では、男の子と女の子が別々の集団を形成できるほど子どもが多くない場合がほとんどであるため、男の子と女の子は一緒に遊ぶ。顕著な社会的カテゴリーは男の子と女の子ではなく、子どもと大人になる。そのため男の子も女の子も行動はたいへん似たものになる」
から、というのだが……
そういう理由で自分の娘を狩猟採集民の部落で育てようとするのは、かなり変わった親だけだろう。
娘を男勝りに育てたいなら、もっと現実的な方法がある。
男のいない学校に送り込むのだ。
日本と同様アメリカでも、女の子は理数系の勉強が得意でないと思われており、文系に進む割合が高い。
ところが男の子がいない女子校では、理系に進む女子生徒の割合が高くなる。
「ジェンダーが顕著ではない状況においては、女の子も若い女性も科学や数学でよりよい成績を残す。女子大からは意外に多くの優秀な女性科学者たちが誕生している」のだ。
実は筆者も全く同じことを進学塾の先生から聞いたことがある。
その先生の話では、
「同じくらいの学力を持った女の子でも、女子校に進む場合と共学校に進む場合で、卒業後の進路が大きく違ってくる。女子校に進んだ子は医者になったり弁護士になったりして社会で活躍する子が多いが、共学に進んだ子は恋愛に興味が向かってしまい、なかなか伸びない。就職後に挨拶に来た元生徒たちで、そういう実例をたくさん見てきた」
ということだった。
娘を医者やITエンジニアにしたければ、共学より女子校に入れ、女の子の中だけで勉強させるほうがよさそうだ。
●「孟母三遷」は正解だった
学校内にいくつかの集団ができると、それぞれの集団が他の集団と差別化しようとして、集団同士の学力の差が広がってしまうことがある。
学校のようにみな年齢が同じ場合、子どもたちの集団は、まず人種と性で分かれ、それから家庭の社会的階層、そして学力によって分かれる。
「人種もしくは社会的経済的地位を超えた友情は、小学校高学年に近づくに従い、ますます珍しくなる。学業成績のよい子どもたちは同じく成績のよい子と友だちになり、問題児は問題児同士で友だちになる」
という現象が起こるのだ。
アメリカでは経験上「一クラスの生徒の数は少ないほうが勉強ははかどる」と考えられている。
これは子どもの数が少ないと、「まじめグループ」と「ふまじめグループ」に分かれにくくなるためだ。
学力ごとにグループに分かれると、もともと成績の良い子たちのグループはさらに成績を伸ばし、悪い子たちのグループは一段と落ちていく。
これは同じ子どもでも成績のよい集団に入るとみんなに合わせて勉強するようになり、そうでない集団に入ると勉強しなくなるためだ。
こうした傾向を心理学で「マタイ効果」と呼ぶ。新約聖書の「持っている者はさらに与えられて豊かになり」というマタイの言葉からとったものだ。
クラスが白人のグループと黒人のグループに分かれた場合、白人グループはまじめに勉強しようとし、黒人グループはそれを敵視することが多くなる。
「黒人の生徒にとって学業で優秀な成績をおさめることは、友人を裏切り、クラスの中でも白人が支配する集団に入ることを意味することが多い」のだ。
黒人の家庭でも親は普通、子どもがまじめに勉強してくれることを望んでいるのだが、成績のいい黒人の子どもには、グループの仲間たちから「そんなに勉強すんな」と圧力がかかる。言われた通りにしないと、「白人のよう(アクティング・ホワイト)」と言われて目の敵にされてしまう。
結果、本来は頭の良い子であっても仲間に合わせて勉強しなくなり、不良行為に手を染めたりすることになる。
「悪いことをするのが正しい」という文化の集団に入っていると、悪いことをしないでいるのは難しい。
アメリカの犯罪者、特に男性はほとんどが十代から二十代前半で、友だちとつるんで悪事を始める。
「彼らは所属する集団の規範に従い、集団内の地位を失わないようにしているだけなのだ」
とハリスはいう。
「朱に交われば赤くなる」
のは世界共通らしい。
黒人であっても、他の子たちより成績のよいグループに入った場合は逆の結果になる。
ブルックリンやブロンクスではジャマイカやハイチからの黒人移民の子どもたちが成績優秀グループを作っていて、そこから社会的に成功した人も多い。
湾岸戦争のときアメリカ軍の統合参謀本部議長だったコリン・パウエルも、ブロンクスのジャマイカ移民の家の子だった。
ジャマイカ系黒人のグループはまじめに勉強する文化を持っていて、それが代々伝えられ、そのおかげでメンバーは社会的に成功しているのだ。
子どもの集団に外から子どもが加入すると、新しく入った子は周りに合わせて言葉や行動を変える。
何かのきっかけで不まじめグループからまじめグループに移ると、同じ子でも生活態度や成績が全然変わってくる。
ハリスは著書の中でニューヨーク・タイムズの記事の例を引用している。
「16歳でサウス・ブロンクスに住んでいたラリー・アユソは成績不振でバスケットボールのチームに入部が認められなかった。
友人のうち三人は麻薬がらみの殺人事件に巻き込まれて命を落とした」
このラリーくんは「スラムから子どもたちを転居させる」という慈善プログラムでニューメキシコ州の小さな町の中流階級の白人家庭に引き取られた。
その結果どうなったかというと、
「二年後には成績はAとBばかりで、高校のバスケットボール・チームに所属し、一試合で二八点を稼ぎ、大学進学をめざしていた」
転居が功を奏して、落第生が成績優秀なヒーローに変身したのだ。
子どもがどんな仲間とグループを作るかは、住んでいる地域にどんな子どもが多いかで変わってくる。
大都市のスラムには不良の少年が多い。そうした地域に住んでいると、自分も不良になる確率が高くなる。
イギリスの研究では、「都市のスラムに住む非行少年を郊外に転居させると、問題行動が減る」という結果が出ている。
デンマークで、犯罪者の家庭の養子になった場合に、その子が自分も犯罪者になる確率を調査した。
その結果、都会の近郊で育てられると普通の家庭の養子より犯罪者になる率が高くなり、人口の少ない村や僻地では、犯罪者の家庭とそうでない家庭とで育てられた養子との間に、犯罪者となる確率の差はなくなるとわかった。
子どもは近所の近い年齢の子たちの影響を強く受けるので、どこに住むかは子どもの将来に大きな影響を及ぼす。つまり親が住む地域を選ぶことによって、子どもたちが犯罪を起こしたり、学校を中退する可能性を下げられるということだ。
「孟母三遷」という中国の故事がある。
中国の戦国時代の儒学者・孟子の家は、はじめ墓場の近くにあった。ところが子どもが葬式の真似をするので、お母さんは「これはいけない」と市場の近くに引っ越すことにした。そうしたら子どもは商売の様子を真似するようになった。お母さんはこれも気に食わなくて、今度は学校の近くに引っ越した。すると子どもが学生の真似するようになったので、「ここがいい」と満足してそこに住むことにした。
やがて子どもはその時代を代表する大学者・孟子になった、という。
子どものために三回も住む地域を変えた孟子のお母さんの行動は、現代社会心理学から見ても正解だった。
子どもをいい子にしたり成績優秀に育てたかったら、家での育て方を工夫するより、住む場所や通う学校を選んだほうが効果が大きいのだ。
●移民の子の特別扱いは逆効果
言葉の習得についても、親より学校や近所の友達の影響のほうがずっと大きい。
人間はもともと親からではなく子どもグループの中で言葉を覚えてきた。
伝統社会では2歳半ぐらいで親から離れて子どもグループに入るが、これは伝統社会ではようやく言葉を話しはじめたばかりの年齢である。
伝統社会では言葉は親が子どもに教えるものだとは考えられていない。乳飲み子は言葉など理解できないと思われているので、親は我が子に話しかけることをあまりしない。
母親が赤ちゃんに話しかけないため、子どもの主な言語の習得時期は子ども集団の中に入ってからになる。
現代社会でも言葉は主に同世代の仲間と話すことで習得される。
話し言葉が使えない聾者(ろうしゃ)の両親の下で正常な聴力を持って生まれた子どもは、親からは全く言葉を教えられなくとも、みな普通にしゃべれるようになる。友達と話して覚えるのだ。
反対に一定の聴力を持ち、普通にしゃべれる子が聾学校に入学してくることがあるが、そういう子もしばらくすると周りの子に合わせて、口で話すことをやめ、手話で会話するようになる。
非英語圏から英語圏に移住してきた家の子は、家の外で友達と話して英語を覚える。
最初のうちは家の中では親と同じ言葉を話しているが、次第に英語を家の中まで持ち込むようになり、母国語で話しかけてきた親にも英語で返事するようになる。
家族で海外に移住しても、親は子どもに現地の言葉を教える必要はない。子どもは勝手に覚えて親より上手になるからだ。
ただ子どもが周囲の子から現地の言葉を学ぶのは、その子が現地の学校に入り、周りの友達がみな現地の言葉を話している場合にかぎられる。
アメリカには英語を話せない移民の子どもたちを母国語ごとに分けて英語を教える、バイリンガル・プログラムを実施している学校がある。
言葉が話せない移民の子たちのためを考えて行われている施策なのだが、ハリスによればこのプログラムは、目指すものとは正反対の効果しかもたらさない。
バイリンガル・プログラムのおかげで、移民家族の多い地域では子どもたちは学校にいる時間の大半を同じ国の言葉を話す他の子どもたちと一緒に過ごすことになる。結果、子どもたちは互いに母国語で会話するようになり、英語を覚えようとしなくなってしまうのだ。
仲間うちで使う言語がスペイン語や中国語であれば、それが彼らにとっての第一言語となり、英語は第二言語にしかならない。
同じ集団に属する子どもの多くがスペイン語なまりの英語を話していれば、その集団の子は全員がスペイン語なまりの英語を話すようになり、思春期までずっとその集団に属していれば、大人になってもなまりは変わらない。
言葉を学習する上で決定的に重要なのは、2歳から15歳ぐらいまで。
「人はなまりのない言語を獲得するのにわずか13年程度しか与えられていない」
という。
元アメリカ国務長官のヘンリー・キッシンジャーは15歳でドイツからアメリカに移住したが、大人になってもドイツなまりが抜けなかった。
彼の1歳下の弟ヴァルターは14歳でアメリカに移住し、なまりのない英語を話すようになった。
1年の違いでそうした差がついてしまうのだ。
スラムの学校から郊外の学校に移って変身した高校生の話をしたが、まじめな子が多い学校がいいからといって不良の子どもたちをまとめて何人もまじめな子たちばかりの学校に入学させたりすると、いい結果にはならない。
人数が多いと新加入の子たちだけで独自の集団を形成し、周りのまじめっ子と自分たちを差別化しようと、ワルの集団になってしまうからだ。
上のラリーくんのケースでは、他に黒人がいない街に一人で送られたのがよかったのだ。
同じことは英語を話せない移民の子についても言える。
同じ教室内に自分と同じ言葉を話す子どもたちが誰もいなければ、移民の子は最初はとまどっても、間もなくその国の言葉を話すようになる。
だが国や自治体が余計な親切心から、その国の言葉を話せない移民の子を1ヶ所に集めるようなプログラムを作ってしまうと、目的とは反対に、いつまでも移住先の国の言葉が話せない子になってしまいかねない。
これはこれから外国人労働者を本格的に受け入れようとしている日本でも、参考になる指摘だろう。
●早生まれは一生続くハンディ
子どもたちは仲間集団の習慣に自分を合わせていくが、一方で集団の中での自分の立ち位置を確立しようとする。
グループの他の仲間と言葉遣いや行動をできるだけ合わせようとする一方で、他の仲間と自分の違いをアピールするのだ。
「児童期は子どもたちが自分自身を知る時期だ。自分がどれだけ強いか。どれだけかっこいいか。どれだけ頭がいいか。それらを知るために、彼らは自分と同じ社会的カテゴリーに属する人たちのいる集団の各人と自分とを比較する」
ここで問題は、同じ学年でも子どもによって成長の度合いに大きな差があることだ。
「同年代の子どもたちで集団が構成される場合、その中では最も発育の早い子が最も高い地位につく傾向がある」ことが観察されている。
「背の低い子どもたち、とりわけ男子は、仲間内では低い地位に甘んじる場合が多い。
背の低い子どもたちは背の高い子どもたちよりも自尊心が低いことで悩み、他の心理的問題もかかえやすい」のだ。
しかもさらに問題なのは、幼年期から思春期の間に子ども仲間の集団で培われた性格や行動パターンは、その後も一生、本人につきまとうということだ。子ども集団における地位の高低も、成人後の性格にまで永続的な影響を及ぼしてしまう。
男の子を発育の早い子と遅い子に分け、成人にいたるまで追跡調査した研究がある。
前述のように性格は家庭環境の影響は全く受けないことがわかっているのだが、この研究では驚いたことに、発育の早い子と遅い子の間では成人になってからも明確な性格の違いが見られた。
発育の早かった者は威厳があり自信にあふれていた。企業の上級管理職など、人を指導する立場にいる者の割合も高かった。
発育の遅かった者は自分に自信がなく、他人の気持ちに敏感で、人に気にかけてもらいたい気持ちが強かった。
これは言い換えると、
「同じ学年の中で早く生まれた子は、遅く生まれた子より決定的に有利で、その影響は一生続く」
ということだ。
同様の研究は日本でも行われている。
奈良女子大の中田大貴准教授は2017年に、プロ野球やJリーグの選手の生まれ月を調査している。結果は4~6月生まれが圧倒的に多かった。
中田准教授は「他の子より発達が進んでいる分、子どもの頃レギュラーに選ばれて活躍する機会が多く、それによってさらに技術が上達し、自信にもつながるのだろう」と分析している。
子どもの頃に集団内で優位であることが、生涯にわたる差を生むのである。
工業化、都市化が進み教育制度が確立された現在では、子どもたちは同年齢の集団に分けて保育され、勉強させられている。だがそうなる以前、子どもたちが置かれていた状況は全く違っていた。
伝統社会では子どもたちはみな、年齢的にも体型的にも集団一のチビとしてグループに加わり、成長とともにその位置からだんだんと順位を上げ、最後は最年長に、つまりグループのトップになっていたのだ。
現代でも年齢を超えた遊び集団が健在な地域では同じことが観察される。
しかし都市化が進んでたくさんの同学年の子と一緒に育つ子どもたちは、一番下から成り上がって最後は一番上になる、という経験ができない。
家庭内では永遠にお兄ちゃんであったり、永遠に末っ子であったりする。
学校では運良く人より少し成長が早ければ、何年間も学年で一番でかいボスであり続けられるし、運悪く周りより成長が遅ければ、一番のチビとして下に見られ続けることになる。
ハリスは指摘していないが、現代の学校にも逃げ道はある。
たとえば筆者はこの「一番下からだんだん上がって、最後は指導層になる」という過程をちゃんと経験している。
筆者にとってのその経験の場は部活動だった。
中高一貫の男子校で運動部にいたため、一番小さくて弱い中一から始めて、最後は下を指導する側になって部活を終えているのだ。中高一貫校では下の学年と上の学年の体格の差は大きいので、明確な上下のヒエラルキーが健在である。
同様の経験をしてきた人は多いはずだ。
日本の学校では教科以外の課外活動や部活動がそうした経験を積む貴重な機会となっている。
それは子どもたちの性格形成に大きな役割を果たし、現代における全人教育の重要な一環をなしていると考えられる。
また同学年の中で体格では一番でなかったとしても、他にも自分の立ち位置はある。勉強ができるとか、「おもろいやつ」であることもその一つ。
そうした集団内でのポジションが決まると、その子がもともと持っていた性格がさらに強調されるようになる。
「ひょうきんな子どもはますますひょうきんになり、頭脳明晰な子はますます頭脳明晰になる」
という現象が生じるのだ。
ユーモアがあることや知的であることが他の人とは違う特色ということになり、子どもはそれを自分の強みとして認識する。児童期は本来、子どもたちが自分自身を社会の中の決まったポジションに当てはめる時期なのだ。
その結果、この時期に選んだ役割はしばしば一生、その人を特徴づける性格となる。
そういった救いはあるにしても、学年の最初の1、2ヶ月に生まれた子は、最後の1、2ヶ月に生まれた子よりはるかに恵まれていることは、疑いようのない事実だ。
早生まれの子は1~3月に生まれたというだけで自分には何の責任もないのに、一生不利を背負わされてしまう。
これは由々しき問題だ(筆者の娘は2月生まれなのだ)。学年制を採る現代の教育制度の欠陥というべきであろう。
*****************
以上、一冊の本の中身を整理するのにずいぶん長くなってしまったが、それだけ内容が濃かったということでもある。
興味があれば一読をお勧めしておきたい。