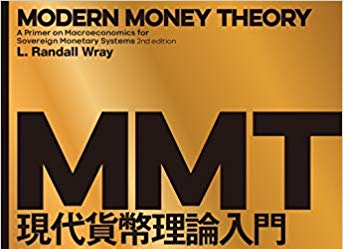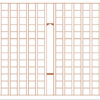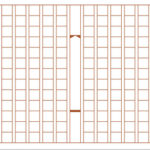目次
●『源氏物語』はアンチ藤原氏の物語
『源氏物語の謎』の終盤は、
「それではこの壮大な物語の最初の一部を書いたのは誰なのか」
という原作者探しに当てられている。
藤本はここで、
「紫式部には藤原氏出身と小野氏出身の2人がおり、後者は語り部として有名だった。その伝承が前者と混同されて『紫式部=源氏物語の作者』説に至った」
と述べているのだが……
筆者の個人的感想としては、綿密な考証を行っている前半に比べ、このあたりのくだりは飛躍が多く、あまり同意できなかった。
ただ藤本が、
「『源氏物語』の原作者は紫式部ではありえない」
とした論拠には、納得できるものが多い。
紫式部は通説では、
「藤原北家良門流の藤原為時(父)と藤原為信の娘(母)の間に生まれ、藤原宣孝と結婚し一女をもうけたが死別、その後に出仕して一条天皇の中宮であった彰子(しょうし)に女房として仕えた女性」
とされている。
この当時の中宮とは、天皇が皇后を2人持った場合に、皇后のうち1人を区別して呼ぶ際の呼称である。
一条天皇には彰子の他に皇后・定子がいて、天皇自身は彰子を皇后とすることにはあまり乗り気ではなかったが、彰子の父である藤原道長の強い要望により、皇后を2人とすることで妥協したとされる。
父も藤原氏なら母も藤原氏、死んだ夫も藤原氏、その上、藤原道長の娘である彰子に仕えていたわけだから、紫式部はまさに「藤原氏尽くし」の女性だったわけだ。
ところがおかしなことに『源氏物語』の中では、藤原氏は完全に「敵役扱い」なのである。
作中の朱雀(すざく)帝は母が藤原氏だが、光源氏に女を取られてばかりいる。
光源氏の正妻・葵(あおい)の上は藤原氏の出身だが、冷たくて意地の悪い女として描かれ、光源氏との夫婦仲は悪く、出産後に女の生霊に取り殺されてしまう。
葵の上の兄の頭の中将も同じく藤原氏出身だが、光源氏より年長なのに官位はいつも源氏より下で、朱雀帝と同じく光源氏に女を取られてばかりいる男として描かれている。
その上『源氏物語』では、光源氏が冷泉(れいぜい)帝の実の父となるなど、現実世界では藤原氏が行っていた「天皇の外戚」戦略を源氏の一族が代わって行っている。
この徹底したアンチ藤原氏の姿勢は『源氏物語』のお約束といってよく、最初に書かれたとみられる第一部の紫の上系物語にはもちろん、第二部、第三部でも幾度となく同様の展開が登場する。
藤原氏出身の敵役が源氏方の主人公にしてやられる話が、しつこく何度も繰り返されるのが『源氏物語』の基本設定なのだ――と藤本はいう。
「こんな話を自分自身が藤原氏で、両親も夫も仕えた先も全て藤原氏一族であった女性が書くと考えるほうがおかしい」
という藤本の主張は、筆者も至極もっともだと感じる。
さらに言えば、『源氏物語』に登場する朱雀帝と冷泉帝は、どちらも実在の天皇の名前なのである。
それが、片方は主人公に女を取られてばかりの人物として描かれ、もう片方はなんと天皇の后と主人公の不義の密通によって生まれた主人公の隠し子という設定になっているのだ。
こんなとんでもない設定は、現代の作家でも畏れ多くてとても書けない。戦前であれば不敬罪で留置場行きだ。
ましてや天皇の権力が今とは比較にならないほど強かった平安時代である。
「そんな話を皇后に仕える女官が堂々と書いて発表したなどと、信じるほうがおかしい」
と筆者も思う。
●本当に子供を生んだ女性が書いたのか
女性作家として多数の作品を上梓している藤本は、
「『源氏物語』はとても女性が書いた作品とは思えない」
とも述べている。
妊娠時の女性の描写や妊娠期間、生まれて間もない赤ん坊の描写等があまりに不正確で、子育て経験者なら絶対しない間違いが多数あるという。
そうした知識は母から娘に口伝えに伝えられるものなので、女性であればたとえ子供がいなくても常識的に知っていることばかりなのだが、明らかに作者は何も知らない。
「紫式部のように一児の母だった女性が、こんな間違いだらけの話を書くはずがない。これは男性の手による作品だ」
というのだ。
この点については、男である筆者には判断がつかない。
藤本はまた、
「『源氏物語』は平安時代の物語の中でも宮中の行事や儀式の描写が特に多い作品だが、中宮・彰子に仕えた女房であった紫式部は、実際の宮中をほとんど見てはいない。彼女が見たのはもっぱら、彰子が父である道長の屋敷に里帰りしたときの姿だった」
「『紫式部日記』から、紫式部が『源氏物語』を執筆したのは中宮・彰子に仕えた期間とされているが、それは長く見つもっても9年までで、これだけの大長編を書き上げるには短すぎる」
とも指摘している。
●『紫式部日記』への疑念
先にも触れたように、『源氏物語』を誰が書いたのかという直接的な証拠はない。
にも関わらず紫式部と呼ばれる歌人が『源氏物語』の作者と推定されている理由は、ひとえに『紫式部日記』と呼ばれる文書に、「『源氏物語』は自分が書いた作品である」と匂わすような記述があるためだ。
この『紫式部日記』について藤本は、
「いろいろな点で筋が通らない。当人が書いた日記などではなく、後世の人間の創作によるもの」
と評している。
その理由は以下のようなものだ。
・『紫式部日記』は地の文で「侍り」を多用しているが、『源氏物語』には会話文以外に「侍り」が使われた例はなく、文体が全く違う。そもそも「侍り」が地の文に使われるようなったのは後代のことで、紫式部の生きていた平安中期にそのような用例はない。
・この時代、女官にとって就職先は宮中しかなく、その立場は非常に弱かった。貴族の世界は狭く、少しでも嫌われたら追い出されてしまうため、悪目立ちしないよう、今日から見ると異常なほど周囲に気を使い、へりくだるのが常だった。ところが『紫式部日記』には手紙文の形で同僚の批評をしたり、和泉式部、清少納言などを辛辣に評価している部分がある。当時の女房が同僚の悪口を大っぴらに言い、まして文字の形にするなど考えられない。
・著書の周囲の女官には官位の下に「君(きみ)」などの敬称をつけているのに、自分が仕えているはずの中宮・彰子や雇い主である藤原道長には当然つけるべきはずの敬称をつけず、官位だけで済ませている。
・日記に自分の兄弟である藤原惟規とのエピソードを書いているが、「弟の」とも呼ばず名前でも呼ばず、官位を使っているのは不自然。また同じエピソードで「ふしぎなほど早く理解した」と自分のことをぬけぬけと自慢しているが、これもしつこいほどの「へりくだり」が当然であった当時の女官として不自然。
・日記の中で舟遊びした日の夜には、皆既月食に近い月食が起きているはずなのに、それにはなんの言及もなく「月がきれいだった」と書いてある。
・藤原為時の娘である紫式部の父や兄弟、夫はみな官位としては五位止まりだったのに、文中に「何ほどの数にも入らない五位」という露骨に見下した表現がある。
・若い貴族が今様歌(いまよううた)を歌う場面が出てくるが、今様歌が流行したのは紫式部の時代より後の平安後期。
・『紫式部日記』には紫式部が中宮・彰子のために『源氏物語』を書いているかのような描写があるが、そもそも『源氏物語』は徹頭徹尾アンチ藤原氏の物語である。その藤原氏の頂点に君臨して勢力をふるった藤原道長の娘として皇后になっている彰子が、現実とは逆に源氏が天皇や皇后の父となることをもって「めでたし、めでたし」と終わる(『源氏物語』第一部巻33)ような物語を読んで、喜ぶことなどありえない。
等々(以上、一部に藤本の別著書『王朝才女の謎』の内容を含む)。
確かに道長にしても、苦労して皇后にした自分の娘に仕えている藤原一族の女が、「藤原氏に代わって源氏が外戚になる」などという話を書いて評判をとっていると知ったら、激怒して即座に解雇していたのではないかと思われる。
筆者が読んだかぎりでは、『紫式部日記』の中宮の男子出産を巡る描写などは実にリアルで、実際にその場にいた者が自分で書いたか、少なくともその場にいた者から聞き取りした上で書かれた文章としか思われなかった。
その一方で「第二部」として日記の中に挟み込まれるようにして置かれている和泉式部や清少納言等の批評などは、いかにも後から取ってつけたような印象がある。
藤本が指摘する「やたらと『侍り』が多用されている」「実の兄弟の話を官名で書いている」「当時の女官なら絶対しない人の悪口や自慢話を書き立てている」というのもこの部分だ。
みなさんの中にも日記をつけている人はいると思うが、長いこと日記をつけた後、突然そこで職場の同僚や有名人の批判を長々と書き、その後にまた何事もなかったかのように日記をつけ始める、などということをするだろうか。
少なくとも筆者はそんなことをしたことはない。
常識的に考えて『紫式部日記』の第二部は、後から押し込まれたものだ。
藤本は前出の『王朝才女の謎』において、
「歴史的人物の名であとがきを偽造したり、天皇の玉璽を装った印を押したりして、どうでもいいような文書を古くて立派なものに見せようとした例は非常に多い」
と指摘している。
その例として挙げているのが、『源氏物語』の後日譚、『雲隠六条』だ。
これには石山本願寺の大僧都信誉が1058年に書いたというあとがきが付けられているのだが、「内容が『源氏物語』にそぐわない」「鎌倉時代の文献に出てこない」ということで、現在はあとがきともども後世の贋作とされている。
『紫式部日記』にしても、全てが後世の人間による創作ではないにしても、実在した日記に後世の人間が手を加え、「『源氏物語』の作者」風に仕立て直して世の中に流した可能性は否定できない。
もしそうだとすると「『源氏物語』の作者=紫式部」という通説は、根拠ゼロになってしまう。
「こんな薄弱な根拠しかない学説が、間違いない事実であるかのように教科書で扱われているのは、どう考えてもおかしい」
という藤本の主張に同感するのは、筆者だけではないだろう。
●『源氏物語』と『紫式部日記』はいつ書かれたのか
『紫式部日記』はいつ書かれたのか。
『源氏物語』と同時期なのか。それとも『源氏物語』が世に知られるようになってから出てきた本なのか。
筆者は『紫式部日記』が初めて他の文献で言及されているのがいつか、調べようとしたが、「初出 1008年」と、『紫式部日記』文中の記述から推定された年代をもって「初出」としているものばかりだった。
こう言ってはなんだが、ずいぶんといい加減な定義である。
本当はいつごろ発表されたものなのか、今となっては知るすべはなさそうだ。
そもそも『源氏物語』自体、いつごろに書かれ、いつごろ発表されたものなのか不明である。
前出の13世紀終盤の『弘安源氏論議』では、「『源氏物語』は寛弘(1004~1011年)の頃に成立し、康和(1099~1103年)の頃に広まった」としている(「ウィキペディア」による)。
しかし物語成立から300年近くも後の時代の伝聞なので、信頼できる話とは言いにくい。
「ウィキペディア」の『源氏物語』の項では「『源氏物語』の文献初出は1008年」となっている。
『紫式部日記』の中に「『源氏の物語』」という記述があり、その『紫式部日記』が書かれたのは日記内の記述からすると1008年のはずだから、『源氏物語』についてもその年をもって「文献初出」とした、ということのようだ。
ここでも根拠になっているのは『紫式部日記』ただ一つなのである。
もし『紫式部日記』が本当はいつ書かれたものかわからないとすると、どうか。
藤本は「11世紀の正史には、『源氏物語』という言葉は出てこない」としている。
筆者の知る範囲では前述の『更級日記』の中に『源氏物語』が登場している。
『更級日記』は貴族の奥方であった菅原孝標の次女が、夫の死後に自分の生涯を振り返って記したとされる回顧録で、公式文書ではない。
ただ記述内容から年代推定が可能とされている数少ない資料である。
仮にそれを初出とし、現在の通説による推定年代を正確とみるなら、著者である菅原孝標の娘が日記を書き終えた1059年が『源氏物語』の文献初出ということになる。
『更級日記』には著者が少女だった頃に『源氏物語』に夢中だったことが記されており、その始まりは父が国司だった関係で上総国にいた頃だった。
「当時の上総国には本などなくて、姉や義母の口から物語のところどころを聞くしかなくてもどかしかった」と語っているから、都では著者の家族が上総国に移ってくる以前から知られていたことになる。
菅原孝標が上総国の国司に任じられたのは1017年なので、遅くもその時までには『源氏物語』が読まれていたわけだ。
道長が太政大臣になったのが1017年だから、それと同年である。
つまり『源氏物語』は藤原道長の全盛期にはもう都の一部で評判になっていたことになる。
●なぜ同時代の文献のどこにも「紫式部」の名がないのか
藤本はこの『更級日記』について、
「これだけ『源氏物語』に憧れているのに、その作者については一言も言及がない。これは物語好きとしては不自然なことで、おそらくこの時点で『源氏物語』は作者不明とされていたのではないか」
と推定している。
筆者も同感である。
通説では970~978年のどこかで生まれたとされる紫式部は、菅原孝標の娘から見れば、972年生まれの自分の父と同世代だ。
「『源氏物語』が読めるように私を都に返して!」とわざわざ等身大の仏様を作ってお祈りするほど物語にはまり込んでいた少女であれば、その作者がどんな人なのか、関心を持たないわけがない。
作者が生きていたら「都にいる間に会いたい」と願っただろうし、死んだと知ったら悲しんでその事実を書き記していたはずである。
だが『更級日記』には『源氏物語』の作者の名も、紫式部の消息も全く出てこない。
素直に考えれば、少なくとも菅原孝標の娘が『更級日記』を書き終えた1059年の時点ではまだ、「『源氏物語』の作者=紫式部」という通念は一般的ではなかったと見るべきだろう。
当時の平均寿命からみて、1059年の時点で紫式部はもう亡くなっていたとみてよい。
つまり紫式部が生きていた間、彼女が『源氏物語』の作者であると一般の人が知ることはなかった、と考えられる。
こうして状況証拠を積み重ねると「『源氏物語』の作者=紫式部」という定説は、ますます信憑性が怪しくなってくる。
≪ 『源氏物語』の作者は誰だったのか(前篇) 『源氏物語』の作者は誰だったのか(後編) ≫