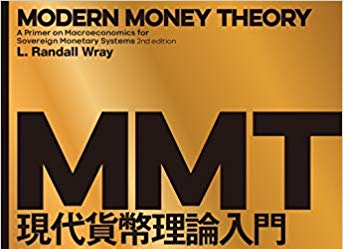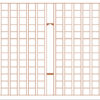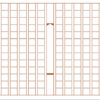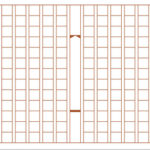目次
●道長の時代に「紫式部」はいなかった
そもそも「紫式部」という人間は実在していたのだろうか。
藤本は後年の著書『王朝才女の謎』の中で、藤原道長の日記である『御堂関白記』に触れている。
『御堂関白記』は、この時代の有力資料の一つである。
だが紫式部の雇い主の日記であるはずの『御堂関白記』には、『源氏物語』も「紫式部」も一切出てこないのだ。
『紫式部日記』には「寛弘五年土御門邸にて」と題して、
「『源氏の物語』、御前にあるを、殿の御覧じて、例のすずろ言ども出で来たるついでに梅の下に敷かれたる紙に書かせたまへる」
云々という記述がある。
土御門邸とは道長の邸宅であり、殿とは道長である。
道長の屋敷の中で中宮・彰子の前に『源氏物語』が置かれていて、道長はそれを見ていつものように冗談を言い、それから紙に和歌を書いてみせた――としており、これが文献における『源氏物語』の初出とされているのだが、そういったことは道長側の記録にはない。
『御堂関白記』には、紫式部の父とされる藤原為時の書いた漢詩に触れた部分がある。
為時は高官ではなかったが、文才では知られていたようだ。
部下でもない為時の短い漢詩については記載があるのに、「『源氏物語』を読んだ」とか「『源氏物語』という本の話を聞いた」という記述が全くないのはどうしたことだろう。
道長が『源氏物語』の存在を知っていたかどうかは不明である。
だが紫の上の物語だけでも大長編なのだから、もし読んでいたら何かしらの感想は残したはずだ。何も書いていないということは、読んでいないとみるべきだろう。
もし紫式部が道長の娘である中宮・彰子に仕える女房で、『紫式部日記』で記述されているように彰子のために『源氏物語』を書き、目の前に『源氏物語』を置いて道長と和歌のやり取りをしていたとするなら、これは奇妙な話である。
『紫式部日記』における『源氏物語』に関わる記述は、虚偽とみるべきだろう。
同時代の資料として有名な藤原実資の日記『小右記』には、「藤原資平が実資の代理で皇太后彰子のもとを訪れた際『越後守為時女』なる女房が取り次ぎ役を務めた」との記述がある。
この記述は、後年に「紫式部」として知られることになる女性が女房として中宮・彰子に仕えていた当時、「紫」とも「式部」とも呼ばれておらず、「越後の国司を務めた藤原為時の娘」として認識されていたことを示している。
『小右記』にも、「藤原為時の娘は『紫式部』とも呼ばれている」とか「この女房が都で評判の『源氏物語』を書いたというもっぱらの噂である」などという記述はどこにもない。
そもそも同時代の資料のどこにもそんな話は出てこないのだ。
『紫式部日記』を除いては、である。
ただし『紫式部日記』自体にも、「紫式部」という名前はどこにも出てこない。この日記を書いた者が周囲からどんな名で呼ばれていたのか、それを示す記述が日記中にないのだ。
道長が生きていた時代、「紫式部」という名の人物はどこにも存在していなかった。
そう考えるのが自然だ。
●作家「紫式部」はいつ誕生したのか
「紫式部」の名の初出はいつだろうか。
1086年に完成した『後拾遺(ごしゅうい)和歌集』に、「紫式部」の名で
「み吉野は春のけしきにかすめども結ぼほれたる雪の下草」
他の和歌4首が収録されている。
これは勅撰和歌集なので、公式文書に数えてもいいだろう。
以後の勅撰和歌集には、歌人・紫式部の和歌がしばしば登場することになる。
『後拾遺和歌集』の紫式部が藤原為時の娘であるかどうかは、はっきりしない。
藤本は前出の『王朝才女の謎』で、
「わたしは為時の娘が中宮彰子に仕えた歌人女房の紫式部であることを、うたがったことはこれまで一度もない」
と述べている。
もしそうだとしたら、出仕していた間『越後守為時女』と呼ばれていた彼女がどのようにして「紫式部」と呼ばれるようになったのか、その経緯をぜひ知りたいものだと思う。
以下はそれについての筆者の想像である。
『源氏物語』という今の作品名は、主人公の光源氏の名前から名付けられたものだが、古い時代には作中第一のヒロインである「紫の上」の名をとって『紫の物語』とも呼ばれていた。
11世紀初めの都の人々にとって『源氏物語』は、「光源氏と紫の上の愛の物語」と理解されていたのだろう。
ただし評判の作品であるにも関わらず、誰が書いたものであるのかは謎だった。
作者が名前を伏せたのは、状況を考えれば当然のことだ。
『源氏物語』が世に知られるようになった11世紀初めは、藤原氏による摂関政治の最盛期である。
最高権力氏族である藤原氏を敵役に据え、彼らを外戚の地位から追い落として源氏がそれに取って代わるなどというアンチ藤原氏物語を書いたことが知られれば、どんな意趣返しをされるかわからない。
その上『源氏物語』は、現実に存在していた天皇の名をそのまま使い、主人公の引き立て役として使ったり、主人公の不義の子としたりしている。
とても著者を名乗って公表できるような作品ではなかったのだ。
だが隠されれば探りたくなるのが人情である。
『源氏物語』の評判が高まるにつれ、都では、
「あの『源氏物語』を書いたのは誰なんだ」
という詮索が、物語好きの間で盛んに行われていたことだろう。
そこに出てきたのが『紫式部日記』である。
日記の書き手の名前は作中に出てこないが、どんな立場の人間かは読めばすぐわかる。
内容は、全体としてはリアルな手記でありながら、ところどころにいかにも「私が『源氏物語』を書きました」と言わんばかりの記述が含まれている。
この文書は古くは『紫日記』と呼ばれていた。
自ら作った写本に『源氏物語』のヒロイン「紫の上」の名前を連想させる思わせぶりなタイトルをつけ、日に当てたり汚したりして古い本らしく黄ばませ、素知らぬ顔で「うちの古い蔵から出てきました」とでも言って流通させたのだろう。
なんの目的でそんなことをしたのかはわからない。ただの愉快犯かもしれない。
明かされない作者名にじれていた人々は、目の前にさりげなく投げ出されたこの餌に飛びつき、以後、
「『源氏物語』の作者は中宮・彰子に仕えていた女房、藤原為時の娘」
という強固な定説が誕生する。
「こんな反藤原色の強い作品を道長に雇われていた女房が書くか」とか、「実在の天皇を不義の子とするような設定の作品を皇后に仕える女房が書くか」といった当然の疑問は、なぜかスルーされてしまう。
多数の不審点が見過ごされたのは、それだけ「『源氏物語』の作者を知りたい」という人々の飢えが強かったためだろう。
現存する資料との整合性を重視するなら、『更級日記』が書かれた1059年から『後拾遺和歌集』が編まれた1086年の間に『紫日記』の存在が知られるようになり、『源氏物語』の作者とされた藤原為時の娘の評判が高まって、歌人としての彼女も改めて脚光を浴びたと考えられる。
「式部丞」は当時の官位の一つだが、和歌の世界の「式部」は「女史」というほどの意味で、その上に国名などをつけて女流歌人のペンネームとして用いられることが多かった。
勅撰和歌集での初出にあたって「紫式部」という名が与えられたのは、都で評判の長大な物語『源氏物語』の作者に対して敬意を払う意味で、国名ではなく『紫日記』や『紫の物語』の「紫」を採ったものだろう。
その名が公式文書である勅撰和歌集に掲載されたことで以後、「歌人にして『源氏物語』『紫日記』の作者=紫式部」という認識が公のものとなり、『紫日記』も『紫式部日記』の名で呼ばれるようになった。
そう考えると、辻褄が合う。
以上はもちろん、空想にすぎない。
ただし藤本が指摘するように、『源氏物語』の反藤原色の濃い内容からして、それが藤原氏に属する誰かによって書かれた可能性は限りなく低いと、筆者も思う。
それがなぜ「藤原氏出身で道長に仕えた女房」が作者に擬せられることになったのか。
そこには何かしら意図的に人心を欺こうとした作為があったのではないか。
以上とは直接関係ないが、紫式部は『紫式部集』という自選の歌集(家集)を残したことになっている。
この『紫式部集』がいつ、どのような経緯で編まれたものかは不明である。
『紫式部集』というタイトルからして、本人の死後、「藤原為時の娘こそが『源氏物語』の作者である」という風評が確立され、後拾遺和歌集で「紫式部」という歌人名が与えられてより後に編まれた歌集ではないだろうか。
本当に「藤原為時の娘」が詠んだ歌が納められているのか、それも確証はない。ただ藤本も言うように、あえてそれを疑う理由もない。
筆者も『紫式部集』を読んでみたが、優れたセンスを感じさせる、よい歌が多いと個人的には感じた。
おそらく『源氏物語』の作者という評判がなくとも、勅撰和歌集に採用されていたのではないか。
小倉百人一首に選ばれた紫式部の和歌も、ここから採られている。
●「反藤原」は平安文学の基本
藤本は『源氏物語』と同時代の『篁(たかむら)物語』『竹取物語』『伊勢物語』『平中(へいちゅう)物語』『大和物語』『宇津保(うつぼ)物語』『落窪物語』『多武峯(とうのみね)少将物語』『狭衣(さごろも)物語』『浜松中納言物語』『夜半(よは)の寝覚め』といった王朝文学作品を分析し、
「王朝文学とは、反藤原氏の文学である」
と断じている。
藤原氏は勢力を拡大する過程で、古くからの名門であった平、橘(たちばな)、大江、伴(とも)、清原、紀(き)、小野などの諸氏を退けてきた。
平安朝文学のほとんどは、これらの氏族の者が主人公となっている。
『篁物語』の主人公は小野氏、『伊勢物語』は在原氏、『平中物語』は平氏、『宇津保物語』は清原氏、『源氏物語』『落窪物語』『狭衣物語』『浜松中納言物語』『夜半の寝覚め』の主人公は源氏。
大陸から伝わった物語の翻案である『竹取物語』と、小話集である『大和物語』は毛色が異なるが、藤原氏が主人公なのは『多武峯少将物語』ぐらいなのだ。
上記の中でも源氏を主人公とする5作品は、数が多いだけでなく他の物語と比べて長さも長い。
なお源氏というと、現代では「武家の棟梁」というイメージが強いが、平安中期までの源氏は皇族が臣下に下る際に下賜される姓であり、貴族の中でも特に名門と考えられていたという。
血統からいえば天皇を補佐する上で最適任のはずだったが、藤原氏が巧みに天皇との間に外戚関係を築くことに成功し、摂関政治を展開して、源氏を政権トップから追い落としてしまった。
藤原氏は9世紀末の菅原道真の太宰府への左遷以降、突出した政治支配力を獲得。
10世紀末、安和の変で源高明が失脚させられてからは、宮中は完全に藤原氏の天下となった。
この源高明は文才、楽才に優れ、左大臣にまで出世し、光源氏のモデルとも言われる。
だが謀反に加担したとの嫌疑を着せられ、太宰府に流されてしまう。
『源氏物語』を含め、源氏を主人公とする一連の作品群が源氏一族に属する書き手により書かれたことは、ほぼ間違いないだろう。
いずれも反藤原氏の色彩が濃いだけでなく、「源氏が天皇の外戚となる」という設定が繰り返し出てくる。
これを源氏以外の氏族の者が書いたとするのは、いかにも不自然だ。
トータル5作品の膨大な量からしても、源氏の一族内には複数の書き手がいたはずである。
中でも『源氏物語』の場合、巻ごとのストーリーや配役の断絶、文体の違い、物語の書き手としての力量の差が歴然としていることからみて、複数の人間が執筆に関わり、世代を越えて書き継いでいったと考えられる――。
藤本はそう結論している。
大変、説得力のある議論であり、筆者もそれが事実ではないかと感じる。
藤本は源氏一族の中でも前出の源高明を、『源氏物語』を最初に書き始めた原作者候補の筆頭に挙げている。
その理由は、
・『源氏物語』の主人公・光源氏は朱雀帝の腹違いの兄弟という設定だが、源高明も朱雀天皇の腹違いの兄弟であるなど、経歴や身の上が『源氏物語』主人公の光源氏とそっくり。
・『源氏物語』では宮中の儀式や行事が克明に描写されているところから、書き手は宮中に日常的に出入りしていたとみられるが、高明は『源氏物語』の設定そのままの時期に宮廷の暮らしを体験している。
・高明は文才と学識があり、『西宮記(さいきゅうき)』という宮廷内部の儀式や歴史を書いた漢文の大著の著者でもある。その内容は宮廷の儀式や行事を詳細に描いている『源氏物語』とも通じるものがある。
・安和の変で藤原氏に恨みを抱いているはずなので、反藤原氏の物語を書こうという動機がある
・安和の変以降、出家して政務には就かず、経済的余裕もあって働く必要もなかったため、大部の本を書く時間があった。
というもの。
この「『源氏物語』の原作者=源高明」説は「ウィキペディア」の『源氏物語』の項でも異説の一つとして取り上げられている。
ただ藤本が源高明を原作者候補として挙げた理由を見る限り、「それらしい」というだけで、明確な根拠があるわけではない。
藤本も後年の『王朝才女の謎』で、
「あくまで仮定」
「学識と宮廷ぐらしの経験があって、経済的余裕にめぐまれ、しかも藤原氏のおかげで閑職に甘んじていれば、『源氏物語』を書く、才能と動機と立場にはいずれもこと欠かない」
とトーンダウンしている。
本書の発表後、「根拠薄弱だ」とだいぶ叩かれたのだろう。
源高明以外にも、藤原氏に同じような目に遭わされた源氏一族はたくさんおり、その誰が原作者でもおかしくはない、ということだ。
だが筆者は、藤本とは異なる理由で「『源氏物語』の原作者=源高明」説を推したい。
その理由とは、『源氏物語』作中の天皇の名前の表記である。
前述したように『源氏物語』では、朱雀帝と冷泉帝については実在の天皇の名前がそのまま使われている。
ところが朱雀帝と源高明の父に当たる醍醐天皇については、作中では「桐壺帝」という別の名前になっている。
なぜなのか。
実在の天皇の名を二つもそのまま使っておいて、もう一人の天皇については名前を変えている理由としては、
「朱雀天皇と冷泉天皇は物語に使ってもいいが、醍醐天皇はまずい」
と作者が判断したから、としか考えられない。
そんな判断をする人間がいるとしたら、日本国広しといえども醍醐天皇本人とその子供たち、およびその直系の一族しかない。
親政を行って「延喜の治」と謳われたほど、死ぬまで政務に熱心だった醍醐天皇には、源氏一族を主人公にする物語など書く動機がないし、その時間もなさそうだ。
数多い醍醐天皇の子供たちの中でも、臣下に落とされて源姓を賜ったのは兼明親王(後に皇族に復帰)と源自明、源高明ぐらいしかいない。
兼明親王も源自明も母は藤原氏なので、反藤原氏の物語を作るとは思えない。
となると残るのは源高明しかいない。
そもそも朱雀天皇と冷泉天皇の名前を使うこと自体、普通の人間だったら絶対にしないことだ。
だが自分がその天皇の兄であった人物なら、それをする可能性はある。
高明は学識文才に優れた人物で、左大臣まで出世したことからもわかるように、官僚としても有能だった。
「自分のほうが朱雀より能力は上だ」と思っていたに違いない。
ところが母が源氏だった自分は臣下に落とされ、母が藤原氏だった朱雀は天皇になった。
高明は七歳で臣下に落とされ、朱雀は八歳で即位している。
朱雀天皇は醍醐天皇の第11皇子である。10人いた兄を抜いて皇太子とされたのだ。
さらにその後には同母弟が村上天皇になっている。
「兄の自分を差し置いて藤原氏の子供ばかり優遇して、おかしいだろう」
という気持ちは高明には当然あったはずだ。
天皇になった弟に対して「そんなに朱雀が偉いのか」という反感を抱いても不思議ではない。
冷泉天皇は、朱雀天皇の同母弟であった村上天皇の息子である。
高明から見れば甥にあたる。
もともと第二皇子であったが、藤原氏の強い推薦により、異母兄の第一皇子を差し置いて、生まれてすぐに皇太子となっている。
こういう経歴からして、高明には気に入らなかったはずだ。
冷泉天皇は精神を病んでいたと言われ、子供もなかったため、冷泉天皇の弟たちが次の天皇の候補となった。
高明は自身の娘を冷泉天皇の弟にあたる為平親王の妃としており、この親王は有力な天皇候補であったが、高明が天皇の外戚となることを恐れた藤原氏の反対により、皇太子に選ばれなかった。
冷泉天皇の次には為平親王の弟である円融天皇が即位している。
為平親王は兄と弟が天皇になったのに、一人だけ外されてしまったのだ。
高明としては、度重なる藤原氏の横槍に憤懣やるかたなかっただろう。
あげくの果てに安和の変で藤原氏に陥れられてしまう。
もはや恨み骨髄と言ってよい。
そのようなわけで、こと源高明の場合、朱雀天皇や冷泉天皇を実名で使っても不思議ではない。
もともと自分と同格で、藤原氏の後押しで兄を押しのけて天皇になった、腹立たしい存在なのだ。
だが醍醐天皇は自分の実の父である。
高明から見れば「おれだけ臣下に落としやがって」という恨みはあっただろうが、さすがに父親を実名で自作の小説に登場させることには憚りがあったはずだ。
高明の子供や子孫たちにとっても、醍醐天皇は自分たちのご先祖さまである。
そのことが作者の筆を鈍らせ、3天皇のうち醍醐天皇だけ名前を変えることにつながったと考えると、うまく説明がつく。
このように見てくると、藤本が提唱した「『源氏物語』の原作者=源高明」説は、それ以外のどんな作者を当てるより信憑性が高いと思われる。
とはいえ、もちろんそれは状況証拠にすぎない。
たとえ源高明を原作者としても、彼が書いたのは長大な『源氏物語』の第一部のうちの紫の上系物語のそのまた一部にすぎず、その一部の文さえ次の代の作者や筆写者によって書き換え、書き足しを受けているはずなのだ。
従って「『源氏物語』の作者は源高明」といった誤解を招く言い方はすべきではない。
学術的な見地からは、『源氏物語』の作者はあくまで「不詳」「多数の書き手が関わっている」とすべきである。
●『源氏物語』の成り立ちと「紫式部」という虚像
以下は筆者の想像である。
『源氏物語』のような大長編が途中、誰にも読まれることなく書き続けられたとは考えにくい。
読者がいなければ、書き手がモチベーションを持続させることは難しいからだ。
反藤原氏色の強い『源氏物語』はおそらく当初、外部にもれないように、書き手の親族の中で内輪に回し読みされながら書き継がれていったのだろう。
その読み手がやがて書き手となり、自分が楽しんだ物語に新たなページを加えていった。
時代が下るとその物語は、同じように藤原氏に追い落とされて反感を抱く名門他氏族にも好んで読まれるようになった。
彼らは作中で藤原氏の男たちが光源氏に鼻を明かされるたび、胸のすく思いで喝采していたのではないか。
先に、
「『源氏物語』は1017年には都で読まれていた」
「当時は藤原道長の全盛期」
「しかし道長は『源氏物語』を読んでいなかった」
と述べた。
それは当然のことだった。
『源氏物語』はアンチ藤原氏物語なので、初期のその読者は第一に源氏一族、第二には反藤原氏の諸氏族に限られていた。
それは作者の身の安全を守るためにも絶対に必要とされたことだったのだ。
だが菅原孝標の娘が属した菅原家は、源高明同様に藤原氏によって失脚させられたあの菅原道真の係累であり、反藤原グループの一つとして、写本を渡されるなどして読者のうちに加えられていても不思議ではない。
一方で物語の敵役・藤原氏の頂点にあった道長には、誰もこの物語の存在を明かしはしなかっただろうし、まして読むように勧める者は皆無だっただろう。
13世紀の『源氏物語』注釈書である『紫明抄』には、
「かつてはたくさんの源氏の物語が存在していた」
という記述があるという。
『更級日記』にも著者が『源氏物語』と同時にいくつもの物語をプレゼントされた記述があるが、そこで挙げられたタイトルの多くは現代には伝わっていない。
残された5作品以外にも源氏を主人公とする物語がいくつもあったとすれば、「作家工房・源氏一族」の生産力は相当なものだったと推察される。
源氏を主人公とする反藤原氏の物語がそこで次々と生み出されていることは、公には語られなくとも、そこから写本をもらって楽しんでいた同時期の反藤原系氏族には自明のことであったのかもしれない。
そこで生み出された作品の中には、同じ光源氏を主人公とする紫の上系の物語と玉鬘系の物語があった。
玉鬘系はもとからあった紫の上系の作者とは別の作者による「本歌取り」的な要素が強い作品だったが、主人公の名前が同じであったことから、後の時代になって一つの話にまとめられてしまう。
また後の時代になって、『源氏物語』が書かれた当時の政治的文脈を知らない読者たちが「作者探し」を始め、彼らを引っかけることを狙って、中宮・彰子に仕えた女房が残した日記をベースに、それらしいエピソードや評論を書き加えた『紫日記』が創作された。
犯人の狙い通り『紫日記』に引っかけられた読者たちは「『源氏物語』の作者=中宮・彰子の女房、藤原為時の娘」という虚構を信じ込んだ。
結果として、反藤原氏を共通理解として書き継がれた物語が、藤原氏の頂点を極めた道長の召使いで自分自身も純粋藤原氏の女性の作品とされるという、なんとも皮肉なことになってしまった。
筆者は現在、そのように理解している。
●なぜ藤本説は無視され続けているのか
本書『源氏物語の謎』の初版が出たのは1980年だから、既に発表から40年近く、一世代以上が経過している。
だが教科書には相変わらず「『源氏物語』の作者は紫式部」と堂々と書かれ、それとは違う見方が世の中にあることには一切、言及されない。
藤本も自説を発表したときには相当な自信を持っていたはずだが、あまりにも無視され続けたので、
「でもわたしは、いつかは――あるいは外国の研究者などから、この自説が表立ってみとめられるときが、きっと来ると思う。だからこそ、遺作にするつもりでこれを書いているのである。」(『王朝才女の謎』より)
と、悲痛な声を漏らしている。
藤本説に対しては、「平安の天才女流作家・紫式部」という華やかな伝説が壊されることへの反発がまずあるだろう。
また藤本説を認めると、これまで「『源氏物語』の作者は紫式部ただ一人」と信じて、互いに矛盾する文章を無理やり筋が通るように懸命に解釈してきた先人たちの努力は、徒労ということになってしまう。
過去の権威の失墜も、伝統を重んずる人々が嫌うところである。
『源氏物語』を「紫の上系」「玉鬘系」に分ける武田説が黙殺されたのも、一つにはそれが原因だったのではないか。
科学の世界には、
「新説が定説になるには、新説を発表してから、旧説を信じている研究者が死に絶えるまで待つしかない」
というジョークがある。
一つの説を一度信じてしまった人を説得するのはそれほど難しい、ということだ。
国文学の世界は、科学の世界よりもはるかに守旧の傾向が強い。
古い時代の文化に憧れ、それを尊重しようという気持ちが特別に強い人たちの集まりなのだから、当然ともいえる。
この世界で先人の権威を否定するような新説が受け入れられるのは、並大抵のことではない。
だが藤本も書いているように、真実はいずれは明らかになるものだ。
藤本の主張はどうみても旧来の定説より合理的なのだから、自分の頭で考えることができる人が読めば、
「なるほど。こちらのほうが正しそうだな」
と感じるはずだ。
大事なのは、それを語り継ぐこと。
筆者がこうして藤本説を紹介しているのも、その一環である。
本記事をご覧になった方たちには、ぜひ本書『源氏物語の謎』を入手して一読してほしい。
今は中古本でしか手に入らないが、興味を持つ人が増えれば電子化される機会もあるだろう。
国文学とは直接関係がなくとも、一般社会で藤本の主張が支持されるようになれば、やがて教科書の記載が訂正される日もくるはずである。