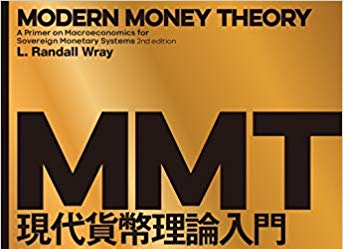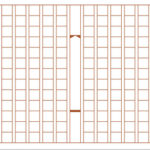『源氏物語の謎』(藤本泉 祥伝社 1980年刊行)は、隠匿された古代の謎を読者に提示し、知的興奮を湧き上がらせてくれる名著である。
筆者は歴史の門外漢だが、学生のときに本書を読み、目からウロコが落ちる思いを味わった。
既に絶版となり電子版も出ていないこと、著者の藤本氏が海外で行方不明となり消息を絶っているらしいこと(「ウィキペディア」による)から、その主張が忘れ去られてしまうことを懸念し、本記事で取り上げさせていただいた。

目次
●教科書が広げた誤解
義務教育を受けた日本人は全員、「『源氏物語』の作者は紫式部」と学校で習っている。
結果、日本国民のほぼ全員が、自分たちと同時代の作家を念頭に、
「紫式部という女性作家が、『源氏物語』という作品の最初の一行から最後の一行までを一人で書き上げ、著者名を添えて発表した」
と信じている。
筆者もその一人だった。
だがそれは実は事実からかけ離れた思い込みだったのだと、本書を読んで教えられた。
第一に、紫式部にかぎらず、「この人が『源氏物語』を書いた」という直接的な証拠はどこにもない。
第二に、『源氏物語』は多くの人の手による書き足し、書き換えを経て今の形となったものである。
書き足された部分があまりに多岐にわたるため、今となっては書き足される前の原型を知ることは不可能とされている。
書き足しを行った人々の名前は不明であり、誰がどの程度を書き加えたのかも全くわかっていない。
以上はいずれも藤本一人の主張ではなく、『源氏物語』研究者にとっては常識に類する事柄である。
現代人は「本とは印刷されて世の中に広まっていくもの」と反射的に考えてしまうが、平安時代には印刷された読み物などなかった。
物語は思いついた人の手によって紙に書き記される「手すさび」だった。
書いた人はそれを自分が見せたい人に見せていた。
読んでみて気に入った相手の中には、自分が繰り返し読むため、あるいは自分の家族や知り合いに貸し出して読ませるため、自ら筆を取って物語を筆写する人がいた。
そうやって筆写された物語が別の人の手に渡り、そこでまた筆写されて、といったことが繰り返され、読み書きの素養を持った人たちの間に写本が出回るようになり、物語の存在が知られていくのである。
筆写者は必ずしも書いてある文章をそのまま書き写すわけではない。
物語を気に入って写そうとする人には、自分も物語を考えることが好きな人もいて、筆写の過程で自分好みに文章を書き換えたり、オリジナルなストーリーを書き加えたりすることがよくあった。
現代でいう二次創作である。
むしろそれがしたくてわざわざ書き写した人が多かったかもしれない。
そうやって書き換えられた物語が次の人の手に渡り、また筆写の途中で書き換えられたりして、流布する過程で同じタイトルでもストーリーが異なる「異本」がいくつも生まれる。
現代に伝わる『源氏物語』は、鎌倉時代の歌人・藤原定家が写本した版が元になっているが、当時は他に二十数種の異本があったという。
それだけ様々な書き足し、書き換えがあったわけだ。
『源氏物語』はそのような筆写を繰り返しながら世の中に知られるようになり、後世に伝わっていった。
つまり『源氏物語』とは、学問的見地に立つなら「作者不詳。現在の形になるまでに多くの書き手が手を加えている」と表記されるべき作品なのである。
本来なら作者不詳のはずの作品に対して、なぜ小学校の教科書にまで「『源氏物語』の作者は紫式部」という断定的な記述が蔓延しているのだろうか。
●2系統の物語が合体されている『源氏物語』第一部
「『源氏物語』はダンテの『神曲』の300年前、中国の『水滸伝』の400年前に書かれた」。
藤本は本書の最初で『源氏物語』が成立した11世紀初めの時点では、世界の他のどこの国にも単一の作家による長編小説が存在していなかったこと、それどころか14世紀まで存在しなかったことを指摘し、「なぜ世界で初めて日本で、4代の帝王の治世と親子3代にわたり、総登場人物が400人以上にもなる長大な長編小説が誕生したのか」という疑問を提示する。
続いて藤本は、『源氏物語』には室町時代以降、いくつもの複数作者説があったことを紹介している。
鎌倉時代以前には、今日54巻と数えられている『源氏物語』のうち、題名だけしか残っていない「雲隠の巻」を含む37巻の本編に対し、残り18巻は「並びの巻」として区別されていた。
最古の『源氏物語』注釈書とされる藤原伊行の『源氏釈』(12世紀半ばに成立)では、並びの巻は扱っておらず、『源氏物語』を全37巻としている。
東北大学の武田宗俊教授(当時)は、
「『源氏物語』全体を三部に分けた場合の第一部とされる巻1「桐壷」から巻33「藤裏葉」までの33巻は、紫の上を中心とする17巻と、玉鬘を中心とする16巻という、2系統の物語に分かれている」
と提唱した。
まず紫の上系が、
巻1「桐壷」、巻5「若紫」、巻7「紅葉賀」、巻8「花宴」、巻9「葵」、巻10「賢木」、巻11「花散里」、巻12「須磨」、巻13「明石」、巻14「澪標」、巻17「絵合」、巻18「松風」、巻19「薄雲」、巻20「朝顔」、巻21「乙女」、巻32「梅枝」、巻33「藤裏葉」。
そして玉鬘系が、
巻2「箒木」、巻3「空蝉」、巻4「夕顔」、巻6「末摘花」、巻15「逢生」、巻16「関屋」、巻22「玉鬘」、巻23「初音」、巻24「胡蝶」、巻25「螢」、巻26「常夏」、巻27「篝火」、巻28「野分」、巻29「行幸」、巻30「藤袴」、巻31「真木柱」。
その理由は以下のようなものだ。
・紫の上系の17巻には、玉鬘系の16巻で主役級を演ずる玉鬘、夕顔、空蝉などの主要人物が1人も出て来ない。
・反対に玉鬘系には紫の上系の人物が出てくるが、その行動は限定されていて、時系列的には重なっているはずの紫の上系のストーリーに全く影響を与えていない。
武田教授は双方の物語を検討し、
「『源氏物語』は最初に紫の上系物語17巻が書かれ、続いて玉鬘系物語16巻が書かれ、その後に34巻以降の第二部、第三部が書かれた」
と結論している。
この武田教授による「紫の上系」「玉鬘系」という物語の区分は、鎌倉時代以前の「並びの巻」の区分とほぼ一致している。
だがこの新説はこれといった反論も受けないまま、学界から黙殺されてしまった。
藤本は武田説に賛同し、
「紫の上系物語と玉鬘系物語は、ストーリー展開や文中の会話や和歌の割合など文章スタイルが全く違い、時間的な矛盾も多数あって、同一作者の作品と見ることには無理がある」
と述べている。
また、
「紫の上系物語を元にアナザーストーリーとしての玉鬘系物語を書いた第二の作者は、自作を無理やり紫の上系物語に合体させるようなことはしなかった」
とも指摘する。
並びの巻を本編と一体化させるような無理な合体は、作家本人ではなく後世の筆写者による編纂の結果と考えるのだ。
藤本によれば、同様の強引な合体の痕跡は、『宇津保物語』『浜松中納言物語』『枕草子』『狭衣物語』『夜半の寝覚め』など、他にも多くの平安朝作品に見られるという。
●同系統内でも巻ごとに異なるカラー
藤本は、『源氏物語』において複数の物語を合体させて一つのものとした痕跡は、紫の上系物語と玉鬘系物語の間にだけ見られるものではないとし、二つの物語の内部でも、巻ごとに歴然とした不整合が存在し、それぞれが別の作者の手で書かれたものであることを示唆しているという。
『源氏物語』の巻1「桐壷」と巻2「箒木」は、それぞれ紫の上系、玉鬘系という別系統の物語であるため、文体やストーリーの連続性に断絶が見られる。
これについては『源氏物語』の現代語訳を行った明治時代の歌人・与謝野晶子も指摘している。
ところがいずれも玉鬘系とされる巻2「箒木」と巻3「空蝉」、巻4「夕顔」についても、
「光源氏の行動や空蝉の顔貌の描写に違いがありすぎ、時間設定も重なっていて、それぞれに断絶がある」
と藤本はみる。
同じ紫の上系である巻1「桐壷」と巻5「若紫」を比較しても、
「桐壷で重要な役割を演じた右大弁や大蔵卿が突然全く登場しなくなっているなど、不可解な断絶が見られる」
という。
藤本は巻ごとに明らかな相違が見られる箇所をカウントし、
「主要人物の言葉や行動の食い違い」237か所
「端役の言葉や行動の食い違い」115か所
「登場人物の年齢等の食い違い」42か所
「月齢や天候、季節の食い違い」46か所
を挙げている。
●二つの物語の合体はいつ行われたのか
以下は筆者(久保田)の勝手な想像である。
かつて玉鬘系の物語が「並びの巻」として本編と区別されていたということは、『源氏物語』が一般に読まれるようになった当初、紫の上系の物語は玉鬘系の物語とは別の本として、おそらくは先行して世に出たことを示している。
ただその先行期間は、あったとしても短かったようだ。
後述する『更級日記』には上総国(千葉県)から都に戻った著者(菅原孝標の娘)が、使いに出された先の叔母から木箱に入った『源氏物語』50余巻をプレゼントされ、狂喜する場面が出てくる。
これは著者が都に戻って間もない時期、疫病で乳母を失った1021年か、遅くもそれから数年以内の出来事と考えられる。
つまり1020年代には『源氏物語』には、現在と同じ全54巻が揃っていたことになる。
13世紀終盤に成立した『源氏物語』注釈書である『弘安源氏論議』は、並びの巻の存在を認めながらも「その存在理由が不審である」としている(「ウィキペディア」による)。
これはその頃までには紫の上系、玉鬘系が合本されて一つの物語として流通するようになっていたことを示唆している。
一方で前出の12世紀半ばの注釈書『源氏釈』は、並びの巻を無視し、本編のみを注釈の対象としている(「ウィキペディア」による)。
これはその頃には本編と並びの巻が歴然と分かれており、「並びの巻は別作者により後から付け足されたもの」とみなされていたことを示唆している。
上からすると紫の上系、玉鬘系の一体化は、12世紀後半から13世紀半ばにかけての写本の過程で行われたのではないかとも推察できそうだ。
●度重なる書き足しが生んだ読みづらさ
『源氏物語』の文章の読みにくさは古来、よく知られている。
この点は明治の文豪・森鴎外をはじめ、作家も研究者も認めるところだ。
その理由について、本書で紹介されている哲学者で『源氏物語』研究家の和辻哲郎は、
「同じ文章の中に、何人もの登場人物それぞれの視点と作者の視点が混合されている」
と分析している。
藤本はこれを、
「最初の文章の上に第二、第三の人間が自分の視点からの描写や感想を書き足した結果」
と見ている。
こうした文章ルールを逸脱した書き足しは『源氏物語』全体を通じて見られ、藤本のカウントによれば、
「長い文章の間に続きの悪い短文がはさまっている」191か所
「文法的に続かない文章がくっつけられている」200か所
「文章が書きかけの形で入っている」86か所
「終わったはずの話がまた始まっている」46か所
を数える。
平安期にはプロの小説家などは存在しなかったし、今日では当然とされている「文の主語は一つに定め、別な登場人物や作者目線で書く場合は文を分けねばならない」といった散文の基本作法も、まだ確立されていなかった。
そうした状況で必ずしも練度の高くない書き手による書き足しが繰り返されたため、いきおい『源氏物語』の文章は冗長なものとなり、一文にいくつもの視点が混在するような、今日の視点から見れば文章の基本を踏み外した悪文を多く含む作品となってしまったわけである。
「『源氏物語』の巻ごとの内容の断絶や文体の変化、また文章の読みにくさは、現代語訳を見ていてはよくわからない」
と藤本は言う。
現代語訳の場合、読者にとって読みやすくするために訳者が手を入れる結果、矛盾点が後付けで説明されたり、長い文章が分けられるなどして、違和感が大幅に緩和されているからだ。
藤本は『源氏物語』製作に関わった書き手と編纂者の数を、
「総計20名以上」
と推定し、
「一つひとつは短編もしくは中編程度であった物語が、多数の筆写者の手でオリジナルの物語に書き加えられたり、後世の筆写者の手で別の物語と合体させられたりすることで、比較的短かった原初の『源氏物語』が時を経るごとに肥大化し、同時代の世界に類を見ない巨大な長編小説が誕生した」
と推論している。
多くの検証の上に立脚するこの結論は、筆者(久保田)にも納得できるものだ。
≪ 『論語』「学而時習之」の正しい解釈は 『源氏物語』の作者は誰だったのか(中編) ≫