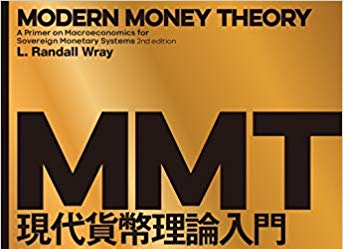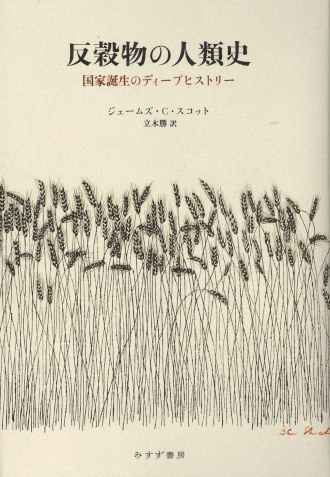
目次
●国家と穀物の関係
今回は人類学者ジェームズ・C・スコットの著書『反穀物の人類史』の紹介である。
本書は人類の農耕と定住が始まり、そこから国家が誕生した過程と、初期の国家が置かれていた環境、国家とその臣民(主に農民)の関係等を論じている。
その主張をざっと挙げると、
「人類は決して望んで狩猟採集生活を捨てて農耕生活に移行したわけではなかった。農耕が発明されてからも、人類の多くは農耕中心の生活を嫌い、狩猟採集民や遊牧民に留まっていた」
「農民の労働時間は狩猟採集民よりはるかに長く、農民の食生活は周囲の狩猟採集民に比べて貧しく、タンパク質、カルシウム、鉄分などの栄養の不足に悩まされており、平均身長は近隣の狩猟採集民に比べて5cmも低かった」
「定住する農民は周囲の狩猟民や遊牧民による収奪のターゲットになってきた」
「初期のすべての国家は、農民から穀物を収奪(徴税)することで経営される農業国家だった。それは狭い土地で毎年同じ時期に同じ量採れる穀物が、徴税の対象として最適だったためである」
「古代メソポタミア文明から古代ローマや中国の歴代王朝に至るまで、古代の国家が支配していたのは、河川下流の沖積層上の穀物栽培地域に限定されていた。それ以外のすべての地域は国家の支配の外にあった」
「農耕が始まったから超過収穫が得られるようになったわけではない。農民は自分たちが食べられる分が収穫できたらそれ以上は耕作しないのがふつうで、納税に充てられた分の収穫は、農民たちが自給分を超えて強制労働させられた結果である」
「農民は重税や伝染病、飢饉から逃れるためしばしば土地を捨てて逃亡し、それにより初期の国家は短期間で崩壊するのが常だった。城壁は外敵の侵入を防ぐためと同時に、農民の逃亡を防ぐためのものでもあった」
「初期国家の戦争の主目的は領土の拡大ではなく、放置すれば減っていく労働力を補充するための奴隷、すなわち戦争捕虜を入手することだった」
「文字と数字は穀物の徴税を記録し、徴税を持続的かつ最大化するために発明された。国家はまた農民を労働力として使役し、壮大な記念碑や建造物を建設した」
「歴史を国家の歴史として描き、農民を臣民、狩猟採集民を野蛮人として描く歴史観は、文字を書ける人間が国家の支配階層にしかおらず、文献を残したのも歴史書を作ったのも国家関係者だった結果である」
「国家は石を用いた建造物や文字を用いた文書を残すが、国家がなければそれらは作られない。このため遺跡と文献が頼りの歴史学の世界では長らく、『国家が存在しない期間は文明の存在しない暗黒時代』と考えられてきた」
「今も昔も歴史学者や考古学者の大半は国家がスポンサーなので、国家中心の史観に偏っている」
といった内容で、半世紀も前に学校で歴史を習っただけの筆者としては初めて知ることが多く、刺激的でおもしろかった。
なお以下では、本の作者であるスコットを「著者」、この文章を書いている私を「筆者」と表記している。
ちょっとわかりにくいと思うが、お許し願いたい。
●気候変動と農耕の開始
著者のスコットはまず、読者との共通理解の土台として、現在知られている人類の大まかな歴史を記している。
ここでも筆者が知らなかったことが多かったので、改めて挙げておくと、
人類の最大の特徴である「火の道具化」は、現生人類(ホモ・サピエンス)の誕生(約10万年前)以前に、原人(ホモ・エレクトス 約180万年前~約10万年前)の時代から始まっていた。
火を使った加熱調理により、それまで食べられなかった多くの植物が消化可能になり、肉類も含めて咀嚼(そしゃく)や消化が楽になった。このため原人以降の人類の歯や消化器官は、類人猿に比べて小さくなっている。
地球は約2万1000年前の最終氷期から約1万年かけて間氷期に遷移し、その間に4~7度気温が上昇している(国立環境研究所 地球環境センターによる)。
紀元前1万2700年頃から紀元前1万800年頃までは比較的温暖で、その頃には人類は、自分たちに都合のよい野生の植物を意図的に増やしたり、都合のよい野生動物を管理するようになっていたことがわかっている。
紀元前1万800年頃から紀元前9600年頃まで1200年ほど、地球は一時的な寒冷期に入り、その後、急速な温暖化が始まった。
地球の温暖化はそれ以降5000年ほど続き、今から6000年前、紀元前4000年頃にピークを迎えた。
日本の縄文時代にあたる。
当時の気温は現在よりも2~3度高く、海水面も今より3~5メートルほど高く、地球は全体として現在より温暖で湿潤な気候だった。
紀元前9600年頃から温暖化・湿潤化していった気候の下で、紀元前8000年から紀元前6000年の間に、中東の一部の地域で穀物や豆類が栽培されるようになった。同じ時期に家畜も登場した。
農耕牧畜の開始である。
初期の農耕は、河川により形成された沖積層の上という、ごく限られた地域に限定されていた。
やがて恒久的な定住地としての原始都市が、紀元前6500年頃、中東のペルシャ湾に近い沖積層の湿地帯に現れ、人工的に掘削した水路とそれを用いた灌漑農業も紀元前6000年代から、中東のメソポタミア、エジプト、イラン等で行われるようになった。
以上が地球と人類について現在わかっている考古学的知見である。
かつての歴史学では、
「農耕は、川沿いの乾燥した地域で河川の水を利用して始まった。農耕により人口が増加し、増えた人口を養うために灌漑が必要とされ、そのために労働力を動員できる組織力を備えた政体が誕生し、国家に発展していった」
と考えられていた。
しかし著者によれば、そうした理解は間違いだったことが判明している。
農耕と定住が始まった当時のメソポタミア南部沖積層は、現在のような乾燥地帯ではなく、湿潤な気候だった。海面は現在よりずっと高く、古代都市のすぐ前まで海が広がっていた。定住地のあった一帯は三角州の湿地が入り組み、雨季になると水路から水があふれて水没する氾濫原だった。
中国最初期の河姆渡(かぼと)遺跡も、インダス文明の初期の遺跡も、こうした湿地帯で育まれた。
こうした土地で行われはじめたのが、イネ科の植物による氾濫農法だった。
洪水でもとからの植物が押し流され、運ばれてきた肥沃な土が広がる平原に、水に強く成長の早いイネの仲間のタネを撒いておく。それだけで、耕作も除草もしないで穀物が収穫できた。
土地は肥沃で水も豊かであったため、穀物以外にも食料には事欠かなかった。周辺には多種多様な植物、魚類貝類、鳥類、よい獲物となる多くの哺乳類が生息していた。
このため現在では、「移動しなくても四季おりおりに多様な食物が手に入る土地であったために、そこに定住地が生まれた」と考えられている。
定住地は水辺にあったため、水路を利用した交易も盛んに行われていた。
●さらなる気候変動と人口の集中
伝統的な歴史学のもう一つの誤解は、「農耕の始まり=国家の誕生」ではなかったということだ。
農耕が始まり、定住が始まり、都市に近い人口密集地域が形成されても、それから数千年間は国家はできなかったのだ。
初期の定住地となった河川下流の湿地帯のように、生物資源が豊かで穀物以外の食物が豊富に得られる環境では、人は多く集まるが、国家は誕生しない。こうした遺跡からは、階級構造の存在を示す遺物(豪華な副葬品など)は出土しない。著者によればそれは、「単一の資源が支配的ではないので、中央からの独占や管理ができないし、簡単に課税もできない」からだという。
狩猟採集の一方で農耕や牧畜もしていた当時の定住地の人々は、収穫に課税されることはなく、豊かな自然の中で様々な食材を得て、自給自足で暮らしていた。
こうした状況が、やがて変化する。
きっかけは気候の変化だった。
まず紀元前6200年頃から、寒冷で乾燥した気候が100年ほど続き、人口が一部の温暖湿潤な地域に集中するようになった。
食料調達の主軸が狩猟採集から農業に移行し、メソポタミアのいわゆる肥沃な三角地帯には、紀元前5000年までに数百の村ができ、作物化された穀物が主食として栽培されるようになった。
この移行がどのような理由で起きたのかについてはまだ定説がないが、有力説として、デンマークのエスター・ボーズラップが提唱した、
「人口の増加、狩猟採集における獲物の減少などの理由で、人々はやむなく農耕の作業量を増やして土地生産性を上げることを選択した」
「農耕への依存は、他に選択肢がなかった状況で、生きのびるための最後の手段として始まった」
という学説がある。
ボーズラップの主張の前提である大型猟獣の減少については、中東でもアメリカ大陸でもはっきり確認されている。
もう一つの前提である当時の人口は、さほど増えていなかった。
世界人口は紀元前1万年から紀元前5000年までの間で、400万人から500万人に変化したと考えられているが、5000年間で25%増は、ほぼ横ばいと言っていい(人口は本書の記述による。根拠は明示されておらず、異説も多い)。
このためボーズラップの主張も全面的には受け入れられていないのだが、重要なのは、
「かつての歴史学で『人類の大きな進歩』と見なされていた狩猟採集生活から農耕生活への転換は、実際には当時の人々にとって決して望ましい変化ではなかった」
という指摘である。
ボーズラップのこの見方は、現在の歴史学では広く受け入れられている。
その理由として、まず農耕は狩猟採集に比べて、同じカロリーを得るために必要な労働時間が長いということがある。
農耕に伴う作業も過酷だった。
「9000年前に死んだ女性が、狩猟採集民の集団ではなく、定住して穀物を育てるコミュニティで生きていたかどうかを調べるには、背中や爪先、膝の骨を調べるだけでいい。穀物を栽培している村の女性は、穀物を挽くために膝をつき、前後に揺れながら長時間の作業をするために、爪先が下向きに曲がり、膝が変形するという特徴がある」
と著者は言う。
今では見なくなったが、筆者が子供だった1960年代ぐらいには、痛々しいほどひどく腰の曲がった老人をよく見かけたものだった。
1950年代半ばまで、日本の産業別就業人口は農業が5割近くを占めていた。
腰の曲がった老人は、田を耕す、収穫する、水を汲むといった腰を曲げて行う長年の農作業の結果、背骨が変形して前屈してしまったのである。
紀元前5000年の古代メソポタミアから1900年代半ばの日本までの数千年間、農民の日常は、体が歪んでしまうほど過酷な労働の連続だった。
加えて農民は狩猟採集民に比べ、栄養状態もよくなかった。
著者によれば、古代の家畜の骨には密集状態で飼育されること、食餌の種類が乏しいことに起因する病変がしばしば見られ、定住して農耕を行うようになった同時期の人間の骨にも、同様の病変が表れているという。
「狩猟採集民と比べて小柄で、たいていは骨や歯に栄養不足の痕跡があるのだ。具体的には鉄不足による貧血で、とりわけ生殖年齢の女性に見られ、食餌中の穀物の割合が急速に高まったことを示している」
しかし、このように過酷で不健康な生活ではあっても、農民の人口増加率は狩猟採集民よりはるかに高かった。
世界人口は紀元前1万年から紀元前5000年までの5000年間で25%しか増えなかったが、農耕が始まった紀元前5000年から紀元0年までの5000年間には20倍の1億人以上(本書の記述による。一般には「数百万人から2億人以上に増えた」とする説が多い)に増え、増えた人口のほぼすべてが農民だった。
こうして人類史は、狩猟採集民の時代から農民の時代に移っていく。
●人口集中の実態
紀元前4000年頃をピークとする地球温暖化が反転したことで、古代メソポタミアでは紀元前3500年から紀元前2500年にかけて寒冷化・乾燥化・砂漠化が一段と進み、ユーフラテス川の水量は減少し、海水面も低下して、それまで海沿いにあった定住地は海から遠ざかった。
人々は水と耕作可能な土地を求めて、残った河沿いの水路の周辺に集まるようになった。
結果、「人口密度は、先史時代の社会がほとんど到達したことのない水準に達し」、増えた人口を養うために、一定面積の土地から最大限の収穫を引き出そうとする、労働集約的な農業が広まった。
地球の寒冷化と乾燥化の過程で、メソポタミアの人口が河沿いの土地に集中するようになったことは、考古学的な事実である。
その実態はどのようなものだったのだろうか。
素直に考えれば、乾燥化で食料調達の手段を失った人びとが河沿いの緑地に集まっていった――ということになりそうだが、彼らが集まろうとした緑地には、すでにそこを耕作し、自分たちの土地と認識している住民がいた。
よその土地で飢えた人間たちが自分たちの土地に押し寄せてきたとき、元からいた住民はどうしただろうか。
よそ者を歓迎して受け入れ、自らの土地に住まわせただろうか?
そんなことはありえない、と筆者は考える。
人間には、というより狩りをする動物のすべてには、縄張りを持ち、それを守ろうとする習性がある。自分たちの土地によそ者が続々と侵入してきたとき、それを黙って見過ごす集団はいない。
自分たちの土地で勝手に狩猟したり、まして勝手に農耕を始めた侵入者を発見すれば、以前からそこに住む男たちは手に手に鋤(すき)や鍬(くわ)を持って飛び出してきて、「すぐに出ていけ! 出ていかなければ殺す!」と恐ろしい勢いで追い払ったはずである。
一方、追い立てられた侵入者たちも、「はい、そうですか」と出ていくわけにはいかなかった。
なにしろ、それまでいた土地は乾燥化で草木は枯れ、狩猟すべき動物も、採集すべき植物も消えてしまっている。戻れば飢えて死ぬしかない。なんとかしてこの数少ない緑地にしがみついて、自分たちの居場所を無理やりにでも作るしか、生きる道はないのだ。負けて追い出されれば家族全員、一族全員の餓死が待っている。
両者の間には、血で血を洗う凄惨な戦いが繰り広げられたはずだ。
先年亡くなられた作家のC・W・ニコルさんはエッセイの中で、「世界各地の人の性格は、その土地に水が豊かであるか乏しいかで異なる」と書かれていた。水の豊かな土地は、人びとの気質も穏やかなのだという。日本はその典型である。
やはり先年亡くなられた、アフガニスタンの地に自ら灌漑水路を拓いた日本人医師・中村哲さんを描いたテレビのドキュメンタリー番組では、干魃に苦しむアフガニスタンで、残された井戸に集まった人びとが、わずかな水をめぐって殴り合い、取っ組み合いの争いをする様子が流れていた。
湿潤な気候が次第に乾燥化し、土地が砂漠へ変わっていった地域の住民はおそらく、家族の命を賭けた水争い、土地争いを何代にもわたって繰り返してきたはずだ。その過程で必然的に気性も荒んでしまうのだろう。
残された緑地をめぐる戦いの多くは、先住民側の勝利で終わったのではないか――と、筆者は考える。
先に専有していた側が立場的に有利だということもある。また農耕は狩猟採集に比べて、単位面積当たりで養える人口がはるかに多く、近隣同士で共闘することも可能だ。
一方の狩猟採集民は、広い地域に散らばって暮らしている。そうしないと獲物を狩り尽くしてしまうから、分散が必然なのである。
結果として守る側は侵入してきた側に対し、数的に有利な状態で争えることが多かったはずである。
以上を踏まえると、乾燥化の過程での人口の河沿いへの集中は、おそらく「そこに人が集まってきたこと」で起きたのではないと考えられる。
乾燥地から逃れてきた人びとが排除され、生存手段を失って斃死(へいし)する。一方で河沿いの土地を死守した人びとは、農地の生産性に支えられて人口を増やしていく。
それにより、見かけの「河沿いへの人口の集中」が起きたのだろう。
●国家は穀物から生まれた
いずれにせよ、こうしたメソポタミアの沖積層におけるライフスタイルの変化から、史上初めての国家の群が誕生する。
著者は国家の定義を、
「王と専任の行政スタッフがいて、社会的階級があり、記念碑的なセンターがあって、市が城壁で囲われ、税の徴収と分配が行われていること」
としている。
そのような国家が登場するのは、紀元前3000年代後半のことだった。
地球上でもっとも早く国家が誕生したのは古代メソポタミアで、紀元前3200年までにはバビロニアのウルクに国家が確立し、遅くも紀元前2000年までには、キシュ、ニップル、イシン、ラガシュ、エリドゥ、ウルなどの都市国家が出現した。
「国家の誕生=階級の誕生」でもあった。
国家の誕生と時を同じくして、自らは耕作せずに農民に耕作させ、収穫物を上納させる階級が現れ、農民を支配するようになったのである。
初期の国家は脆弱で、できては壊れ、できては壊れていた。
国家が生まれ始めてからも数百年の間、それは常に存在するものではなかった。
「王国のあった期間よりも空白期間の方が一般的で、崩壊と分裂が長く続くのは当たり前だった」と著者はいう。
各国家の崩壊の原因ははっきりしていない。当時、歴史を記録していたのは国家公務員だけだったので、国家の崩壊が始まると、記録する人間がいなくなってしまうからだ。
国家が消える原因としては、疫病の蔓延、凶作による飢饉、農民の逃亡などがあった。
初期の国家は狭い範囲に密集して人が住む地域に発生したが、そのような地域は疫病が発生する可能性も高かった。
下水システムがない中での人口の集中は衛生状態を悪化させ、人畜に伝染病を頻発させた。文字記録が利用できるようになって以後については、悲惨な伝染病の証拠が豊富にあり、有名な『ギルガメッシュ叙事詩』でも、ペストで斃れたと思われる死体の数々がユーフラテス川を流れていく様が語られている。
疫病による人口減少だけでなく、疫病を恐れた農民の地域外への逃亡によっても、国家は崩壊した。
特定品種を集中して育てたことで、農作物にも病虫害が頻発した。当時の中東では、いくつかの作物が連続して虫や鳥による食害、あるいは病気で壊滅状態となることも珍しくなかった。
そういった事態が起きると農民は生きていけなくなり、死ぬか逃げるかする。重税を課せられた農民が土地を捨てて逃亡することも少なくなかった。支配地域から人がいなくなると、国家は滅びた。
国家は農民から徴収する穀物に依拠(いきょ)していたが、その農民は「事実上、生存できるぎりぎりの線で生活していた」(著者)から、国家が倒れるにはちょっとしたきっかけがあれば十分だった。
国家が出現した場合も、それが支配する範囲はごく限られた地域だった。
「国家は本質的に農耕民で構成されるので、その範囲は世界にわずかしかない耕作好適地にほぼ限られていた」(著者)
それ以外の地域、つまり世界の大部分には、国家の支配の手は及ばなかった。
著書は、
「古代の最初の主要農業国家――メソポタミア、エジプト、インダス川流域、黄河――の生業基盤はどれも驚くほど似通っている。すべて穀物国家で、小麦や大麦、黄河の場合はヒエやアワなどの雑穀を栽培していた」
「湿地帯の豊かさが初期の都市化と商業につながることはあったが、大規模な穀物栽培なしに国家形成が起こることはなかった」
と指摘し、
「中東ではとくにレンズマメ、ヒヨコマメ、エンドウマメなどの豆類が、中国ではタロイモ、大豆がすでに作物化されていたのだ。なぜ、こうしたものは国家形成の基盤とならなかったのだろう。(中略)こうした栽培品種の多くは、土地1単位当たりで得られるカロリーが小麦や大麦よりも多く、労働力が少なくて済むものもある」
と疑問を呈している。
なぜ穀物のみが国家の基盤となったのか。
著者はその理由を、
「なによりも収奪の容易さと効率にある」
としている。
狩猟や漁労、遊牧、焼畑農業などは、移動範囲が広いので徴税コストが高くつき、得られたものも貯蔵性が低く長距離の運搬に適していないため、財政の基盤には向いていなかった。
一方、穀物は毎年同じ時期に同じ場所で熟し、農民の手で収穫され、集められ、保管される。
「軍隊や徴税役人は、正しい時期に到着しさえすれば、1回の遠征で実りのすべてを刈り取り、脱穀し、押収することができる」
「ただ待っていれば作物は脱穀され、貯蔵されるので、あとは穀物倉の中身をごっそり押収すればいい」
という手軽さがあった。
同じ栽培種でも大豆やエンドウマメなどの豆類は、「長期間にわたって継続的に実をつけること」が問題だった。「徴税官の側はワンストップ・ショッピングで済ませたいので、成熟期の決まっている作物が最適なのだ」という。
またイモ類は一気に収穫する必要がなく、地中にそのまま残しておいて、食べたいときに掘り出せばいいので、徴税する側はやりにくい。長距離の運搬にも不向きだった。
「軍隊や徴税官がイモをほしいと思ったら、農民がするようにひとつずつ掘り出さなければならない」
「荷車1台分のジャガイモは同じ荷車に積んだ小麦と比べるとカロリー面においても市場においてもずっと価値が低い上、すぐに腐ってしまう」
といった問題があった。
もっとも豆類の中でもヒヨコマメやレンズマメは成熟期が決まっていて、なぜそれらが穀物のように扱われなかったのかについては、「まだよくわからない」と著者は述べている。このあたりはなかなか正直である。
いずれにしても穀物は、土地面積あたりの収量、カロリーが高い上、貯蔵性がよく、運搬にも適していた。しかも毎年決まった時期に実り、地中や水中に隠しにくく、細かい単位に分割もできるので、徴税が容易だった。同じ特性から通貨代わりに用いるのにも適していた。
それが初期の農業国家が穀物に依存していた理由だった。
だからこそ初期の国家は集中的な穀物生産に好適な、生態学上のわずかなニッチにしか存在していなかった。
このあたりの著者の議論には説得力がある。
●国家の事業と労働力の確保
国家は徴税のために記録を必要とし、その必要のために数字と文字を生み出した。
初期のメソポタミアでは文字は簿記目的ためだけに使われ、年代記や文学、宗教書などが文字で記されるようになったのは、文字が生まれて500年以上経ってからだったという。
文字は徴税の手段であったため、初期国家で読み書きできるのは全人口のうちわずかしかおらず、その大半が役人だった。文字は徴税を象徴するものであり、一般の人々からは忌み嫌われていた。国家が崩壊すると、文字による記録も消滅するのが常だった。
古代に独自文字によるミノア文明、ミケーネ文明が栄えたギリシャの地中海沿岸でも、紀元前1200年頃にはそれらを担った都市国家が滅び、その後400年ほど文書記録のない時代が続いた。
この間、宮殿は放棄され、交易は大幅に減少し、古代文字も忘れられてしまった。
その後、紀元前800年頃になると、今度はアテネやスパルタなどの新たなポリスが形成されて新しい文明が栄え始める。が、そのとき使われたのはミノア文明やミケーネ文明で使われたのとは異なる文字だった。
交通や灌漑のための水路も、国家が生まれると、農民への賦役や奴隷による労働によって掘削されるようになった。
国家が徴税できる範囲は、穀物を輸送可能な範囲に限られる。輸送範囲=国家の勢力範囲だった。そして長距離輸送は陸路より水路のほうがはるかに容易だったので、水路の拡張は国家の最大関心事の一つだった。
「平らな沖積平野で役畜と荷車を使うと仮定すると、最初期の国家が穀物を輸送できる範囲は、半径48キロメートルを大きく超えることはなかったろう」
と著者は指摘する。
水路がなければ、半径50キロ以上の国家は成立し得なかった。
有名な古代国家がすべて大型河川のほとりにあるのは、こうした事情からである。
国家のもう一つの大きな関心事が、労働力の確保だった。
「逃亡をあきらめさせるためにあらゆる手を尽くし、逃亡者を罰しても――実際に、最古の法典はそうした禁止命令であふれている――通常の環境下では、古代国家はある程度の漏れを防ぐことはできなかった」
「大半の古代国家がさまざまな手段で損失を埋めようとした。これには、戦争によって奴隷を獲得する、奴隷商人などから奴隷を購入する、コミュニティ全体を穀物コアに強制的に移住させる、などが含まれる」
「戦争の戦利品は領土よりも捕虜のことが多かった」
「国家は逃亡と死亡による損失の補填につねに苦慮していて、だいたいは強制的な軍事作戦によって、それまで課税も規制もされなかった人びとのなかから新しい臣民を囲い込んでいた」
「戦争の大多数は、強大で有名な都市政体同士のものではなく、そうした有力政体が自国の後背地にある小規模な独立コミュニティを征服して労働力を増強しようとした、小規模戦争だった」
このような表現で著者は、「古代国家の支配者層にとって、国民は労働力であり、自分たちがそこから利益を得るための家畜であった」ことを強調している。
●都市国家の崩壊と古代王朝の誕生
国家はこれまでに挙げた原因の他、遊牧民の侵入や長期の気候変動(寒冷化)によっても崩壊した。
森林の伐採も国家衰退の原因となった。
国家は人口が集中する定住地を基盤としていたが、こうした定住地は燃料や建材として大量の木材を必要とした。燃料は暖房や調理のためだけでなく、塩や鉄や漆喰、土器、陶磁器の生産にも使われ、建材としては家屋以外に船を作るためにも必要とされた。
人口密度の高い地域では、周辺の森林はあっという間に刈り尽くされてしまう。都市国家がある程度の期間存続するためには、水路を用いて上流の森林で伐採した木材を搬入することが不可欠だった。
だが森林の伐採はその保水機能を失わせ、下流にある都市に洪水被害をもたらした。
やがて水路で運べる範囲の森林が伐採され尽くしてしまうと、都市はそれ以上の燃料と建材を得られなくなり、密集した人口も拡散せざる得なくなる。国家はそれによっても滅びた。
農地の疲弊も国家衰退の原因の一つだった。
乾燥地域で灌漑農法を行うと、蒸発で水分中の塩類が濃縮されて土壌に蓄積し、やがて塩分濃度過剰で穀物が育たなくなってしまう。いわゆる塩類集積である。それによって優良な耕地が失われることによっても、国家は滅びた。
それでも都市国家が盛衰を繰り返すうちに、次第に長続きする王朝も出現するようになった。
メソポタミアでは紀元前3000年代にシュメール人による都市国家が興亡を繰り返し、その後、紀元前2300年頃、サルゴン1世がメソポタミア全域の都市国家を統一してアッカド王国を築いた。
アッカド王朝は11代、約180年続いて滅んだ。
それから120年ほど経つとウル第3王朝が出現し、100年ほど続いた。
その滅亡から100年ほどして古バビロニア王国が勃興し、ここでは300年ほど多くの文書資料が作られた時代が続いた。
しかし著者は別の歴史学者の言葉を引用して、「これらの王朝が存在した紀元前2500年から紀元前1600年にかけての900年間を通して見ると、そのうち自らの年代記を残すほどの王国が存在していたのはトータルで200年ほどであり、残り700年間は分裂と分散の時代だった」とする。
王国が300年続いたといっても、年代記が残されるような国家支配の盛期は、そのうちごくわずかの期間にすぎなかったようだ。
古代エジプトでは紀元前3000年頃、メネス王が上下エジプトを統一し、最初の統一国家を作った。
エジプトではその後、紀元前332年にアレクサンドロス大王に征服されるまでの2700年間で31の王朝が交替したとされる。その中の第3王朝から第6王朝まで、時代にして紀元前2650年頃からの約500年間は、古王国時代と呼ばれている。
こうした歴史を見ると、誕生と崩壊を繰り返していた古代の都市国家も、紀元前3000~2000年頃からは一部の国家が安定してきて、数世代を超えて継続される王朝国家が成立するようになったことが伺える。
長続きしなかった古代都市国家と100年以上続く王朝との違いは、どこにあったのか。
気になるところだが、これについては著者は何も語っていない。
●国家はなぜ生まれたのか
著者は、
「古代オリエントの村々は植物を作物化し、動物を家畜化した」
「一方、古代国家ウルの都市制度は人間を家畜化した」
という歴史家の発言を引用し、国家は農民が望んで創った民主組織ではなく、農民の意思に反して一方的に作られた支配組織だったことを示唆している。
著者によれば、初期国家の国政の原則は、「人を集め、権力の中核近くに住まわせ、その場所を離れさせることなく、必要を超えた余剰物を生産させること」であり、国家は「飼い馴らした臣民」の数と生産性につねに焦点を当てていて、それは羊飼いが羊の群れの維持に腐心するのと変わらなかった。
その際は「一方では国家余剰を最大化したいが、他方では臣民の大量逃避を誘発するリスクがあって、微妙なバランスをとる必要」があった。
戦国の覇者となった徳川家康が、「農民は生かさず殺さずがよい」と言っていたことはよく知られているが、支配する側の発想は、洋の東西を問わずよく似ている。
灌漑や交易は、国家ができて盛んになったが、実際にはそれ以前から行われていた。
人口増大や気候変動により、人びとが食料を主に農耕で得るようになって以降も、自給自足で生存していく上で、国家は別に必須ではなかった。
だとすれば、国家の誕生に必然性はないことになる。
人びとが必要としないものだったのなら、なぜ国家は生まれたのだろうか。
この問いに対して著者のスコットは、「わからない」としている。
凶作や伝染病と並ぶ農民の脅威、それは外部の手による略奪である。
乾燥化で周囲から逃げてきた侵入者を排除し、河沿いの緑地を死守した農民たちも、それで安心できたわけではなかった。
略奪する食料の対象としてもっとも適していたのが、穀物だったからだ。
収穫時期が定まっており、収穫後は倉庫にしまわれ、貯蔵性・運搬性が高く、分割も容易なため交易における通貨としても使われる。穀物が徴税に適する条件はそのまま、穀物が略奪に適する理由に等しい。
「定住コミュニティは、移動性の狩猟採集民にとっては、集中的な採集ができる最高に魅力的な場所だった」
と著者は指摘している。
虎視眈々と農作物を狙う非農民たちは、可能であれば農民の目を盗んで、そうでなければ力づくで、食料を守ろうとする農民たちを襲い、備蓄された穀物を奪った。
あるいは農民たちはそうした略奪に対抗するため、自ら兵を雇い、国家を建てたのだろうか?
その可能性はないわけではない。しかし、実際には考えにくい。
自衛を目的としてつくった国家に、毎年収穫の一部の上納を強要され、賦役まで課されるのでは、外敵に支配されるのと変わらない。そんなことを農民たちが自分から望むとは思えない。
著者スコットもこう指摘している。
「もし略奪民が定住コミュニティを攻撃して家畜や穀物、人、貴重品を持ち去ってしまえば、その定住地は破壊されてしまう。(中略)まさに金の卵を生むガチョウを殺すことになる」
「それがわかっているから、略奪者はむしろ「みかじめ料」を取る方向へ戦略を変更したと考えられる。交易商品、収穫物、家畜、その他の貴重品の一部を受け取る見返りに、交易者やコミュニティをほかの略奪民から――そしてもちろん自分たちから――「守る」というわけだ」
「安定的なみかじめ料の取り立ては、実は古代国家のしていることそのもので、両者の区別はほとんどない」
●古来、国家は暴力団だった
著者が本書で強調しているのは、「初期の国家とは『安定的な略奪者』だった」ということである。
これを筆者なりに敷衍(ふえん)すると、おそらく国家とは、そもそも誕生の時点からそうした存在だったのではないか。
つまり「国家は古代の農耕地域において『農民からみかじめ料を徴収する略奪者』として発生した」ということだ。
今はあまり聞かなくなったが、昭和までの日本の繁華街には「ヤクザ」と呼ばれる集団がいて、それぞれに縄張りを持ち、自らの縄張りの中の店舗から「みかじめ料」と呼ばれる上納金を徴収していた。
強制力もない相手にカネを差し出す店はないから、みかじめ料を徴収するヤクザはみな、言うことを聞かない相手を脅して従わせる暴力を備えていた。ヤクザが暴力団と呼ばれる所以(ゆえん)である。
暴力団=ヤクザは、どこから出てきたのか。
「山口組が関西から東京へ進出してきた」というように、外部から侵入してきた場合もあっただろう。
しかし外からヤクザが来るような街は、そもそもヤクザが存続できる条件が整った地域であって、そうしたところではほとんどの場合、外部から来る前に内部で自然発生的にヤクザが出現し、みかじめ料を徴収していた。
おそらく、国家の発生も同じだった。
繁華街にヤクザが自然発生し、暴力をちらつけせてみかじめ料を徴収するように、穀物を栽培する農村に国家という寄生集団が自然発生し、兵や軍という暴力装置で威嚇しつつ、年貢を徴収するようになった。
彼らは年貢を徴収する代わりに、自ら備えた暴力装置によって外部の略奪者に対し、農民を守った。守ったのは農民が自分の飯の種だからで、羊飼いが羊泥棒から羊を守るのと同じである。
支配した農民には年貢に加え、賦役も課した。賦役とは、暴力装置で強制する労働である。強制労働によって神殿や記念碑や自分たちの城を建設させ、外敵の侵入や農民の逃亡を防ぐための城壁をめぐらし、水路を掘削し耕地を増やして税収の嵩上げをはかり、道路を整備し関所を設けて通行料を徴収した。
日本の戦国時代、領主たちは兵を養い、領土を奪い合って他の領主と戦闘していた。領土というと抽象的だが、実際に奪い合っていたのは、年貢を生産する農地と農民である。
農民は自分から「支配者がほしい」とか「年貢を納めたい」などと望んだわけではない。
誰がどこの領主になるのかは、領主同士が戦争して勝手に決め、農民は勝った領主におとなしく年貢を納め賦役に使われるしかなかった。
領主層からすれば領民とは、自分たち支配者がそこから利益を得るための存在であり、奪い合いの対象だったのである。
事情は創成期の大和朝廷も同じだったはずだ。
大和朝廷による出雲の国譲り神話は、戦国時代と同じく農民の支配権をめぐる領主間の争いだし、東北の蝦夷(えみし)の征服は、これまで遠方で勝手に耕作していた農民のところに出張っていって、兵という暴力装置を見せつけ、年貢や賦役を強制する過程だった。
古代オリエントと同じく中世の日本でも、文字を書き歴史書をつくれるのは支配者階級だけだったから、古事記から太閤記に至るまで文字資料は常に支配者目線で、支配される側の視点などは無視されている。
しかし事実を見れば、古代から中世まで、国家とは暴力装置によって「みかじめ料」を徴収する、暴力団そのものだった。
そのように理解することで国家が、地球が温暖湿潤な気候から寒冷化と乾燥化に向かった時期に成立した理由も見えてくる。
現代でいえば熱帯の東南アジアなどがそうであるように、一年中温暖で湿潤な地域では、人びとは食料をあまり備蓄しない。それは食料が不足する「冬」がないからだ。
こうした地域では一年のいつでも米をはじめとする穀物や野菜の作付けが可能で、年に何度も収穫できてしまう。当然ながら、一度に大量の穀物を植え付け、一斉に収穫して、倉庫に蓄えたりはしない。
これはみかじめ料徴収で生きている国家にとっては、都合のよろしくない環境である。
そもそも自分では働かず、人の上前を刎(は)ねて楽をしようという心がけの悪い連中だから、みかじめ料の徴収でもなるべく手間をかけず、年に一度で済ませたいのである。
その上こうした地域では、田畑以外にも周囲の自然環境に採集可能な食料がいろいろある。脅されて食料を奪われるようなことが続けば、みんな嫌気がさして、田んぼは放棄してどこかへ逃げてしまう。
みかじめ料を徴収する連中からしたら、
「ああっ。やつら、逃げやがった!」
で、飯の食い上げ。
これでは国家は成立しない。
そこにいくと古代メソポタミアやエジプトのように、乾燥化が進んで周囲は砂漠となり、河沿いの狭い地域に肩を寄せ合うようにして田畑を耕し、かろうじて生きている農民は、どこにも逃げ場がない。
砂漠に逃げれば飢えて死ぬし、河沿いは人が密集しているので、どの土地にも持ち主がいる。
そうなるといくらみかじめ料を取り上げられるのが嫌でも、生きるためには目の前の土地にしがみつくしかない。
しかも寒冷化した地域では、年に一度しか穀物が穫れない上、冬には食料が枯渇する。このため農民は冬に備えて一度に大量の穀物をつくり、備蓄しなければならない。
みかじめ料を取る連中からすれば、これは楽ちんである。年に一回、倉庫に穀物が溜まったところで徴発しに行けばいい。
兵という暴力装置を背に穀物を奪っていく国家は、農民たちの生殺与奪の権を握っている。寒冷地域の農民は、冬の間の食料をすべて奪われたら、飢えて死ぬしかない。「逆らったら餓死させられる」となれば、いきおい国家の支配力も強まる。
もちろん本当に農民を餓死させてしまったら、来年からみかじめ料が取れなくなる。したがって、そういう目に遭わせるのは一部の反抗的な者にとどめ、その他大部分の農民については、備蓄全部は奪い取らず「生かさず殺さず」で押さえておいただろう。徳川家康の心がけである。
こうして国家は誕生し、搾り取った税金でさらなる暴力を蓄え、世界中に支配圏を広げていった。
現代社会では、世界中のほぼすべての土地が国家によって分割され、人類のすべてがその管理下にある。
支配者だった国家は今では逆に、国民を主権者とし、それに奉仕するためのシステムとして定義されている。少なくとも、民主主義国家ではそうなっている。
だがそれは果たして、国家の本来の姿なのだろうか。
本書『反穀物の人類史』は、現代人の常識をフィルターとすると見えなくなってしまうそうした歴史上の真実に、改めて目を開かせてくれる、良質な啓発書であると思う。
≪ 『現代貨幣理論(MMT)入門』 2 お金とは何か